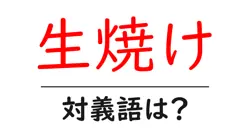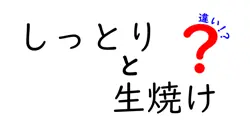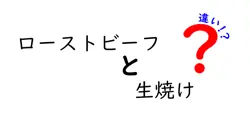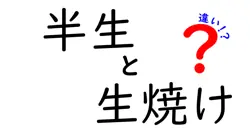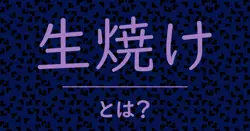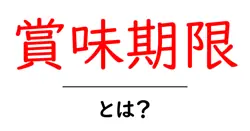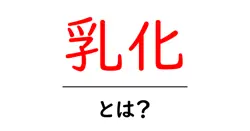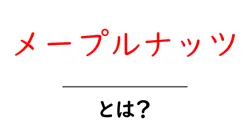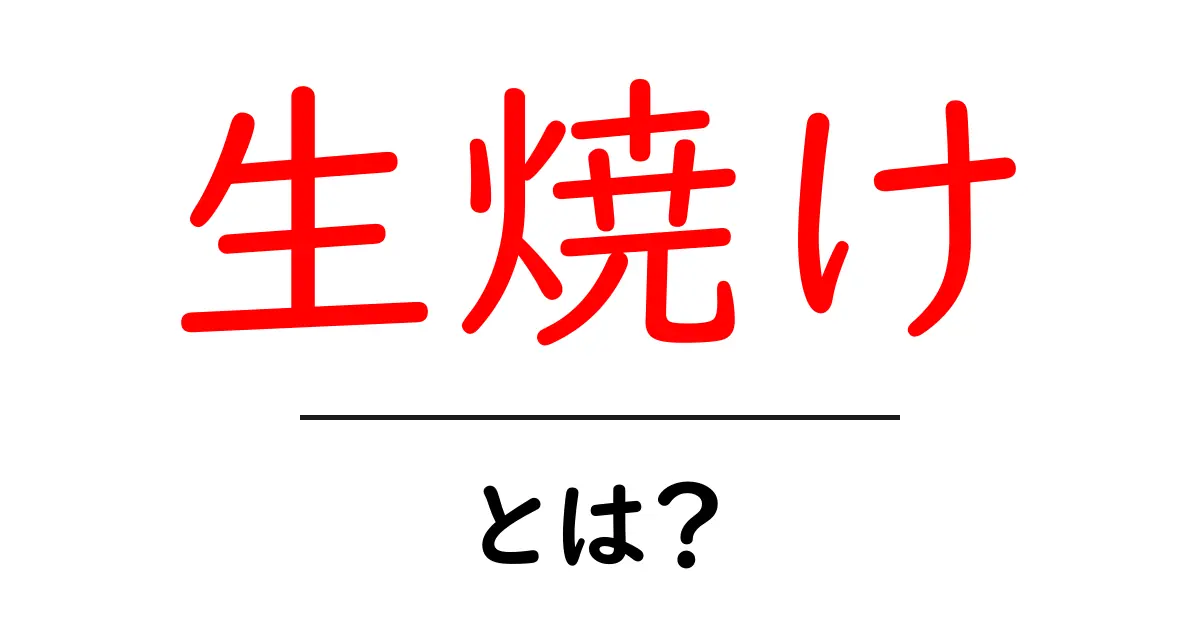
生焼けとは?
生焼け(なまやけ)という言葉は、料理に関する用語で、食材が十分に加熱されていない状態を指します。特に、肉や魚などの動物性食品では、中心部が生のままであることが多く、食べると危険な場合があります。
生焼けの商品の例
| 食品 | 生焼けになると危険な理由 |
|---|---|
| 鶏肉 | サルモネラ菌に感染する恐れがある |
| 豚肉 | トキソプラズマなどの寄生虫がいる可能性がある |
| 魚 | 寄生虫や病原菌が心配される |
生焼けの危険性
生焼けの食品を食べてしまうと、様々な病気の原因になることがあります。特に、感染症にかかる危険性が高く、しっかりと加熱することが大切です。たとえば、鶏肉や豚肉は中心温度が75度以上になるまでしっかり焼かなければなりません。
生焼けを見分ける方法
生焼けかどうかを見分けるためには、以下のポイントに注意しましょう。
- 中心部がピンク色や透明でないか確認する
- 肉汁が透明でない場合は生焼けの可能性がある
- 外側が焼けていても中が生のことがあるため、切ってみるのが確実
安全に料理をするために
安全に食事を楽しむためにも、料理の際はしっかりと加熱しましょう。特に肉類や魚は、十分な温度で調理しなければ、家族や友人を危険に晒してしまいます。
それでも、どうしても生の状態を楽しみたい場合は、食材の鮮度を確認し、信頼できる店舗で買うようにしましょう。また、生食できる魚(刺身など)の場合は、新鮮さが重要です。
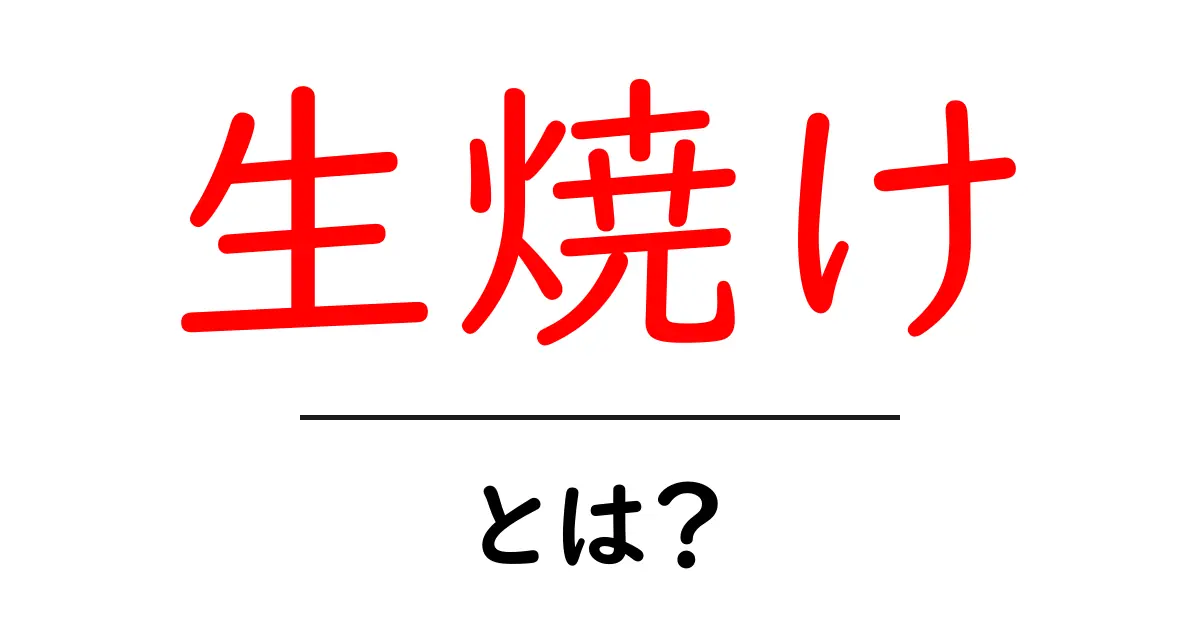
食中毒:生焼けの食材を食べることで発生することがある、細菌やウイルスによる感染症です。特に生肉や生魚に注意が必要です。
焼き加減:食材を調理する際の焼く程度のこと。生焼けは焼き加減が不足している状態を指します。
内部温度:食材が中心部まで温まる際の温度のこと。生焼けを避けるためには、適切な内部温度に達することが重要です。
食品衛生:食品を安全に取り扱うための規範や知識のこと。生焼けの食材を扱う時は、食品衛生に十分配慮する必要があります。
肉類:特に生焼けになりやすい食材の代表。鶏肉や豚肉は、十分に加熱しないと危険です。
魚介類:刺身など生で食べることも多いが、加熱不足の場合は生焼けとなり、食中毒の危険性が高まります。
火の通り:料理において、熱が食材全体に均一に伝わること。生焼けを避けるためには、十分な火の通りが求められます。
調理法:食材を調理する方法のこと。焼く、煮る、揚げるなどがあり、調理法によって生焼けのリスクが変わります。
見た目:生焼けの食材は、中心部分が生のまま残っているため、見た目が生っぽくなっています。
食べかけ:食材が十分に加熱されていない時に中途半端に食べてしまうこと。生焼けの食材は健康に影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。
半生:料理が完全に火が通っていない状態で、中心部が生または少しだけ火が入った状態を指します。
未加熱:焼く、煮る、揚げるなどの調理が行われておらず、生のままであることを示します。
生煮え:煮るべき食材がまったく加熱されておらず、特に煮込み料理において、火が通っていない状態を意味します。
レア:特に肉料理において、外側だけが焼かれ、中は生に近い状態を表します。ステーキなどでよく使われます。
生焼き:料理が焼かれた部分と生の部分が存在する、特に焼き物において十分に加熱されていない状態です。
生焼け:料理が十分に加熱されておらず、中心部が生の状態のこと。食材によっては、食べると健康に害を及ぼすことがあるので注意が必要です。
食中毒:加熱が不十分な料理や衛生状態の悪い食べ物を食べることによって引き起こされる、体調不良のこと。生焼けの肉や魚を食べた場合に生じることがある。
焼き加減:料理を焼く際の加熱の程度を指し、レア、ミディアム、ウェルダンのような表現で示されます。生焼けは焼き加減が不十分な状態を指します。
食品衛生:食品が安全であるために遵守すべき衛生基準や管理方法。食材の生焼けを避けるためには、温度管理や調理法が重要です。
中心温度:料理の内部の温度を測定したもので、特に肉料理において安全に食べられるかどうかの判断基準となります。生焼けを防ぐためには適切な中心温度に達することが重要です。
加熱処理:食材を一定の温度で加熱することで、微生物を殺菌したり、食材の食感や風味を引き出したりする工程。生焼けを防ぐためには、十分な加熱が必要です。
レア:肉料理の焼き加減の一つで、表面が焼かれ、内部が赤くまだ生に近い状態を指します。生焼けではありませんが、適切な食材の場合のみ安全とされています。
フードセーフティ:食品の安全性を確保するための考え方や取り組み。生焼けを防ぐためには、調理する際の衛生管理や加熱温度の確認が重要です。