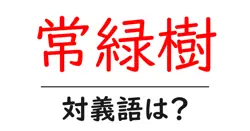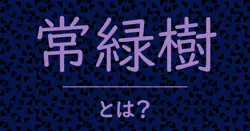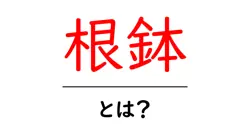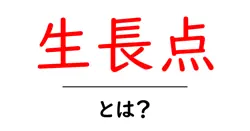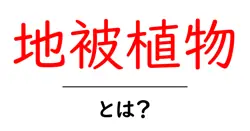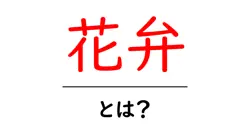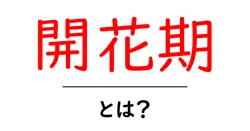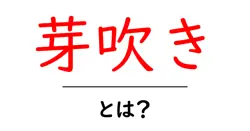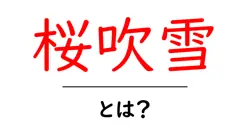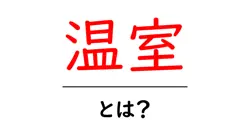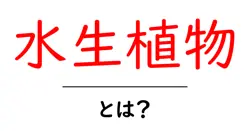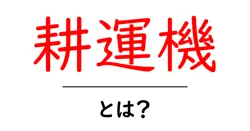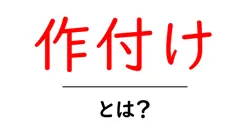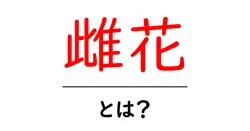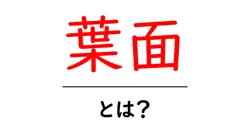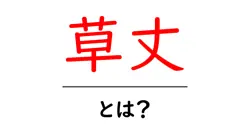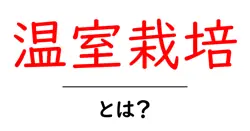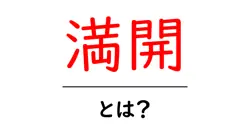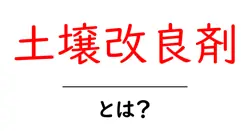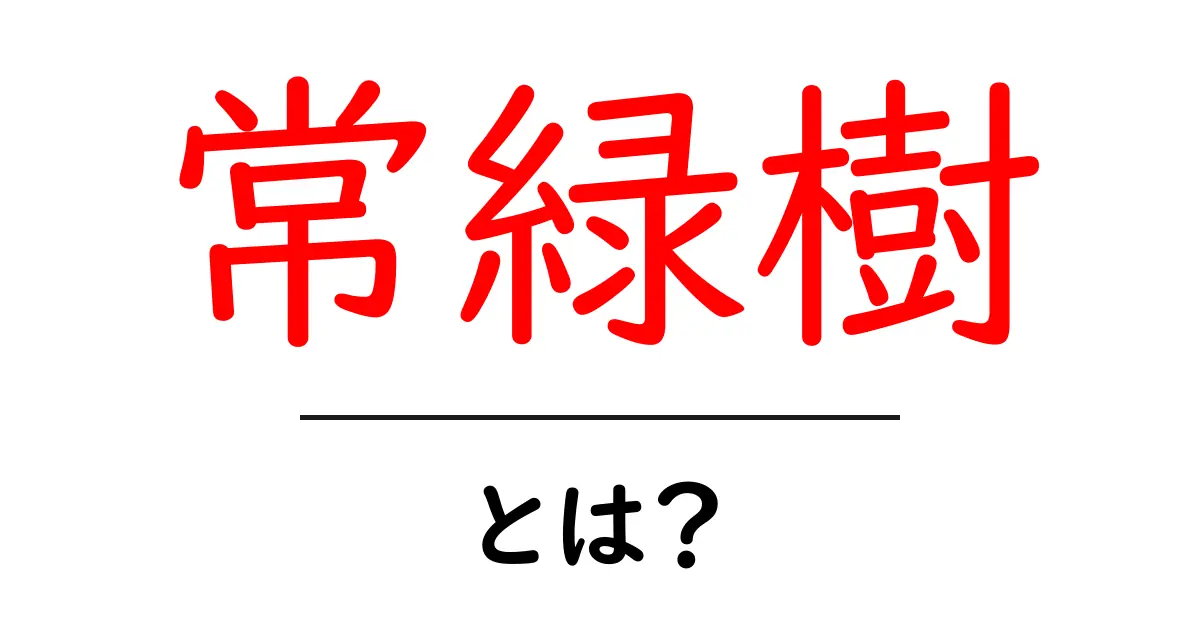
常緑樹とは?その特徴や育て方をわかりやすく解説!
「常緑樹(じょうりょくじゅ)」という言葉を聞いたことがありますか?常緑樹とは、季節に関係なく葉が落ちず、緑の葉を保つ木のことを言います。この記事では、常緑樹の特徴や育て方について詳しく説明します。
常緑樹の特徴
常緑樹にはいくつかの特徴があります。まず、その名の通り、常に緑色の葉を持っています。これに対して、落葉樹(らくようじゅ)は秋になると葉を落とします。常緑樹は寒い冬でも葉が落ちないため、景観を保つのに役立ちます。
常緑樹の種類
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| ヒノキ | 香りが良く、木材としても人気 |
| モミ | クリスマスツリーによく使われる |
| ツツジ | 美しい花を咲かせる |
常緑樹の育て方
常緑樹を育てる際には、いくつか注意が必要です。まず、日当たりの良い場所を選びます。十分な光が当たると、元気に育ちます。また、地面の水はけも大切です。水が溜まると根腐れを起こすことがあるため、適度に水を与えるようにしましょう。
土壌について
常緑樹は一般的に酸性から中性の土壌を好みます。土壌を選ぶときは、農業用の土や腐葉土を混ぜることを検討してください。
常緑樹の利点
常緑樹は、景観を美しくするだけでなく、風よけや騒音の防止にも役立ちます。また、四季を通じて緑を楽しむことができるので、気持ちも明るくなります。
まとめ
常緑樹は、季節を問わず葉が落ちず、緑の美しい木です。育て方も比較的簡単で、多くの利点があります。庭や公園で目にすることが多い常緑樹を育ててみてはいかがでしょうか?
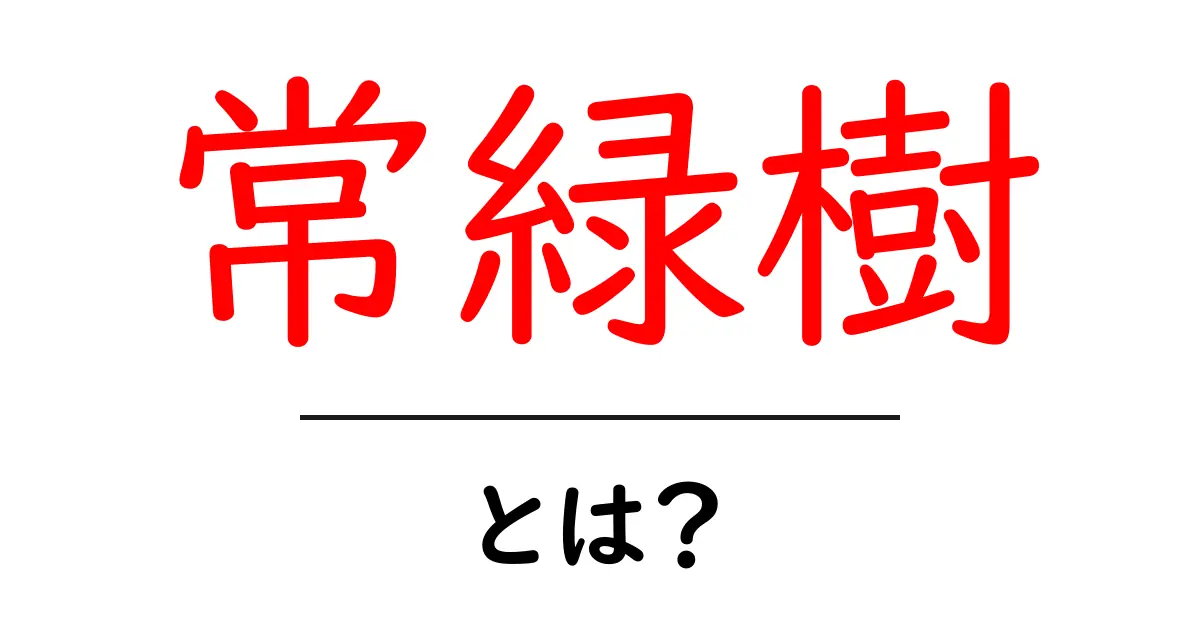
落葉樹:秋に葉を落とす樹木のこと。常緑樹と対比されることが多い。
樹木:幹がある植物で、一般的に高さが1メートル以上のものを指します。常緑樹もその一種です。
緑化:植物を植えて環境を緑で満たすこと。常緑樹は四季を通じて緑を保つため、緑化に効果的です。
葉:植物の光合成を行う部分。常緑樹の葉は通常、季節を問わず緑色を保ちます。
生態系:生物とその環境との関係を示す用語。常緑樹は多くの生態系において重要な役割を果たします。
木材:樹木から得られる材料。常緑樹の木材は、建材などに広く利用されます。
植栽:植物を意図的に植えること。常緑樹は庭園や公園でよく使われます。
耐寒性:寒さに耐える能力。常緑樹の中には、特に寒冷地に適応した種も存在します。
生長:植物が成長する過程。常緑樹は年中成長し、一定の大きさを維持します。
風景:自然環境の見た目。常緑樹は四季を通じて安定した景観を提供します。
常緑植物:一年を通して葉を失わず、緑色の葉を保つ植物のこと。常緑樹はその一部として、特に木本植物を指します。
常緑樹木:常緑の特性を持つ木本植物のこと。一般的には針葉樹(マツやスギなど)が多いですが、一部の広葉樹も常緑です。
耐寒性樹木:寒い地域でも生育できる樹木で、多くの常緑樹がこの特性を持っています。寒冷地でも緑を提供します。
針葉樹:葉が針状または鱗状で、ほとんどが常緑の樹木を指します。例としては、スギやマツなどがあります。
不落葉樹:秋冬に葉を落とさないことから、常緑樹と同義に用いられることがある言葉です。
常緑樹:葉が常に緑色を保つ樹木のこと。季節に関係なく葉が落ちず、四季を通じて生育する特徴がある。
落葉樹:季節に応じて葉を落とす樹木のこと。一般的には秋に葉が色づき、冬には葉を落とす。常緑樹と対照的な存在。
樹木:幹や枝を持ち、成長し続ける植物の中で、特に木質の部分が発達したもの。常緑樹や落葉樹などが含まれる。
植物:光合成によって自ら栄養を作り出す生物の総称。草花、樹木、藻類などが含まれる。
光合成:植物が太陽の光を利用して二酸化炭素と水から栄養を作り出す過程のこと。これによって酸素も生成される。
生態系:特定の環境内で動植物が相互に関わり合いながら存在する仕組みや関係のこと。常緑樹はこれに重要な役割を果たす。
針葉樹:常緑樹の一種で、細長い針のような葉を持つ樹木のこと。これらは一般的に寒冷地に適応している。
広葉樹:広い葉を持つ常緑樹または落葉樹のこと。主に温暖な地域に多く見られる。
庭木:庭の装飾や目隠しとして植えられる樹木のこと。常緑樹が選ばれることが多い。
景観:自然や人工物が作り出す視覚的な状況のこと。常緑樹は美しい景観の一部として重要な役割を果たす。
常緑樹の対義語・反対語
常緑樹(ジョウリョクジュ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
常緑樹(ジョウリョクジュ)とは? 意味や使い方 - コトバンク