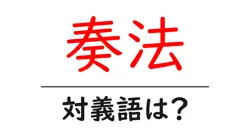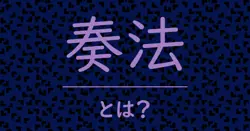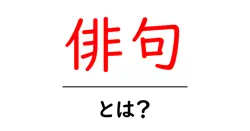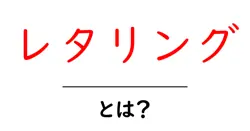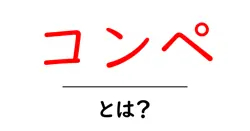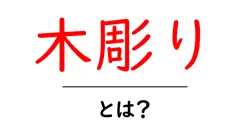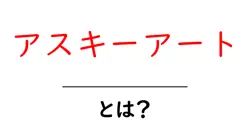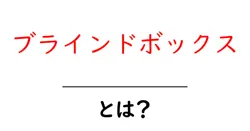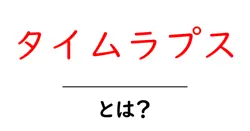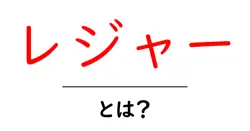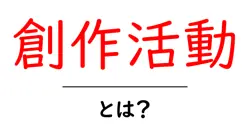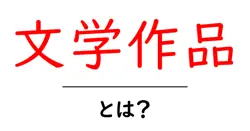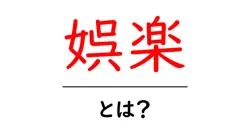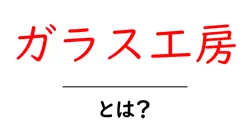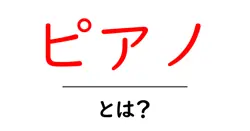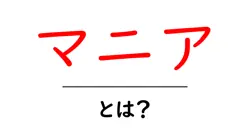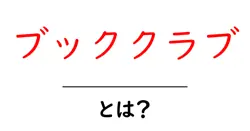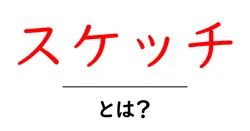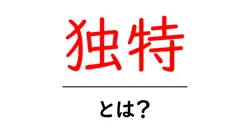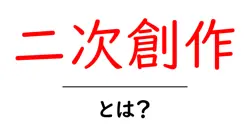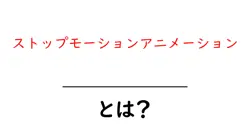奏法とは?音楽の表現力を高める方法とその重要性
音楽にはさまざまな要素があり、その中で「奏法」は非常に重要です。では、奏法とは何なのでしょうか?簡単に言うと、奏法は楽器や声を使って音楽を演奏する際の技術や方法を指します。この奏法によって、音楽の表現力が大きく変わるのです。
奏法の種類
奏法は楽器によって異なりますし、さらにはその楽器の演奏者によっても違いがあります。以下は代表的な奏法の種類です:
| 楽器 | 奏法の例 |
|---|---|
| ピアノ | 指の使い方やダイナミクス(強弱)の付け方 |
| ギター | ストロークやフィンガーピッキング |
| バイオリン | 弓の動かし方や指の位置 |
このように、奏法は楽器ごとに多様で、演奏者の個性を表現するための大切な手段となります。
奏法の重要性
演奏者が奏法を理解し、それを使いこなすことができれば、より豊かな音楽表現が可能になります。たとえば、ピアノであれば、強く打鍵することで力強い音を出したり、優しく弾くことで柔らかな雰囲気を作り出したりできます。このように、奏法を使い分けることで、曲の解釈が深まります。
奏法を学ぶ方法
奏法をしっかりと学ぶためには、以下のような方法があります:
- 専門の先生に習う
- オンラインレッスンを受ける
- 教材や教則本を使う
特に、個別指導を受けることで、自分の奏法を見直し、より改善することができます。また、仲間と一緒に演奏することで、新しい技術を学ぶ機会も増えます。
まとめ
奏法は音楽において非常に重要な要素です。楽器ごとに異なる技術や方法を学ぶことで、音楽の表現力が高まります。ぜひ、様々な奏法に挑戦してみてください。
バロック 奏法 とは:バロック奏法(ばろっくそうほう)とは、17世紀から18世紀にかけて主にヨーロッパで発展した音楽の演奏スタイルです。バロック時代には、鍵盤楽器や弦楽器などの楽器が多く使われました。バロック奏法の特徴は、装飾音や即興演奏が多く、演奏者が自分の解釈を加える自由さがあることです。例えば、楽曲の中で旋律を美しく飾り立てることで、聴く人に感動を与えます。また、バロック音楽は感情表現が豊かで、喜びや悲しみを感じさせるように作られています。バロック奏法は、ただ楽譜を読むだけでなく、演奏者が自分の思いを表現することが非常に重視されるため、演奏者の個性が大きく反映されます。バロック時代の有名な作曲家としては、バッハやヘンデルなどが挙げられます。彼らの作品を通して、バロック奏法の素晴らしさを感じることができるでしょう。バロック音楽に触れることで、音楽の奥深さや楽しさを感じられるので、ぜひいろいろな曲を聴いてみてください。
音楽 奏法 とは:音楽奏法とは、楽器を使って音楽を演奏する方法や技術のことを指します。例えば、ギターを弾くとき、指をどうやって動かすか、どの弦を鳴らすかなどが奏法に関係しています。音楽はただ聴くだけではなく、自分で演奏する楽しさもあります。奏法を理解すれば、演奏がもっと楽しくなります。音楽の奏法には、指使いやリズムの取り方、音の出し方など、いろいろなポイントがあります。これらを学びながら、少しずつ上達していくのが大切です。まずは好きな曲を選び、基本の奏法から始めると良いでしょう。練習を重ねることで、だんだんと上手になり、演奏するのが楽しみになってきます。そして、自分の演奏を友達や家族に聴いてもらうことで、さらに自信がつくでしょう。音楽奏法を学ぶことは、自分の表現力を高めることにもつながります。楽器を使って心の中の思いを音にする、そんな素晴らしい体験をぜひしてみてください!
技術:奏法を実践するために必要な技術やスキルのこと。演奏者が楽器を扱うための知識や訓練を含みます。
リズム:奏法による演奏では、リズムを正確に守ることが重要です。音楽のテンポや拍子を意味します。
音色:奏法によって生成される音の質や色合いのこと。異なる奏法によって異なる音色が生まれます。
表現:奏法を通じて音楽の感情やストーリーを伝えることを指します。演奏者の個性や感受性が反映されます。
テクニック:奏法における具体的な操作や動作のこと。特定の技法や手法を駆使することで、演奏の質を向上させます。
アーティキュレーション:音をどう発音するかという奏法の一部。ノートの始まりや終わりをどのように表現するかを指します。
ダイナミクス:音の強弱を表す奏法の要素。演奏にメリハリをつけるために重要です。
楽器:奏法が適用される具体的な楽器のこと。楽器によって奏法は異なるため、使用する楽器に特化した技術が必要です。
フレージング:音楽のフレーズをどのように演奏するかを決める奏法のことで、メロディーやリズムをどのように解釈するかに関わります。
練習:奏法を習得するために繰り返し行う訓練のこと。効果的な練習方法が奏法のマスターに寄与します。
技法:特定の技術や能力を使って表現や創作を行う方法を指します。音楽に限らず、絵画や文章など、様々な分野で使われる言葉です。
プレイスタイル:演奏する際の個々の特徴や方法を指します。奏法はこのプレイスタイルに深く関わっており、演奏者の個性や技術によって異なります。
演奏技術:楽器を使った演奏を行うために必要なスキルや手法を含みます。具体的には、指の使い方やリズムの取り方など、演奏に関する技術的な側面を強調した言葉です。
奏で方:音楽や楽器を演奏する際の特定のやり方や手法を指します。奏法と近い意味を持ちますが、より日常的な表現です。
演奏法:特定の楽器や曲に対する演奏の方法を指します。奏法とほぼ同義ですが、より一般的な文脈で使われることが多いです。
手法:特定の目的を達成するために採用する具体的な方法や技術を指します。音楽においては、楽器の扱いや表現方法に関連づけられます。
演奏法:楽器や声を使って音楽を演奏する方法のこと。奏法は演奏法の一部として位置付けられ、特定の楽器や楽曲に応じた技術やスタイルを含みます。
奏者:楽器や声で音楽を演奏する人のこと。奏法においては、その奏者の技術やスタイルが重要となります。
技術:演奏に必要な技能や方法。良い奏法を身に付けるためには、練習と技術の向上が欠かせません。
音色:楽器や声が生み出す音の質感や特徴のこと。奏法によって音色が変わるため、演奏の印象に大きく影響します。
フレージング:音楽の中のフレーズやメロディーをどのように表現するかの技術。奏法の一部として重要な要素です。
ダイナミクス:音の強さや大きさの変化を指します。奏法においてダイナミクスの扱い方も重要で、感情を表現する手段となります。
テクニック:具体的な演奏技術や手法のこと。奏法には様々なテクニックがあり、習得することで演奏の幅が広がります。
スタイル:特定のジャンルや文化に基づく演奏の特徴。奏法は演奏スタイルによっても異なるため、学ぶ際にはそれぞれの特徴を理解することが重要です。
表現力:演奏において感情や意図を伝える力。奏法を磨くことで、表現力も高めることができます。
アーティキュレーション:音を区切る方法や、音にさまざまなニュアンスを持たせる技術。奏法によりアーティキュレーションが変わります。
スケール:音階のこと。特定の奏法を学ぶ際には、スケールの練習が欠かせません。これにより基本的な音の理解が深まります。