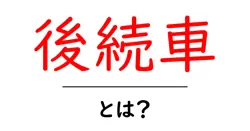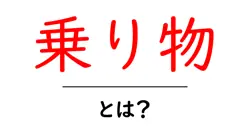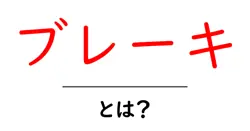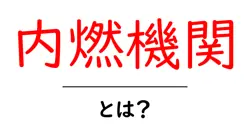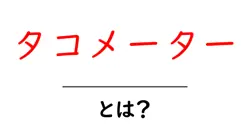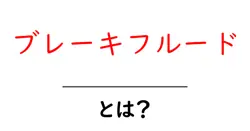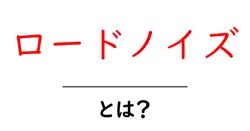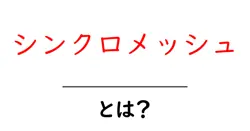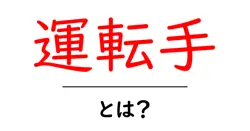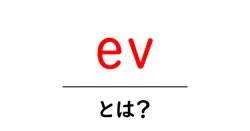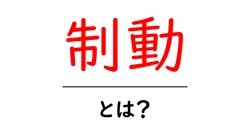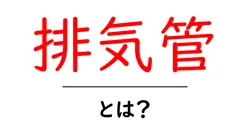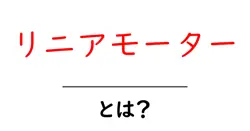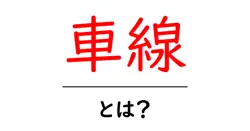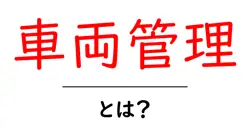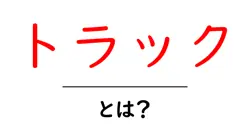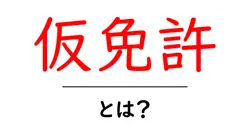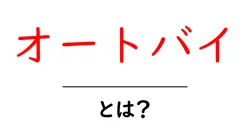船首とは?
船首(せんしゅ)とは、船の最前部のことを指します。船にとって非常に重要な部分であり、さまざまな面で役割を果たしています。この記事では、船首の役割や重要性、さらには種類について詳しく説明します。
船首の役割
船首は、船が進む方向を決定するための重要な役割を果たしています。そのため、船首の形状は、航行の安定性や加速性、さらには抵抗を減らす役割も持っています。
船首の種類
船首にはさまざまな形状がありますが、大きく分けると次のような種類があります。
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| クリン(V型) | 鋭い形状をしており、波を切るように進みます。 |
| 平行船首 | 前方が直線的で、広い甲板を持つ船に適しています。 |
| ラウンド(丸型) | 丸みを帯びた形状で、荷物を積むのに適しています。 |
船首の魅力
船首の魅力は、そのデザインだけでなく、船が海を進む姿にも現れています。特にクルーズ船や戦艦などの大型船では、船首の形が船全体の印象を大きく左右します。
また、船首には「艦橋」と呼ばれる操縦室が設けられていることも多く、船の運航における重要な拠点でもあります。ここから船を操ることで、海の上を自由に航行することができるのです。
まとめ
船首は、単に船の前の部分だけでなく、航行の安定性やデザインに大きな影響を与える重要な部分であることがわかりました。今後、船について学んでいく中で、船首の役割や種類を知っていると、より深く理解できるでしょう。
船体:船の主な構造部分で、船首部分が含まれています。船体は水上での浮力を受け持ち、航行を支える重要な役割を果たします。
舵:船を操縦するための装置で、船首の向きを変えるのに使われます。舵を使うことで、船の進行方向を変えることが可能です。
艦首:船の前方部分を指し、船首と同義で使われることがあります。艦首は進行方向に最も近い部分です。
モーターボート:エンジンを搭載したボートで、速い航行が可能です。船首のデザインは航行の安定性に影響を与えます。
ブリッジ:船の操縦室で、船首近くに位置し、船の動きや方向を確認しながら操作します。
艦載:船舶に装備された機器や武器を指します。船首には艦載されている機器が配置されることが多く、戦闘能力に関わります。
航跡:船が水面を進む際に残す跡のことです。船首から後方にかけての航行の証跡となります。
艦首:軍艦や大きな船の前部のことを指します。一般的に船首と同じ意味で使われますが、特に艦船においてはこの用語が多く用いられます。
船頭:船を操る人のことを指しますが、船首という言葉とは異なります。船が進む方向や操船の指示を担当する立場です。
前部:船の前の部分全般を指します。「船首」とほぼ同義ですが、より一般的な表現です。
舳先(しゅせん):船の前端を意味しますが、特に日本の伝統的な船において使用されることが多い言葉です。
先頭:物事の最前面やトップを指しますが、船に関して言えば、進行方向を示す最前部という意味でも使われることがあります。
べリ(ベレー):一部の船舶用語で、特に船首の形状を指す際に使われますが、一般的ではありません。
船尾:船の後部を指します。船首が前を向いているのに対し、船尾はその反対側に位置しています。
舵:船を操縦するための装置で、船首を曲げたり方向を変えたりするのに使われます。舵を左右に動かすことで船の進む方向を調整します。
船体:船の主要部分を指し、船首、船尾、左右の側面を含む構造物です。船体は水中に浮かび、船の安定性を保つ役割もあります。
ブリッジ:船の操縦室のことで、船の運航に関する指示や制御が行われます。ブリッジからは船首を見渡すことができ、航路の確認が可能です。
マスト:帆船の場合、船首および船体に立っている縦に長い棒で、帆を吊るすために使用されます。マストは航行時に風を受けて船を進める役割も担います。
プロペラ:船を推進するための装置で、エンジンの力で回転し、水を後ろに押し出すことで船を前に進めます。プロペラによる推力は船首の進行方向に大きな影響を与えます。
艦船:海軍の船を指し、戦闘や任務に使用されるもので、専用の設計や搭載されている武装を持つことが特徴です。艦船の多くは、船首の形状が特に重要です。
バウ:船首のことを指し、特に中型以上の船舶では、前部のデザインが重要視されます。バウの形状は船の航行性能に大きな影響を与えます。
航行:船が決まったルートに沿って移動することを指します。航行中、船首の向きや風の強さ、潮の流れなどが重要な要素となります。
ドック:船を修理や保管するための設備です。ドックは船首を含む全体を支え、点検や改修を行う際に使用されます。
船首の対義語・反対語
該当なし