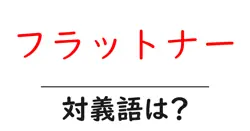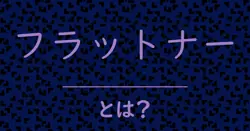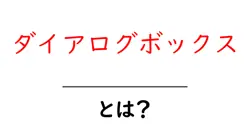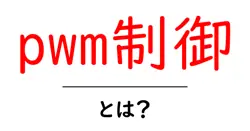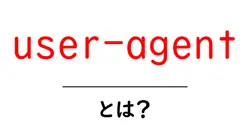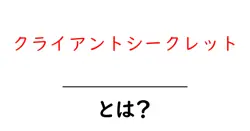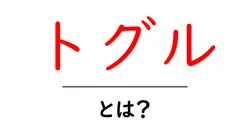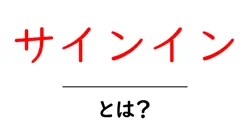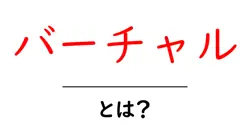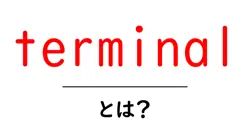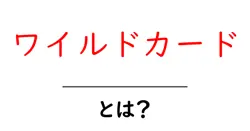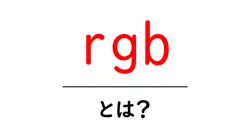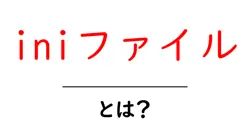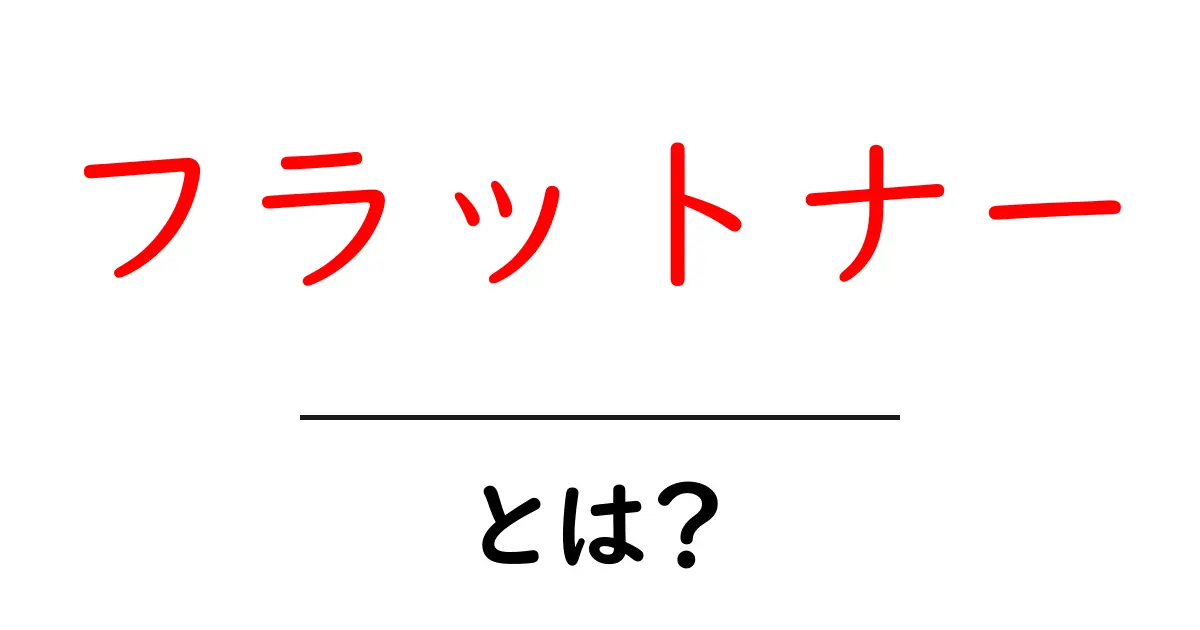
フラットナーとは?
フラットナーという言葉は、様々な分野で使われていますが、特に「インターネット」や「コンピュータ」などの技術関連の文脈でよく耳にします。この言葉を理解するためには、まずその基本的な概念を知ることが重要です。
フラットナーの基本
フラットナーは、「平坦にするもの」とも言えます。たとえば、インターネット上の情報を整理することで、よりアクセスしやすい状態にするツールや技術を指します。この言葉は、特にデジタルデータの整理や分析に関連しています。
フラットニングの例
フラットニングとは、データを平らにして扱いやすくする手法のことです。例えば、複雑なデータベースの表を一つの平面に集約して、必要な情報をすぐに見つけられるようにすることが挙げられます。
フラットナーの利点
| 利点 | 説明 |
|---|---|
| 情報の整理 | データをシンプルにして見やすくする。 |
| アクセスの向上 | 必要な情報にすぐアクセスできるようになる。 |
| 効率的な分析 | データの分析が簡素化され、迅速に結果を得られる。 |
フラットナーの活用方法
フラットナーは、さまざまな分野で活用されています。ビジネスのデータ管理や、教育機関での情報整理、さらには個人の学習における資料整理にも役立ちます。特に、インターネット上で膨大な情報が行き交う中、フラットな状態で整理された情報は、効率的かつ効果的に使うことができます。
事例紹介
例えば、学生が勉強する際、教科書の内容をフラットナーを使って整理することで、重要なポイントをすぐに見つけられるようになります。また、ビジネスマンが会議のために資料を準備する際も、情報をフラットに整理しておくことで、プレゼンテーションがスムーズに進むでしょう。
まとめ
フラットナーという言葉は、情報を整理し、見やすくするための技術やツールを指します。デジタル時代において、このフラットナーの考え方は、様々な場面で非常に役立つことがわかります。今後もその重要性は増していくことでしょう。
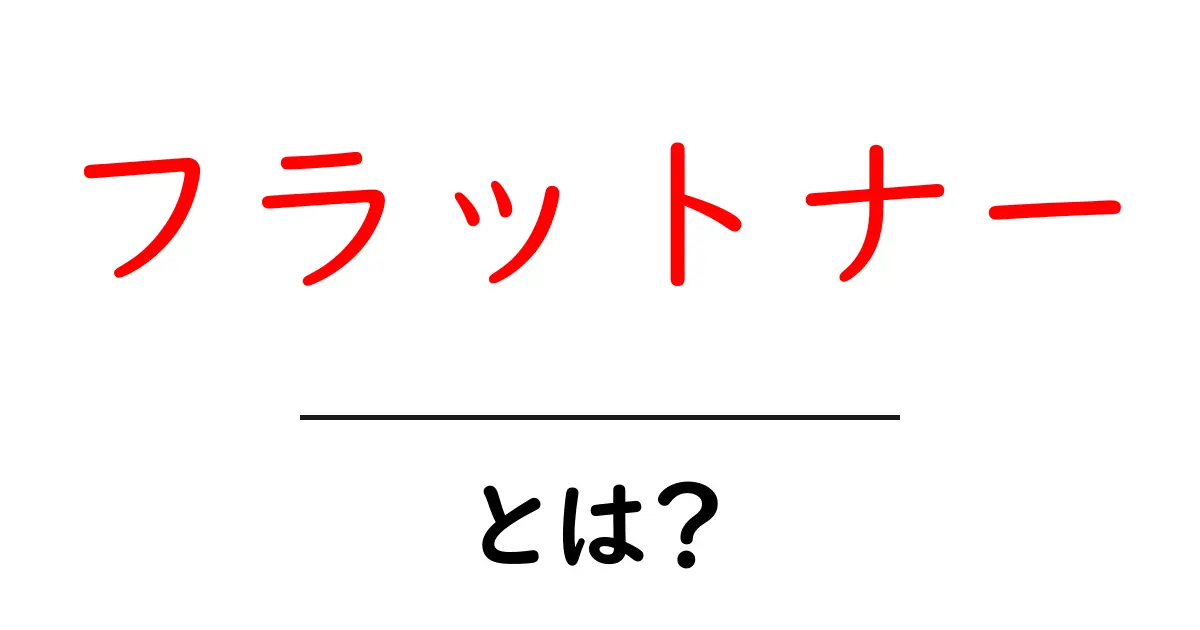
デジタル:情報を電子的な形で処理や伝達する技術や概念。フラットンサーはデジタル技術によって実現されることが多い。
非階層的:組織やシステムが階級やレベルを持たないこと。フラットナーは、従来の階層構造がなく、よりシンプルな関係を築くことを指す。
グローバル化:世界がより一体化し、国境を超えた交流が増えること。フラットナーは、情報技術の進化によって国際的なコミュニケーションが容易になったことを指す。
情報:データや知識のことで、フラットナーでは、さまざまな情報が迅速かつ容易に共有されることが強調される。
競争:市場やビジネスの場において、他者と比較し優位を目指すこと。フラットナーによって新しい競争の形が生まれている。
コラボレーション:共同で作業を進めること。フラットナーは、個人や企業が協力しやすくなる環境を提供する。
アクセス:情報やリソースに対する到達手段。フラットナーは、誰もが情報にアクセスしやすくすることに寄与する。
テクノロジー:技術のこと。フラットナーは、新しいテクノロジーの利用によって変化するビジネス環境や生活スタイルを示す。
イノベーション:新しいアイデアや製品を生み出すこと。フラットナーは、イノベーションを促進する役割を果たす。
心理的安全性:人が自由に意見を言ったり思い切った行動ができる環境のこと。フラットナーは、このような環境を作る要素ともなる。
フラットデザイン:従来の立体的なデザインに対して、シンプルで平面的なデザインスタイルを指します。主に、アイコン化された形状や、明快な色使いが特徴です。
ミニマリズム:必要最小限の要素で構成されたデザインスタイルで、シンプルさを追求します。余分な装飾がなく、ユーザーに使いやすさを提供します。
シンプルデザイン:デザインにおいて、複雑さを排したシンプルなスタイルを指します。視覚的に分かりやすく、使用することにストレスを感じにくい特徴があります。
フラットUI:ユーザーインターフェース(UI)デザインの一種で、立体感を持たせずに平面的な要素で構成されています。ユーザーが直感的に操作できるようにデザインされています。
クリーンデザイン:無駄な要素を省いた、すっきりとした印象のあるデザインです。視覚情報が整理されており、ユーザーが情報を容易に探しやすい形になっています。
フラットデザイン:フラットデザインとは、装飾的な要素を排除し、シンプルで平面的なデザインスタイルのことを指します。これにより、ユーザーが直感的に操作できるインターフェースが実現されます。
ユーザーエクスペリエンス (UX):ユーザーエクスペリエンスは、製品やサービスを通じてユーザーが感じる体験全体を指します。フラットナーはUXを向上させるためのデザイン手法として活用されることがあります。
レスポンシブデザイン:レスポンシブデザインは、異なるデバイスや画面サイズに応じてレイアウトを調整するデザイン手法です。フラットナーはこの手法と組み合わせて使用されることが多いです。
インターフェース:インターフェースとは、ユーザーとシステムが相互作用するための接点や手段のことを指します。フラットナーを使ったインターフェースは、視覚的に分かりやすく、使いやすいことが求められます。
アイコン:アイコンは、アプリケーションやウェブサイト内で特定の機能や情報を示すための小さな画像やシンボルのことです。フラットデザインでは、シンプルで直感的なアイコンが多く使われます。
カラーコントラスト:カラーコントラストは、異なる色の明るさや彩度の違いを示すもので、読みやすさや視覚的な魅力に大きな影響を与えます。フラットナーでは、高いコントラストを用いることで、要素を強調することができます。
ナビゲーション:ナビゲーションは、ユーザーがウェブサイトやアプリ内を移動する手段を指します。フラットナーを活用した分かりやすいナビゲーションは、ユーザーにとって非常に重要です。