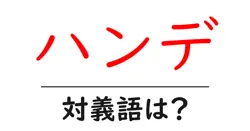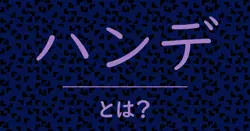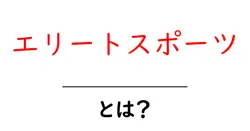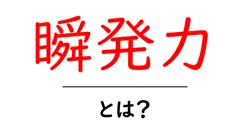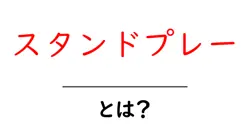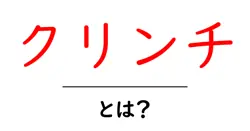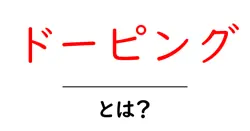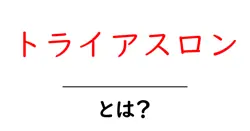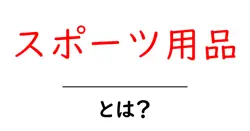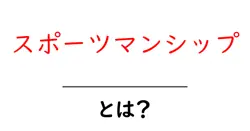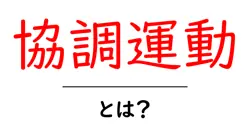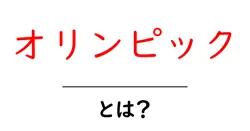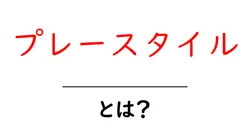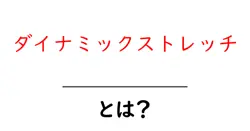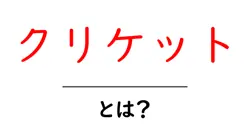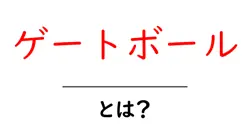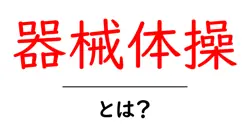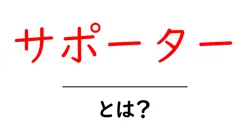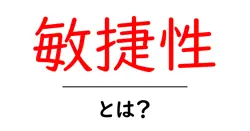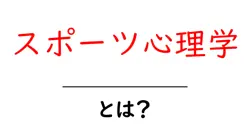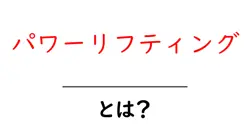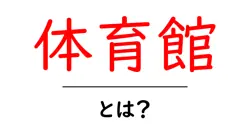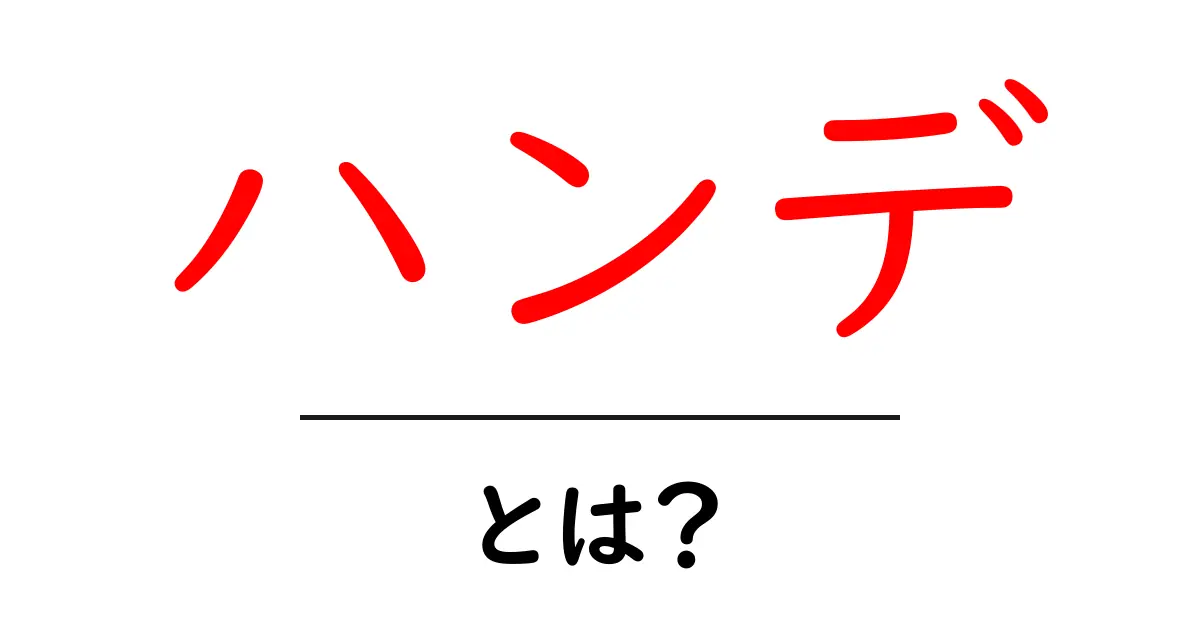
ハンデとは?
「ハンデ」とは、主にスポーツやゲームの世界で使われる用語で、参加者の力量の違いを補うために与えられる不利な条件のことを指します。この「ハンデ」を設定することで、全体の競技の公平性が保たれ、参加者が試合やゲームを楽しむことができるのです。
ハンデの具体例
例えば、ゴルフにおいては「ハンディキャップ」というシステムが存在します。これは、各プレーヤーの技術や実力に応じて与えられる点数のことで、これによって初心者と上級者が同じ土俵で戦えるようになります。また、将棋やチェスにおいても、実力差を埋めるためにハンデを与えることがあります。
ハンデの種類
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| ポイントハンデ | 特定の点数を差し引くことによって、実力差を調整する方式。 |
| 体力ハンデ | 体力やスピードに基づいて与えられる不利な条件。 |
| 技術ハンデ | 特定の技術を制限することによって調整する方式。 |
ハンデが必要な理由
ハンデは、特に異なる能力を持つ参加者がいる場合に非常に重要です。もしハンデを設定しないと、実力が圧倒的に上のプレーヤーがすぐに勝利してしまい、初心者や中級者が楽しむ機会を失ってしまうことがあります。そこで、ハンデを設けることにより、より多くの人が楽しめる環境を作るのです。
まとめ
このように「ハンデ」とは、競技や活動において公平性を保するために必要な要素です。特にスポーツやゲームにおいては、皆が同じ条件で楽しむために欠かせない仕組みとなっています。競技をする際は、どのようなハンデが与えられるのかを理解することが、より楽しむためのポイントになります。
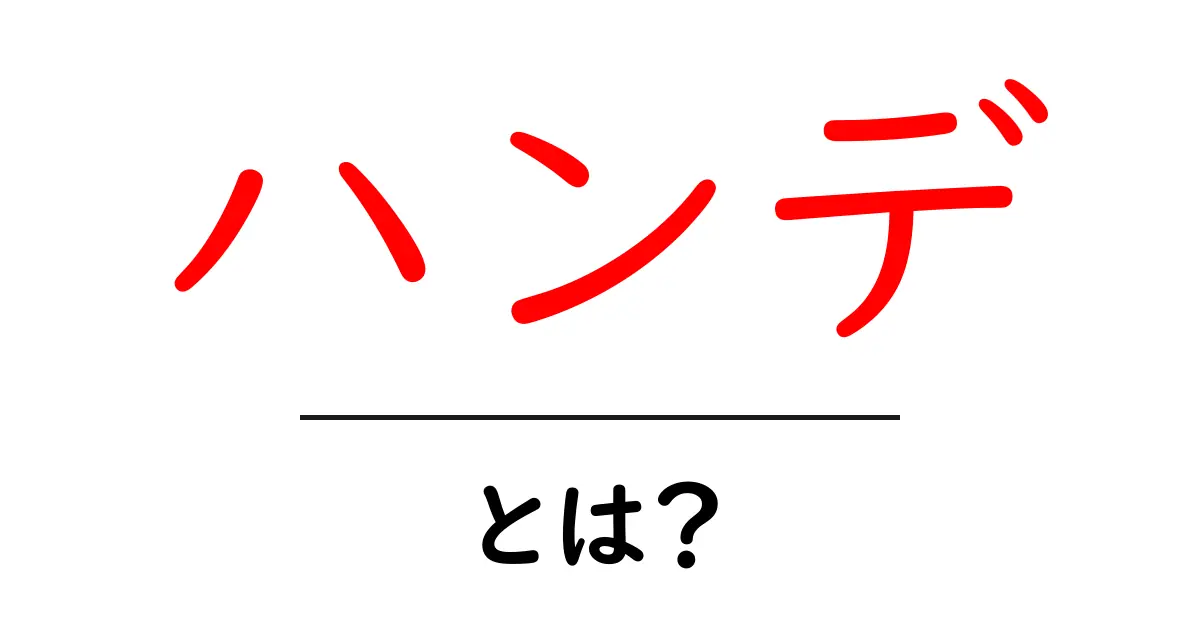
オートレース ハンデ とは:オートレースハンデとは、オートレースのレースにおいて参加車両の実力を均等にするための仕組みのことです。オートレースでは、運転するバイクやそのドライバーの能力が異なるため、全ての選手が同じ条件で競うと、一部の強い選手だけが勝つことになってしまいます。それを避けるために、「ハンデ」と呼ばれる制度が導入されています。 ハンデとは、指定された時間を遅らせてスタートするというものです。例えば、実力が劣る選手は1周遅れでスタートし、強い選手は早くスタートするという形です。この制度により、実力差を減らし、より公平なレースを楽しむことができるのです。 このハンデ制度は、観客にとってもワクワクする要素を増やします。どの選手がハンデを克服して先にゴールに達するのか、緊張感を持ってレースを観戦できるのです。また、ハンデは毎回変わるため、レースごとに異なる戦略を楽しむこともできます。オートレースハンデについて理解することで、より一層レースを楽しめるでしょう。
ゴルフ ハンデ とは:ゴルフのハンデとは、プレーヤーの実力を数値にしたものです。主にゴルフの競技で、多くの人が平等に楽しめるようにするために使います。ゴルフは、上手な人がたくさん打っても、あまり上手くない人と対戦すると不公平になることがあります。そこで、ハンデが必要になります。一般的に、ハンデはコースの難しさも考慮して決まります。たとえば、あるプレーヤーのハンデが18だとしましょう。この場合、そのプレーヤーはラウンド中に18打多くボールを打つことが許されます。つまり、スコアが18打少ない上手な選手と対戦した場合、その人に18打の優遇が与えられます。このように、ハンデを使うことで、みんなが同じスタート地点に立てるため、楽しく対戦できます。ゴルフを始めたばかりの人でも、ハンデを使うことで、より経験豊富なプレーヤーと対戦するチャンスが増えます。これにより、技術を磨く良い機会にもなります。したがって、ゴルフのハンデを理解することは、競技を楽しむためにはとても大切です。
ハンデ とは 意味:「ハンデ」という言葉は、特にスポーツやゲームの場面でよく使われる言葉です。ハンデは「ハンディキャップ」の略で、特定の人に対して与えられる不利な条件や、逆に優位になれる条件のことを指します。例えば、スポーツでいつも勝っている選手が、次の試合で他の選手よりも難しいルールを適用されると、その選手にとってはハンデを与えられたことになります。このように、ハンデは競争の公平性を保つために存在するものであり、実力差を埋めるための手段でもあります。また、ハンデは単にスポーツだけでなく、ビジネスや学校の試験、日常生活の中でも使われることがある言葉です。相手に与える不利な条件のことを考えながら、ハンデをうまく利用することで、相手との競争を楽しむことができるのです。ハンデを理解することで、競技やゲームをより深く楽しむことができるでしょう。
ハンデ エブリワン とは:「ハンデ エブリワン」という言葉を耳にしたことがありますか?これは、特にゲームやスポーツ、さらにはビジネスなどの場面で使われる概念です。ハンデは「ハンデキャップ」の略で、参加者に公平に競争できるように設けられた条件のことを指します。つまり、実力や能力が異なる参加者が同じスタートラインで競べるようにするための手段です。例えば、ゴルフでは、プレーヤーの実力に応じてスタートの位置を変えることがあります。これにより、初心者でも経験者と対等に楽しめるのです。ハンデ エブリワンは、このように誰もが参加しやすくも、競争も楽しめる環境を作るための考え方を表しています。この考え方は、実はゲームの世界だけでなく、私たちの日常生活や仕事にも当てはまります。それぞれの人が持つ特技や経験を生かして、全員が活躍できるようにすることが重要です。ハンデ エブリワンを通じて、みんなが楽しく成長し合う環境を作ることが、社会においても求められているのです。
競馬 ハンデ とは:競馬において「ハンデ」とは、レースに出る馬の能力を平等にするための仕組みです。簡単に言うと、強い馬と弱い馬が同じ条件で勝負できるように、重りを加えたり(ハンデ)減らしたりすることです。一般的には、強い馬には重りが課せられ、逆に弱い馬には軽い負荷がかけられます。このようにすることで、どの馬にも勝つチャンスが生まれ、レースがより面白くなるのです。競馬では、ハンデキャップ競走と呼ばれる特別なレースもあり、ここでは特にこのハンデの仕組みが重要です。競馬を楽しむ際には、なぜある馬にハンデがあるのか、どのような理由でその馬が強いとされているのかを考えることが、とても楽しみの一部になります。こうした知識を持つことで、レースを見るときの理解が深まりますし、より楽しめることでしょう。
食んで とは:「食んで」とは、古い日本語で使われていた言い方で、主に「食べる」という意味を持っています。この言葉は今ではあまり使われなくなっていますが、昔の文書や詩の中では見かけることがあります。例えば、昔の物語や歌詞の中では「食んでいる」というような表現が使われていたりします。言葉の変化は私たちの生活の一部であり、古い言葉がどう使われていたのかを知ることは、とても面白いことです。また、「食んで」という言葉が使われていた時代は、人々が食べ物を得ることや、それを食べることに非常に重要な意味がありました。そのため、この言葉を通じて、当時の人々の生活や文化を知ることができます。今では一般的に「食べる」と言いますが、こうした古い表現を理解することは、言葉の歴史を学ぶ上でとても役立ちます。現代においては、インターネットや本などでこのような言葉に触れる機会も増えているため、興味を持った際にはぜひ調べてみてください。言葉にはその背景にある文化や歴史が詰まっているからです。
不利:ハンデは、ある人や物事が持つ不利な条件や要因のことを指します。
条件:ハンデは特定の条件や状況をもとに付けられるもので、例えばスポーツやゲームでの特別な扱いなどです。
競技:ハンデは競技や試合において不平等を調整するために使われることが多い用語です。
平等:ハンデは、参加者同士の平等を図るために設けられる要素とも言えます。
スポーツ:体育的な競技においてハンデは、選手の技術や能力の差を補うために導入されます。
ルール:ハンデは通常、特定のルールに従って設定され、競技者のバランスを保つ役割があります。
補助:ハンデは選手やプレイヤーへの補助的要素としても機能し、魅力的な競技環境を作り出します。
バランス:ハンデを設けることで、競争のバランスが取れ、試合がより面白くなります。
ギャンブル:ハンデが用いられる場合、ギャンブルの場面でも、出場者間の実力差を調整するために使用されることがあります。
評価:ハンデは選手の実力や能力を評価する基準の一部として用いられることもあります。
障害:特定の状況や条件で、不利益や不都合をもたらす要因を指します。例えば、身体的な障害や環境的な障害が考えられます。
不利:競争や対比の中で、他と比べて劣っている状態を示します。このため、特定の場面でうまくいかないことが多いです。
制約:行動や選択において何らかの制限がかかることを指します。これは、その人が持つ能力や環境によって異なります。
負担:特定の状況や条件において、個人やグループが背負わなければならない重荷やプレッシャーを意味します。
劣位:他のものと比べて、立場や条件が不利であることを示します。特に競争や比較の文脈で使われます。
ハンディキャップ:特定の状況や環境において、他の人と比べて不利な条件や障害を指します。主にスポーツや日常生活において、能力や条件の違いを補正するためのルールや配慮がなされることがあります。
デメリット:ある行動や選択に伴う不利益や欠点を示します。たとえば、競技スポーツにおいて、ハンデがあることで平等に競い合うことが難しくなる場合があります。
アドバンテージ:有利な点や条件を意味します。ハンデが設けられる目的は、アドバンテージを持つ者と持たない者の間で公平な競争を促進するためです。
公平性:すべての個人やグループが平等に扱われる状態を指します。ハンデは公平性を維持するために用いられることがあります。
バリアフリー:身体的な障害を持つ人々が社会に参加しやすくするための環境整備を指します。ハンデと関係深く、人々が平等に生活するための工夫の一つです。
スポーツ精神:競技に臨む姿勢や意義を重視し、互いにリスペクトし合う気持ちを指します。ハンデは時としてスポーツ精神を育むための要素になることもあります。
インクルージョン:全ての人々を排除せず、受け入れる社会を作ることを指します。ハンデは、インクルージョンを促進する手段として機能します。
競争:目的を持った活動において、他者と比べて能力や資源を使い、優劣を測ることを指します。ハンデは競争をより公平にするための要素です。