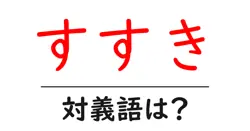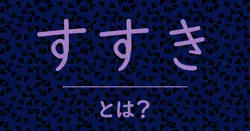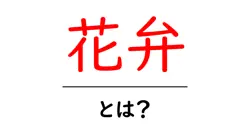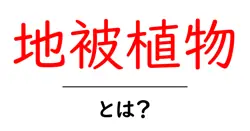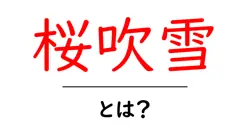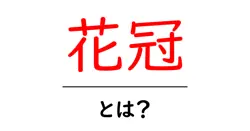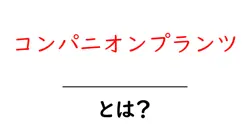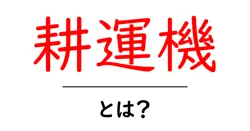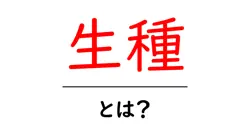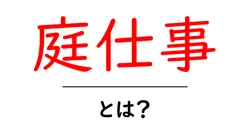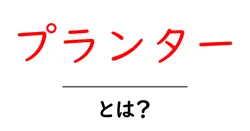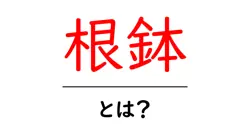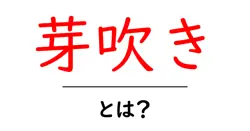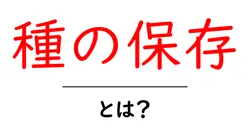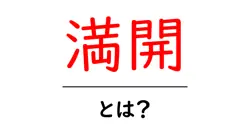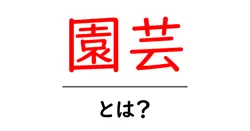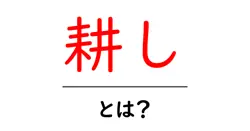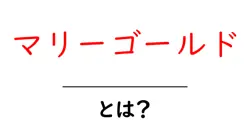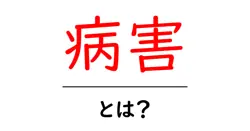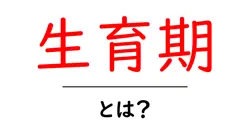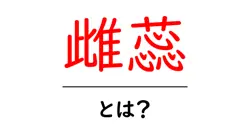すすきとは?
すきは、日本で非常に一般的に見られる草です。秋になると、黄金色に色づき、その優雅な姿が多くの人に親しまれています。すすきは、特に日本の風景や文化に深く根ざしており、観賞用としても人気があります。
すすきの特徴
すすきは、細長い葉と、穂のような形をした花が特徴です。高さは1メートルから2メートルほどに成長します。すきの穂は、風に揺れる様子が美しく、特に夕暮れ時の光景は幻想的です。
すすきの生育場所
じすきは、日本全土で見られますが、特に水辺や道端、空き地など、日当たりの良い場所を好みます。土壌の条件はあまり厳しくなく、砂質の土壌でも育つことができるため、非常に適応力が強い植物です。
すすきの利用方法
すすきは、お正月や秋の行事に使われることがあります。また、観賞用として庭に植えられたり、花束にされることもあります。
すすきにまつわる文化
日本の伝統的な歌や詩にも、すすきはしばしば登場します。特に「すすき、秋の風に揺れる」というフレーズは、多くの人に親しまれています。すすきは、秋の訪れを象徴する存在として、季節感を感じさせてくれます。
すすきの生態系への影響
すすきは、土壌を安定させる役割や、多くの小動物や昆虫にとっての住処となるため、生態系の一部としても重要です。特に、すすきの茂みには昆虫が集まり、その生態系を支えています。
まとめ
すすきは、日本の秋を代表する草であり、観賞用としての魅力も多く、文化的な価値も高い植物です。その独特な美しさは、私たちの心に深く残ります。ぜひ、秋の季節にはすすきを見に出かけ、自然の美しさを楽しんでみましょう。
秋の七草 ススキ とは:秋の七草は、古くから日本で親しまれている植物たちです。その中でもススキは特に親しみがあります。ススキは、田んぼや河原、さらには野原などに生えている草で、穂が風に揺れて美しい姿を見せます。日本では、ススキは秋の季節の到来を知らせる植物とされ、特に中秋の名月の時期に合う花です。これは、ススキが月を美しく際立たせるからです。ススキの穂は、まるで銀色に輝くようで、夜になると月明かりとともに幻想的な光景になります。さらには、ススキは葉っぱや茎が丈夫で、昔は屋根を作る材料として使われたこともあります。また、ススキは日本の歌や詩にもよく登場し、昔の人々の生活に深く根ざしていました。こうした背景から、ススキはただの草ではなく、日本文化の中でとても特別な存在なのです。秋になると、ススキを見つけながら、その美しさや歴史を感じてみてはいかがでしょうか。自然の中に身を置き、秋の風を感じる時間は、とても心を豊かにしてくれます。ススキを通じて、日本の象徴を知ることができる素晴らしい機会になるでしょう。
芒 とは:「芒」とは、植物の一部で、特にイネ科の植物に見られる細長い突起のことを指します。たとえば、稲や麦などの穂についている部分が「芒」と呼ばれています。この突起は、種子の散布を助ける役割を持っています。つまり、風に乗って遠くに飛んでいくことで、新しい場所に芽を出すことができるのです。\n\nまた、芒は見た目にもおしゃれで、穂が風に揺れる姿はとても美しいです。このため、芒がある植物は、日本の田園風景にも多く見られ、自然の風景を彩る存在となっています。\n\n芒は、植物にとって重要な役割を果たしていますが、人々にとっても親しみやすい存在です。このように、芒を通じて自然の仕組みや美しさについて知ることができます。みんなも「芒」を見る機会があったら、その働きについて考えてみてくださいね。自然の中にある不思議を理解することで、より深い感動を得られるかもしれません。自分の生活の中で見つけた「芒」を観察して、自然の素晴らしさを感じてみましょう。
薄 とは:「薄」という言葉は、日本語でいくつかの意味を持っています。まず、形容詞として使われるときは、物の厚さを表すことが多いです。たとえば、紙や布などが「薄い」と言われると、厚さがあまりないことを意味します。このように、薄いものは軽くて持ち運びやすいという利点もあります。 また、「薄」という言葉は比喩的にも使われます。例えば、人間関係や感情の「薄さ」を表すときもあります。友達との関係があまり深くないとき、その関係を「薄い」と表現することがあるでしょう。 さらに、料理の世界でも「薄い」という言葉はよく使われます。例えば、薄く切った野菜や肉は、料理の仕上がりを良くすることがあります。このように、「薄」という言葉はさまざまな場面で使われ、私たちの身近な言葉の一つとなっています。日常生活での「薄」の使い方を知ることで、会話がより豊かになるでしょう。
草原:広い場所に生えている草のこと。すすきは草原などで群生することが多い。
秋:すすきが見ごろを迎える季節。特に秋の風景によく映える。
風:すすきは風に揺れて、その独特な音や動きが楽しめる。特に秋にはそよ風が似合う。
自然:すすきは森や川辺などの自然環境に生息する植物で、自然の一部として重要な役割を果たしている。
風景:すすきが生い茂ることで、秋の風景が美しく演出される。特に夕暮れ時や朝日の中で見ると幻想的。
季節感:すすきは秋の訪れを感じさせる植物で、季節の移り変わりを象徴する存在。
日本:特に日本の風景では、すすきは古くから親しまれ、文化や芸術においても多く取り上げられている。
月見:すすきは月見の際に供えられることが多く、秋の月とともに楽しむ風物詩がある。
野原:すすきは野原や荒地に多く生育し、自然との共生を示す代表的な植物。
植物:すすきはイネ科に属する植物で、特徴的な穂を持っていることから、草本植物として知られている。
ススキ:日本の秋に見られる草本植物で、穂先に細かい花がつき、風に揺れる姿が特徴的です。
薄(うす):ススキの別名で、特に古い日本の文献などで用いられる名称です。
尾花(おばな):ススキの穂の部分を指す言葉で、特に秋の風情を表現する際に使われます。
秋草(あきくさ):秋に見頃を迎える草のことを指し、ススキはその代表的な存在です。
野生の草:ススキが自然に生育する様子を表現した言葉で、他の草と共に自生する地域が多いです。
ススキ:日本やアジアに広く分布している多年生の植物。秋に美しい穂をつけ、風に揺れる姿は日本の風情の象徴として知られています。
秋:ススキが特に美しい季節。草原や山野にススキが見られ、秋の風物詩として人々に親しまれています。
湿原:ススキは湿った土壌を好むため、湿原や河川の近くに生育することが多い植物です。
草野:ススキの生育地として一般的な草原。ススキが密集している場所では、他の植物も一緒に見られることがあります。
面倒臭さ:ススキを育てる際に注意が必要な点。成長が早く、他の植物を圧倒することがあるため、手入れを怠ると繁茂しすぎることがあります。
風情:ススキがもたらす、日本の秋の情緒や景観の美しさを指します。詩や絵画に多く取り上げられるテーマでもあります。
食用:ススキの茎や根は、一部の地域で食材として利用されていることもあります。特に根は栄養価が高いとされます。
文化:ススキは多くの日本の伝統文化や行事に取り入れられていて、たとえばお月見などの行事では、ススキを飾る習慣があります。
茅葺き:ススキは屋根材として昔から利用されてきました。茅葺き屋根は自然な断熱効果があり、温かみのある住まいを提供します。
生態系:ススキが生育する環境には多くの動植物が共存し、豊かな生態系が形成されています。特に昆虫や小動物にとって重要な棲み家となっています。