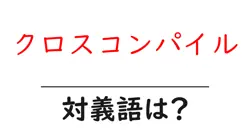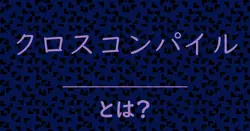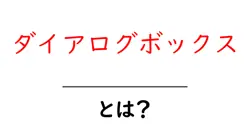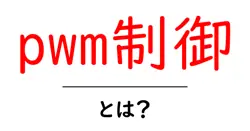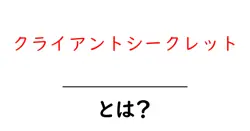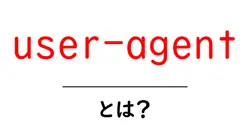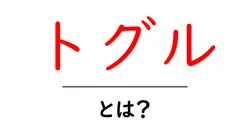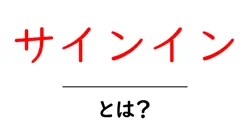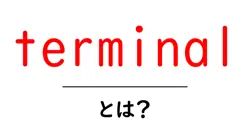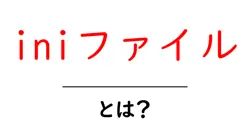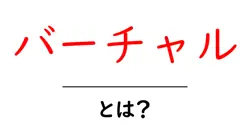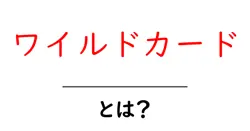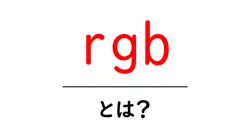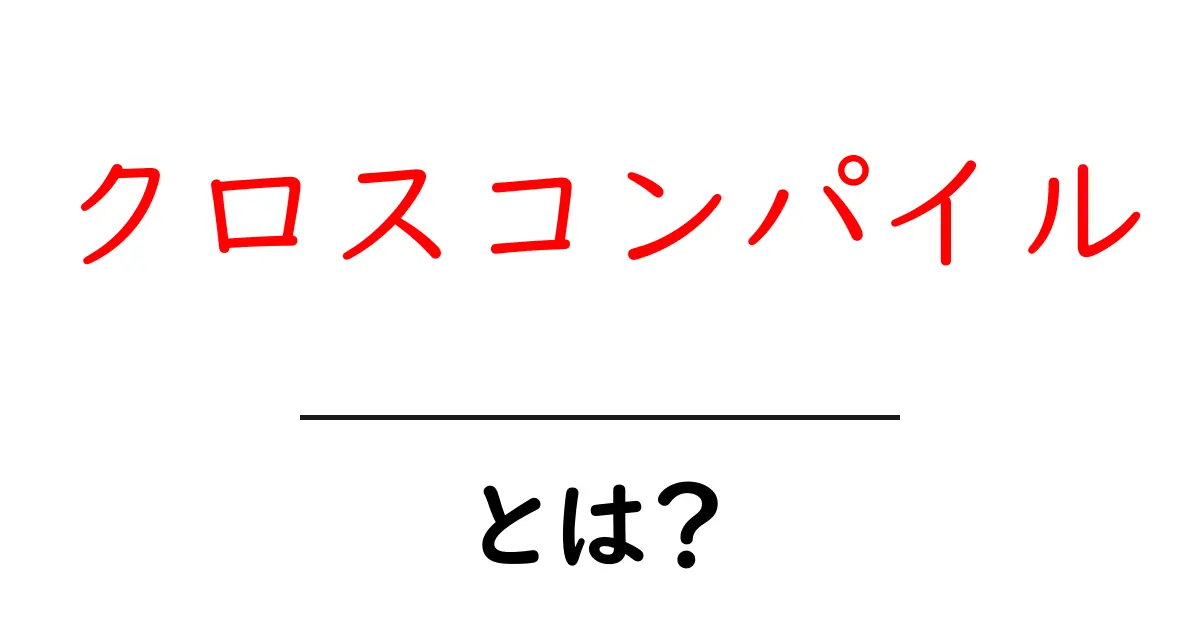
クロスコンパイルとは?初心者でもわかる意味と使い方を解説!
こんにちは!今日は「クロスコンパイル」という言葉についてお話しします。聞いたことがある人もいるかもしれませんが、詳しく知っている人は少ないかもしれません。そこで、クロスコンパイルの意味や、どういった場面で使われるのかをやさしく解説していきます。
クロスコンパイルの基本的な意味
まず、クロスコンパイルとは「あるプラットフォーム用のプログラムを、別のプラットフォームの環境で作成すること」を指します。こう聞くと、ちょっと難しく感じるかもしれませんね。
例えば、Windowsで動くソフトウェアを、Linux(リナックス)で開発するような場合がクロスコンパイルにあたります。開発環境(開発中のパソコンのOS)とは異なる環境で実行できるプログラムを作成するための技術です。
なぜクロスコンパイルが必要なのか?
では、なぜわざわざ別の環境で作る必要があるのでしょうか?それにはいくつかの理由があります。
- 開発の効率化:開発者が使い慣れた環境でプログラムを作成しながら、他の環境でも動かすことができるので、効率的に作業が進められます。
- さまざまなデバイスへの対応:スマートフォンやタブレットなど、今は多くのデバイスが存在します。各デバイスごとに開発環境を整えるのが難しい場合に、クロスコンパイルを使うことで、効率よく対応できます。
どのようにクロスコンパイルを行うのか?
次に、クロスコンパイルを行うにはいくつかのステップがあります。ここでは、簡単にその流れを見ていきましょう。
- コンパイラの選定:まず、どのプラットフォーム向けに作成するかを考え、それに合ったコンパイラを準備します。
- ソースコードの準備:次に、実際にプログラムを書く「ソースコード」を用意します。
- コンパイル:最後に、そのソースコードをコンパイラを使って、目的のプラットフォーム用の実行ファイルに変換します。
クロスコンパイルの例
具体的な例を挙げてみましょう。たとえば、ゲームを作る場合、開発はWindows環境で行い、最終的にゲームはスマートフォン(iOSやAndroid)でも動くようにクロスコンパイルすることがあります。このように、実際の開発の現場でもよく利用されています。
まとめ
クロスコンパイルは、異なるプラットフォームで動作するプログラムを効率的に作成するための大切な技術です。これを理解すれば、ソフトウェア開発の幅が広がると思います!ぜひ、さらに興味を持って学んでみてくださいね。
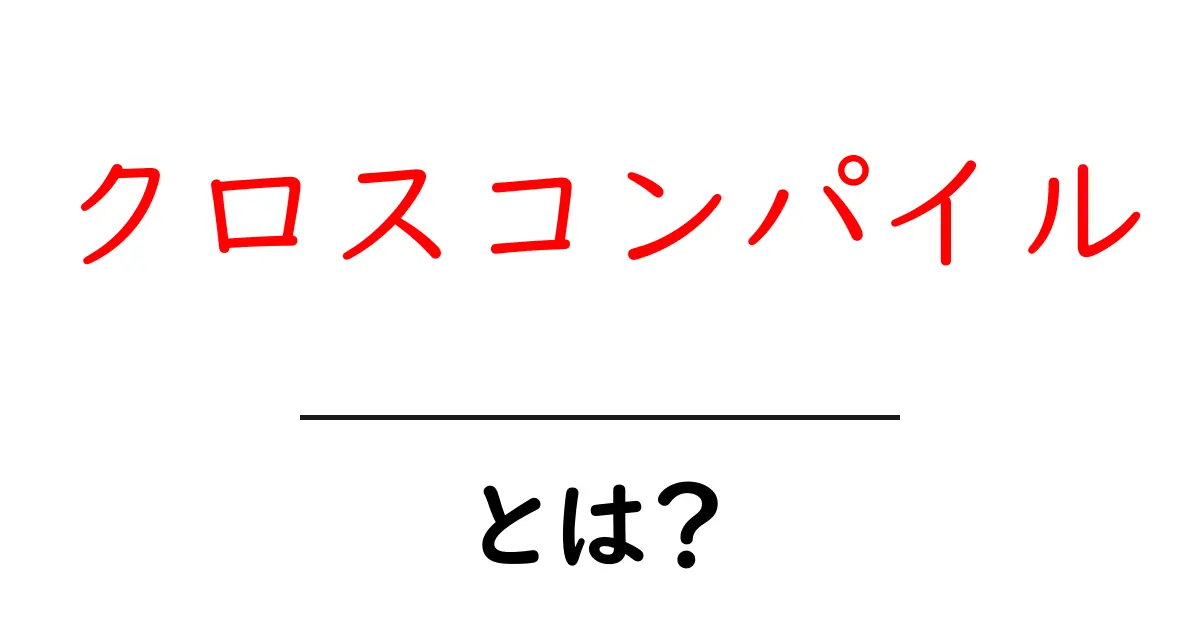
コンパイラ:プログラムコードを他の言語に変換するソフトウェア。クロスコンパイルでは、特に異なるプラットフォーム向けのコードを生成する役割を果たします。
ターゲットプラットフォーム:クロスコンパイルで生成されたコードが実行される環境。異なるOSやアーキテクチャを持つデバイスが含まれます。
ホストプラットフォーム:クロスコンパイルを行う際に使用するコンピュータや環境。通常、開発環境とも呼ばれます。
ビルド:プログラムをソースコードから実行可能な形に変換する工程。クロスコンパイルによってこの工程が異なるプラットフォームに適応されます。
ライブラリ:プログラムでよく使用される機能や処理をまとめた集合体。クロスコンパイルでは、ターゲットプラットフォームに対応したライブラリが必要です。
デバッグ:プログラムのエラーや問題を見つけて修正する作業。クロスコンパイル後のコードもデバッグ作業が必要です。
エミュレーター:異なるプラットフォームを模倣するソフトウェア。クロスコンパイルしたアプリをテストする際に使用されることがあります。
CMake:クロスプラットフォームのビルドツール。特にクロスコンパイルの設定を簡素化するために使用されることが多いです。
クロスプラットフォーム:異なるプラットフォームで動作することを目的としたソフトウェアやアプリケーションを指します。クロスコンパイルはこの考え方に基づいています。
ソースコード:プログラムの設計や処理を記述したテキストファイル。クロスコンパイルはこのソースコードを異なる形式に変換します。
クロスコンパイラ:異なるプラットフォーム向けにコードをコンパイルするための専用ツールです。例えば、Windows上でLinux用のアプリを作ることができます。
クロスビルド:異なるプラットフォーム向けにソフトウェアを構築するプロセスを指します。開発環境と実行環境が異なる場合に用いられます。
クロスプラットフォーム:複数のプラットフォーム(オペレーティングシステム)上で動作することができるソフトウェアやアプリケーションを指します。
エミュレーション:あるプラットフォーム上で別のプラットフォームの動作を模倣する技術です。これにより、異なる環境での動作をテストできます。
ポーティング:既存のアプリケーションを異なるプラットフォーム上で動作させるために修正することを指します。クロスコンパイルとの関連が深い業務です。
クロスコンパイル:異なるプラットフォーム向けにプログラムをコンパイルすること。例えば、Windows上でLinux用のソフトを作る場合など。
コンパイラ:プログラムコードを機械語に変換するツール。クロスコンパイルには、ターゲットプラットフォームに適したコンパイラが必要。
ターゲットプラットフォーム:ソフトウェアが動作する予定の環境やデバイスのこと。これにはOSやハードウェアが含まれる。
ホストプラットフォーム:ソフトウェアを開発するために使用するプラットフォームのこと。プログラマーが作業を行う環境を指す。
クロスプラットフォーム:異なるプラットフォームで動作するソフトウェアのこと。クロスコンパイルを利用することで、こうしたソフトが作成可能。
ビルド:ソフトウェアのソースコードをコンパイルして実行ファイルやライブラリを生成するプロセスのこと。
Makefile:ビルドプロセスを自動化するための設定ファイル。コンパイル時の指示を含むことが多く、クロスコンパイル時にも役立つ。
エミュレーター:あるプラットフォーム上で、別のプラットフォームのソフトウェアを動作させるためのソフトウェア。開発環境のテストとして利用される。
ライブラリ:プログラムで利用される再利用可能なコードの集まり。クロスコンパイルでは、ターゲットプラットフォームに対応するライブラリが必要。
デバッグ:プログラムのバグ(不具合)を見つけて修正する過程。クロスコンパイルされたプログラムのデバッグは特に慎重に行う必要がある。