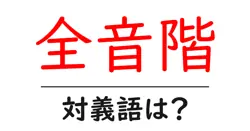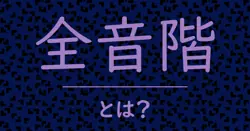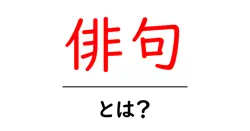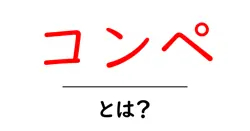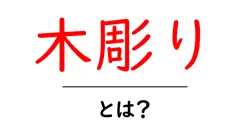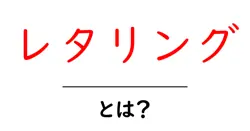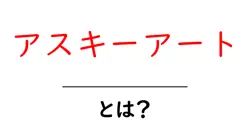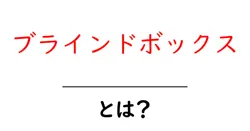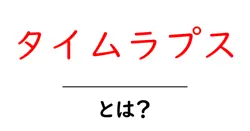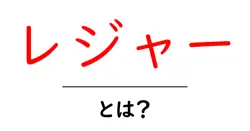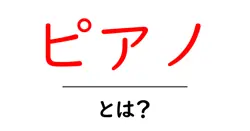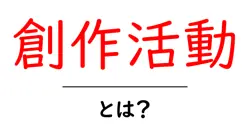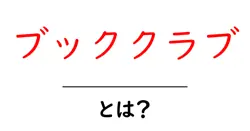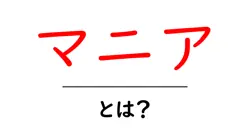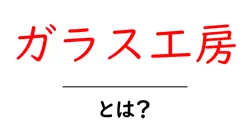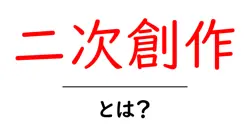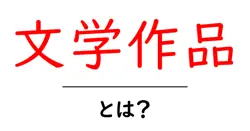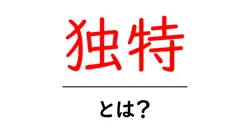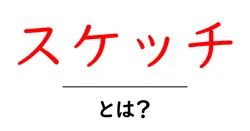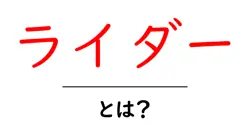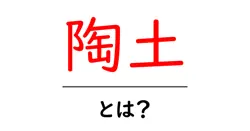全音階とは?音楽の基本を学ぼう!
音楽の世界はとても広く、私たちの日常でも聴くことが多いですよね。その中でも「全音階」という言葉を耳にしたことがある人も多いと思います。今回は、この「全音階」についてわかりやすく解説していきます。
全音階の基本
全音階とは、音楽の音階の一つで、12の音から成り立っています。これらの音は、白鍵と黒鍵を使ったピアノの鍵盤で表現されます。全音階の基本的なルールは、音と音の間の距離、つまり音程によって構成されています。
全音階の構成
全音階は、以下の音で構成されています。
| 音名 |
|---|
| C |
| C# |
| D |
| D# |
| E |
| F |
| F# |
| G |
| G# |
| A |
| A# |
| B |
全音と半音
全音階には「全音」と「半音」があります。全音は、2つの音の間に1つの音を挟む距離を指し、半音は2つの隣り合った音の距離を指します。例えば、CからDまでの距離は全音ですが、CからC#までの距離は半音です。
全音階と音楽の関わり
全音階は音楽の基盤です。ほとんどの楽曲は、この全音階を元に作られています。全音階を理解することで、音楽の仕組みや楽器の演奏がスムーズになります。また、全音階の知識は作曲やアレンジをする際にも重要です。
音楽での全音階の利用
例えば、ピアノの曲やギターの演奏では、全音階を使ってメロディを作ったり、和音を構成したりします。また、全音階を学ぶことで、即興演奏を楽しむことも可能になります。
まとめ
全音階は音楽にとって非常に重要な要素です。全音階について理解を深めることで、より音楽を楽しむことができるでしょう。ぜひ、全音階について興味を持って、音楽の世界を探求してみてください!
音楽:全音階は音楽に関する概念で、楽曲やメロディを作成する基盤となる音の集合です。
音階:音階とは音の高さの順序を示すもので、全音階はその中の一種です。
ドレミ:全音階はドレミの音程で表現されることが多く、初心者でも覚えやすい音名です。
半音:全音階は半音を基本にした音の並びですが、その半音の構造を理解することが重要です。
和音:全音階の音を組み合わせることで和音を作ることができ、楽曲の雰囲気を豊かにします。
メロディ:全音階を使用することで、メロディを作る際の音の選択肢が広がります。
調:全音階は特定の調に基づいて構成され、音楽の中心となるキーを決定します。
楽器:全音階は多くの楽器で使用され、音楽を演奏する際の基本的な知識となります。
クラシック音楽:全音階は特にクラシック音楽において重要な役割を果たし、多くの名曲が全音階を基にしています。
ポピュラー音楽:現代のポピュラー音楽でも全音階は広く使われており、メロディやコード進行に影響を与えています。
音階:音を高低に並べたもので、全音階はすべての音を含む音階を指します。
スケール:音楽理論における用語で、全音階は特にすべての音を含む音の配置のことを示します。
調律:音楽において音を一定の基準に合わせることですが、全音階はその調律の全体を示すことがあります。
鳴り:音楽における音の出方を表す言葉で、全音階では音の鳴り方に多様性があります。
音楽理論:音楽の構造や法則を研究する学問で、全音階もこの理論の一部として理解されます。
音階:音の高低を体系的に並べたもので、音楽における基礎的な概念です。音階によって異なるメロディやハーモニーが構築されます。
ドレミファソラシ:西洋音楽で使われる音階の音名で、全音階における各音を表しています。これらの音を組み合わせることで、楽曲が作られます。
全音:音階において、隣接する2つの音の間に全音の間隔があることを指します。たとえば、ドとレの間が全音です。
半音:全音の半分の音の間隔を示します。ドとド♯のように、隣接する音の間にある最小の間隔です。
メジャースケール:明るい響きを持つ音階の一つで、全音と半音の組み合わせから構成されます。特に人気のある音楽のスタイルで使用されます。
マイナースケール:暗い響きや哀愁を帯びた音階で、特定のパターンに従って全音と半音が配置されています。
調性:音楽において特定の音階を基にした音の組織化を指します。調性は楽曲の中心となる音を持ち、その音が楽曲全体に影響を与えます。
和音:二つ以上の音が同時に鳴ることで生じる音の組み合わせを言います。和音は音楽の重要な要素で、メロディのバックグラウンドを形成します。
調律:楽器の音が正確に音階に合うように調整することを指します。調律が行われることで、楽曲の演奏がより美しくなります。
フラット:音を半音低くする記号で、楽譜の中でよく使われます。フラットがついた音は、元の音よりも低い音になります。
シャープ:音を半音高くする記号で、こちらも楽譜に頻繁に現れます。シャープがついた音は、元の音よりも高い音として演奏されます。