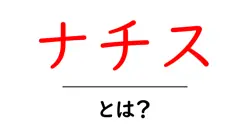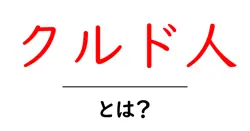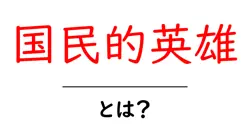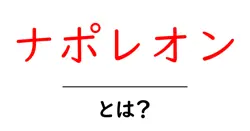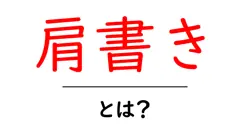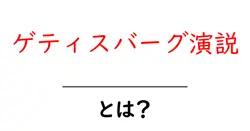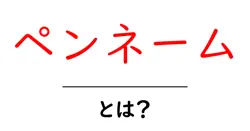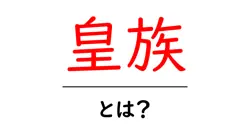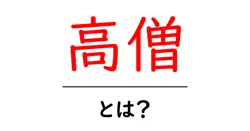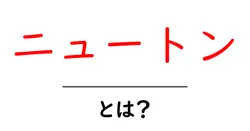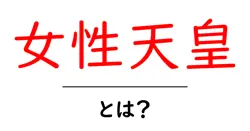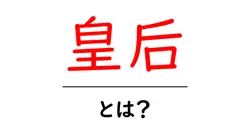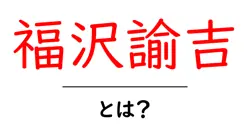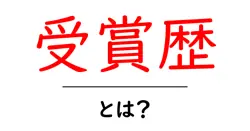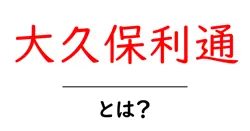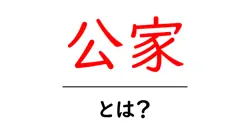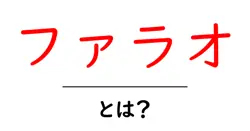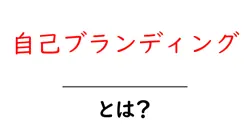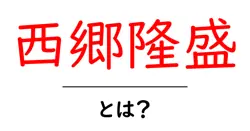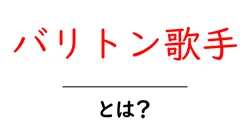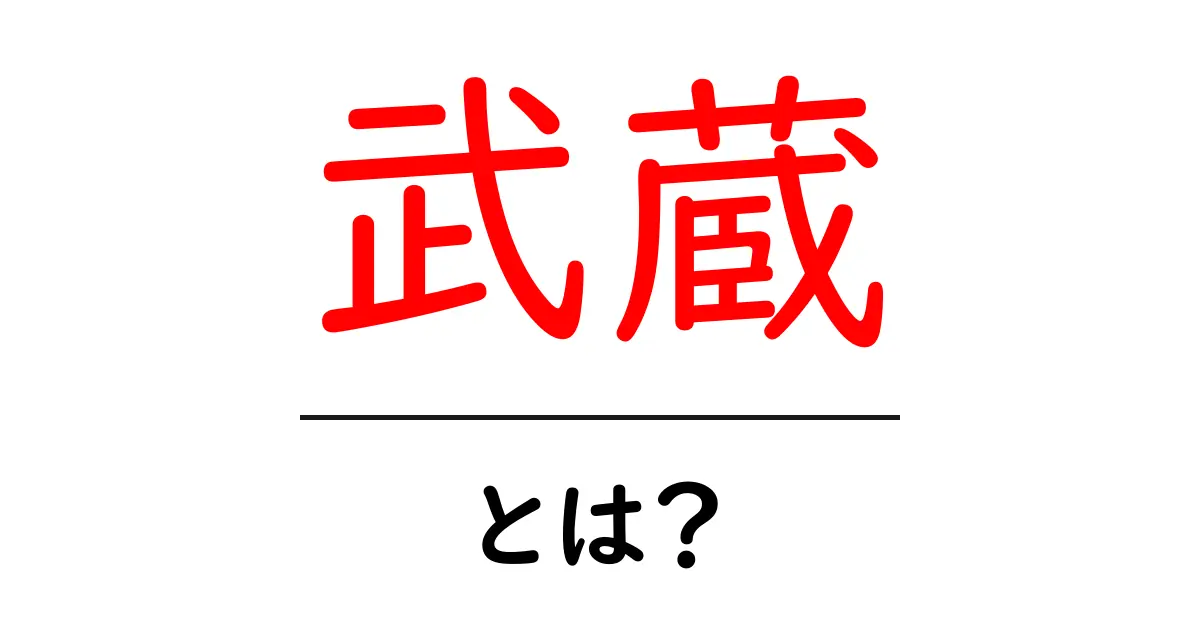
武蔵—その魅力と歴史を知ろう!
「武蔵」と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか?江戸時代の剣豪、宮本武蔵を思い出す方が多いかもしれません。彼は日本の歴史において非常に重要な人物であり、剣術だけでなく芸術や哲学にも携わっていました。この記事では、武蔵の生涯や彼の影響についてやさしく解説していきます。
武蔵の生涯
宮本武蔵は1584年に生まれ、1645年に亡くなりました。彼は若い頃から剣術を学び、多くの試合で勝利を収めました。特に有名なのは、彼が「二刀流」という独自のスタイルで戦ったことです。これは、両手に剣を持って戦う方法で、敵に対して非常に効果的でした。
剣術の達人としての業績
武蔵は生涯で多くの戦いを経験し、その中で得た知識や技術は後の世代にも伝えられています。彼は『五輪書』という書物を著し、ここでは剣術だけでなく、戦うための心構えや生き方についても語っています。この本は現在でも、多くの武道家に影響を与え続けています。
武蔵の影響と文化
武蔵はただの剣豪ではなく、画家としても知られています。彼は水墨画を得意とし、その作品は今でも高く評価されています。彼の画風や考え方は、後の日本の芸術にも影響を与えることになりました。
まとめ
武蔵は、剣術の名人であるだけでなく、多才な人間として歴史に名を残しています。彼の教えや作品は、今でも私たちの心に響きます。
| カテゴリ | 内容 |
|---|---|
| 生涯 | 1584年生まれ、1645年没 |
| 業績 | 二刀流、五輪書の著述 |
| 芸術 | 水墨画の達人 |
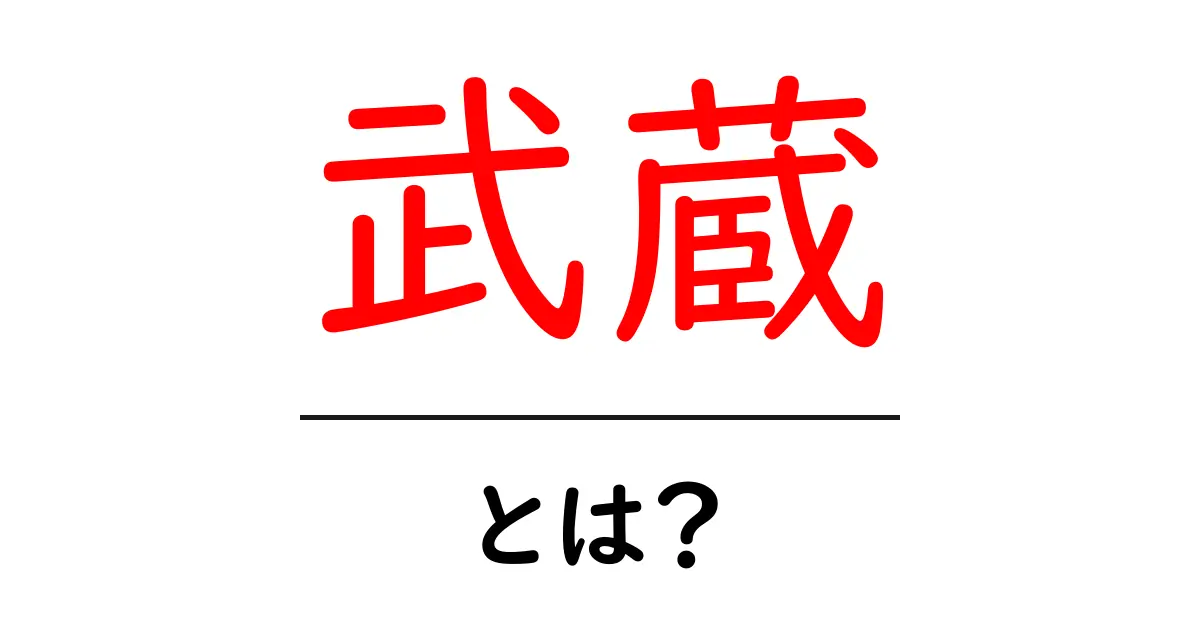
武士:日本の戦士階級を指し、特に武道や戦闘技術に秀でた人々を意味します。武蔵もまた武士の一人です。
剣道:日本の伝統的な武道の一つで、剣を使って技を競い合うスポーツです。武蔵は剣士として名を馳せました。
道場:武道の稽古を行う場所を指し、武蔵も多くの弟子に教えを授けた道場があります。
二刀流:二本の刀を使って戦う戦法のこと。武蔵はこの技術を使用し、名を馳せました。
勝負:戦いや対決を指し、武蔵は多くの剣士と勝負を重ねて技術を磨きました。
戦略:戦の戦術や計画を指し、武蔵はその巧妙な戦略で知られています。
流派:武道や剣術の流れやスタイルを示します。武蔵は自身の流派を確立しました。
書籍:武道や戦略についての書物で、武蔵が著した『五輪書』などが有名です。
師匠:武道や技術を教える人を指します。武蔵にも数人の師匠がいました。
名勝負:歴史に名を残すような素晴らしい戦いを意味します。武蔵にはそのような名勝負が多く存在します。
武士:戦国時代や江戸時代において武器を持ち、戦いに従事した日本の戦士のこと。武士道に則り、高い倫理観や忠誠心を持つことが求められました。
侍:主に武士と同義で使われるが、特に平和な時代において主君に仕える武士を指すことが多い。彼らは戦闘だけでなく、政治や文化にも関与しました。
剣士:剣を使って戦うことを専門とする武道の達人や戦士のこと。他の武器や戦術を使う武士とは異なり、剣術に特化した存在を指します。
騎士:主に西洋における武士のような存在で、騎馬に乗り戦うことが多い。名誉や忠誠心を重んじる点で武士との共通点がありますが、文化背景は異なります。
勇士:勇敢な戦士を意味し、戦闘において際立った勇気を見せる人を指します。武士や侍と同様に、戦いの場面で活躍することが期待されます。
武道家:武道や戦闘技術を修練する人のこと。武道を通じて精神的成長や身体能力の向上を目指します。武士の精神を受け継いだ文化的側面を持ちます。
武士:日本の戦国時代において、戦闘や政治に関与した士族のこと。武蔵の時代背景には武士の文化が深く関わっている。
武蔵野:東京都の西部にある自然豊かな地域を指す言葉。武蔵野では、多くの文化や歴史が育まれた。
武道:武士が行っていた戦う技術や精神を学ぶための道のこと。剣道、柔道、合気道など、日本の伝統的な武道が含まれる。
宮本武蔵:江戸時代初期の剣豪で、二刀流の創始者として有名。彼の著書『五輪書』は武道や戦略に関する教えを示している。
武士道:武士が重んじていた道徳や倫理観。忠義、名誉、礼儀などがその根底にあり、現代にも影響を与えている。
武士階級:日本の封建制度において、特権を持った階級。彼らは戦士としての役割を持つ一方、政治や文化にも大きな影響を持っていた。
武器:武士や戦士が戦闘に使用する道具。刀や弓などが有名で、その技術も武道の一環として学ばれる。
日本刀:日本の伝統的な刃物の一つで、武士が使用した刀。美術品としても評価が高い。
剣術:刀を用いた戦いの技術のことを指す。武蔵は剣術の達人として知られ、多くの流派を創設した。
戦国時代:日本の歴史の中で、戦国大名が各地で戦争を繰り広げた時期。武士の活躍が目立った時代であり、武蔵もこの時期に活躍した。
武蔵の対義語・反対語
該当なし