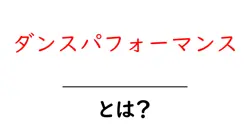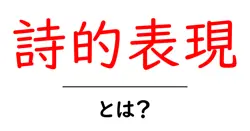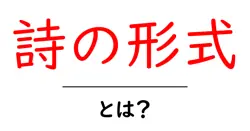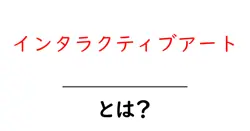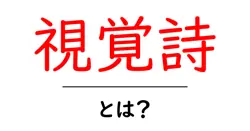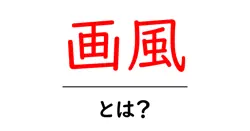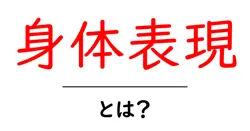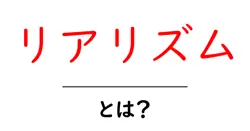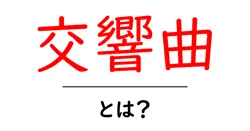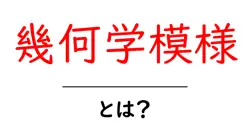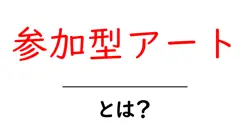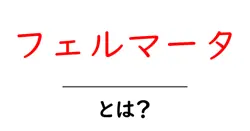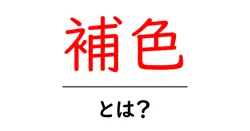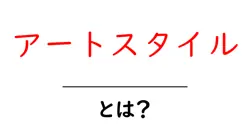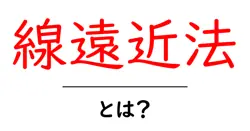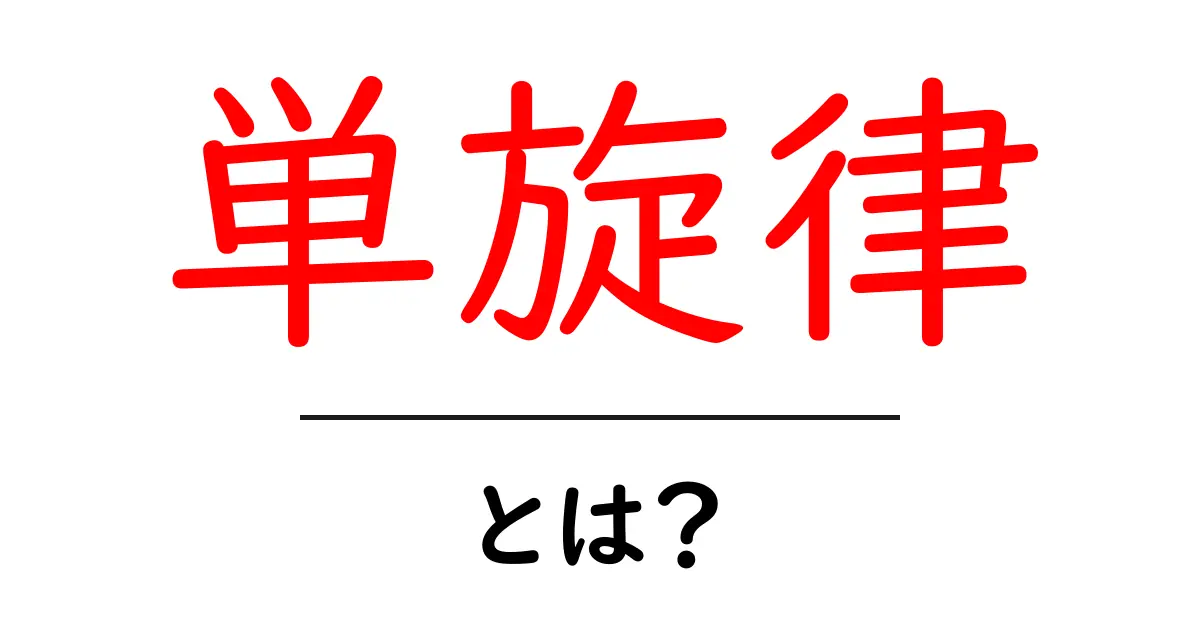
単旋律とは?音楽の基本を理解しよう!
音楽にはさまざまな要素がありますが、その中でも「単旋律」という言葉を聞いたことがありますか?単旋律は、音楽の基本的な形式の一つであり、特に初学者にとって理解することがとても大切です。
単旋律の基本的な定義
単旋律とは、一つの旋律(メロディ)だけの音楽のことを指します。これは、たった一つの声または楽器が奏でる音楽で、和音や複数の旋律が重なることはありません。たとえば、ピアノやギターで単音でメロディを弾くと、単旋律の音楽になります。
単旋律の特徴
単旋律にはいくつかの特徴があります。以下にその主な特徴を示します。
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 一つの旋律 | 単旋律は、ただ一つのメロディが中心となり、伴奏や他のメロディがない。 |
| シンプルな構造 | 音楽的な構造がシンプルで、聴き手にとってわかりやすい。 |
| 感情の表現 | 一つの旋律で感情を強く表現することができる。 |
単旋律の例
具体的に単旋律の例を挙げてみましょう。多くの子供が知っている「きらきら星」のような童謡や、個々の楽器で演奏されるメロディも、単旋律にあたります。また、クラシック音楽の中でも、ピアノソロなどが単旋律の一例です。
単旋律の重要性
単旋律は、音楽の基礎を学ぶ上で重要な要素です。音楽を習い始めたときに、このシンプルな形式を学ぶことで、旋律の作り方や演奏法を理解しやすくなります。また、複雑な和声や多声的な音楽を理解するための土台ともなるのです。
まとめ
単旋律は、一つの旋律で構成されたとてもシンプルな音楽形式です。その理解は、音楽を学ぶ上でとても重要です。これから音楽を学ぶ人は、まずこの単旋律から始めてみましょう。
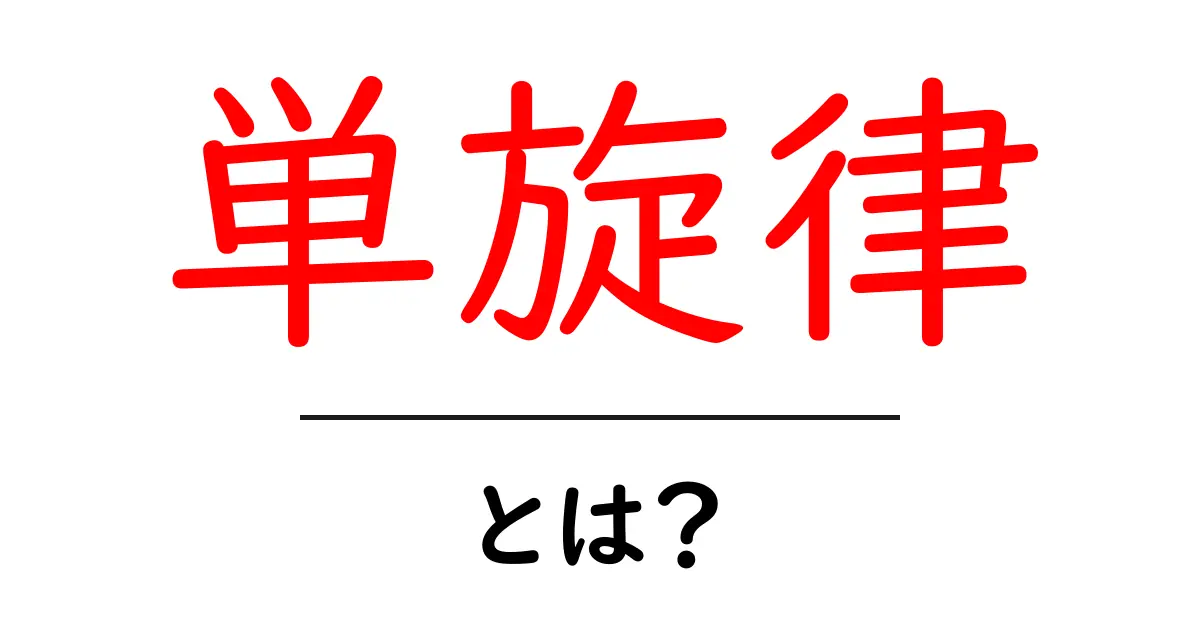
メロディ:音楽において、単旋律のことを指し、特定の音の連なりで構成される楽曲の主旋律です。
単音:音楽理論における、単旋律で使用される一つの音で、和音に対して単独の音のことを意味します。
旋律:音楽の中で、リズムと音高の組み合わせから成る音の連なりのことを指し、単旋律はその一つの形態です。
調性:音楽での音の関係性を示す概念で、単旋律が特定の調性に基づく場合、より一層の印象を与えます。
リズム:音楽の時間的な要素の一つで、単旋律の進行にともなう拍子やテンポのことです。
フレーズ:音楽における意味のある音の塊で、単旋律を形成する一部として考えられます。
ハーモニー:音楽理論において、複数の音が同時に鳴ることを指し、単旋律と対比されそとは、歌や演奏においての響きの要素として付加されます。
即興演奏:音楽を作りながら演奏するスタイルで、単旋律を基にした即興のフレーズが生まれることがあります。
楽譜:音楽を記述するためのシンボルの集合で、単旋律も楽譜に記載されて演奏されます。
メロディー:音楽の中での歌の部分や主題となる旋律のこと。通常は単独で演奏され、楽曲の感情や雰囲気を表現します。
旋律:音の高低が順序よく並んだもので、音楽の基本的な要素です。単旋律は一つの旋律で構成されることを意味します。
単音:一度に一つの音だけを出すこと。単旋律は単音の集合として見ることもでき、ハーモニーが存在しない音楽スタイルを指します。
シングルトーン:一つの音を繰り返し奏でたり、発声したりすること。単旋律の特色として、一つの音が中心となります。
メロディ:音楽における旋律のこと。単旋律は、一つのメロディだけで構成されている音楽を指します。
和声:メロディに対してハーモニーを加える音楽技法のこと。単旋律は和声を使わず、一つの音の流れで表現されます。
楽器:単旋律を演奏するための器具。単旋律は、ピアノやギターなど、どんな楽器でも表現できます。
フレーズ:音楽の中での短いメロディのまとまり。単旋律にも、複数のフレーズが組み合わさることがあります。
リズム:音楽の拍や強弱のパターン。単旋律にもリズムが伴い、メロディをより魅力的にします。
音域:楽器や声が出せる音の範囲。単旋律は、その音域を使い分けてさまざまな表現が可能です。
即興:事前に計画せずにその場で演奏すること。単旋律は、即興演奏でもよく用いられます。
対位法:複数の旋律を同時に組み合わせる音楽技法。単旋律は、対位法を用いず、一つの旋律に集中します。
リピート:同じ部分を繰り返すこと。単旋律でもリピートを使うことで、聴き手に印象を与えることができます。
テーマ:音楽の中心思想やメロディ。単旋律は、テーマを基に展開されることが多いです。
単旋律の対義語・反対語
該当なし
芸術の人気記事
次の記事: 氷柱とは?冬の美しい自然現象を知ろう共起語・同意語も併せて解説! »