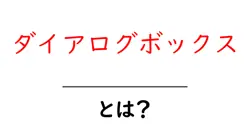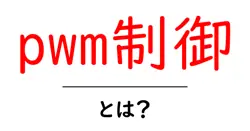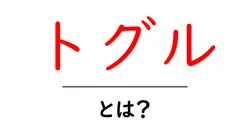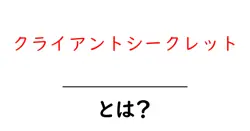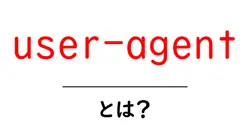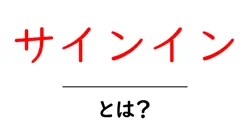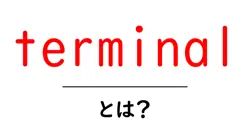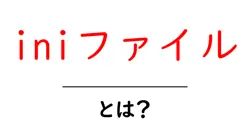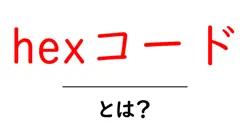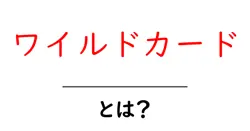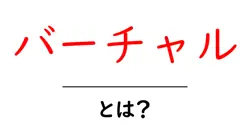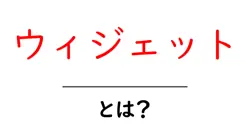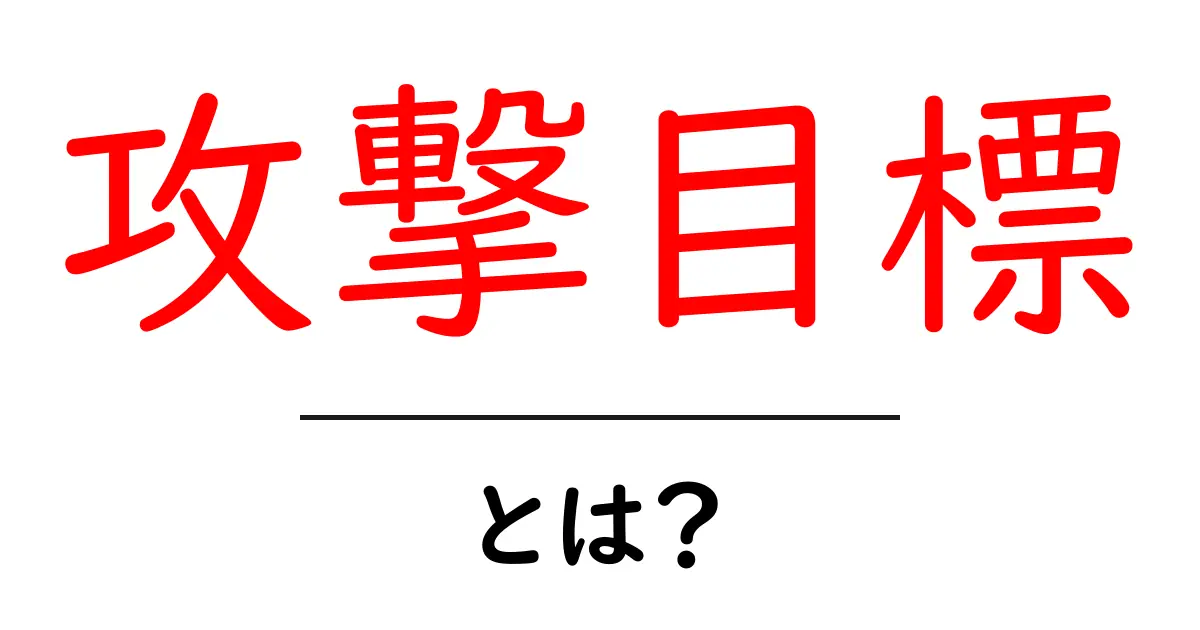
攻撃目標とは?
攻撃目標(こうげきもくひょう)という言葉は、主にサイバーセキュリティやネットワークの分野で使われる用語です。これは、攻撃者が特定のシステムやネットワーク、データを狙って攻撃を行う際のターゲットを指します。
攻撃目標の種類
攻撃目標にはいくつかの種類があります。その中にも、企業のウェブサイトや個人のアカウント、または政府機関のデータベースなど、様々なものが含まれます。攻撃者は、どのようなデータや情報が重要であるかを考え、狙う対象を選びます。
具体的な攻撃目標の例
| 攻撃対象 | 説明 |
|---|---|
| 企業のウェブサイト | 顧客情報や販売データを盗むために狙われることがある。 |
| 個人のSNSアカウント | 個人情報やプライベートなデータを盗むために攻撃される。 |
| 政府のデータベース | 機密情報を取得するために狙われることが多い。 |
なぜ攻撃目標が重要なのか?
攻撃目標を理解することは、ネットの安全性を保つために非常に重要です。攻撃者がどのような情報を狙っているかを把握することで、それに対する対策を講じることができます。例えば、企業は自社のウェブサイトを守るために、セキュリティ対策を強化することができます。
対策例
- ファイアウォールを設置する
- 定期的なシステムのアップデート
- 利用者へのセキュリティ教育
まとめ
攻撃目標という言葉は、攻撃者が狙う対象を示す重要な概念です。この理解を深めることで、自分自身や自社を守るための有効な策を見つけることができます。常に最新の情報に注意を払い、安全なネットライフを送ることが大切です。
サイバー攻撃:インターネットを利用した攻撃で、企業や個人の情報を盗んだり、システムを麻痺させる行為を指します。
脆弱性:システムやソフトウェアに存在する弱点のこと。攻撃者がその弱点を悪用することで、攻撃目標が被害を受ける可能性があります。
防御手段:攻撃からシステムを守るための方法や技術ネットワークファイアウォールやウイルス対策ソフトなどが含まれます。
フィッシング:ユーザーを騙して個人情報を引き出そうとする手法で、攻撃目標として特定の個人や団体を狙います。
マルウェア:悪意のあるソフトウェアの総称で、攻撃目標に感染することで情報漏洩やデータ損失を引き起こす可能性があります。
DDoS攻撃:多数のコンピュータを使って特定のサーバーに大量のトラフィックを送りつけ、サービスを停止させる攻撃手法です。
リスク管理:攻撃目標に対してどのようなリスクが存在するのかを把握し、それに対処する計画を立てることです。
セキュリティポリシー:組織の情報システムを守るために設けられた規則や方針で、攻撃目標をどう防ぐかの指針を示します。
侵入テスト:システムのセキュリティを確認するために、実際に攻撃を模倣してテストを行うことです。
ターゲット:攻撃目標となる特定の人物、団体、またはシステムを指します。その特性や弱点を熟知した上で攻撃が行われます。
ターゲット:攻撃の対象となるものを指します。例えば、サイバー攻撃では特定のシステムやデータがターゲットになります。
目標:攻撃によって達成しようとする対象や目的を表します。軍事やサイバーセキュリティの分野でよく使われます。
対象:攻撃や行動の対象となる個体や組織を指します。
攻撃対象:具体的に攻撃されることを意図したもの、または攻撃の焦点となるものです。
的:目指す場所や対象を意味します。一般的には「ターゲット」と同じ意味で使われますが、使い方によっては異なるニュアンスを持つこともあります。
狙い:特定のものや対象を攻撃や行動の際に標的とすることを意味します。
脆弱性:システムやネットワークに存在する弱点で、これを悪用されることで攻撃の対象となる可能性があります。
ペネトレーションテスト:実際に攻撃をシミュレーションしてシステムの安全性を評価するためのテストで、攻撃目標に対する脆弱性を見つける手法です。
悪意のある攻撃者:データの盗難や破壊など、害を及ぼす意図でシステムに侵入しようとする人物やグループを指します。
ファイアウォール:不正侵入を防ぐためのネットワークセキュリティシステムで、攻撃目標へのアクセスを制御します。
マルウェア:悪意のあるソフトウェアの総称で、システムに感染させて情報を盗む、または機能を妨害することを目的としています。
攻撃ベクトル:システムやネットワークに対して攻撃が行われる経路や手法を指します。例えば、フィッシング、DDoS攻撃などです。
セキュリティパッチ:システムやソフトウェアの脆弱性を修正するために提供される更新プログラムで、攻撃目標となるリスクを軽減します。
インシデントレスポンス:セキュリティインシデントが発生した際の対応プロセスで、攻撃目標への影響を最小限に抑えるための計画的手順です。
攻撃目標の対義語・反対語
該当なし