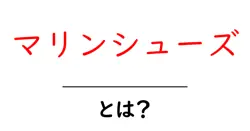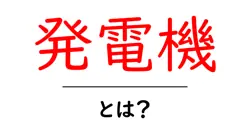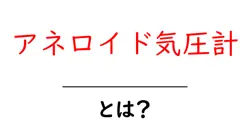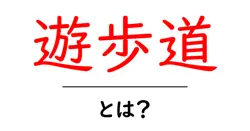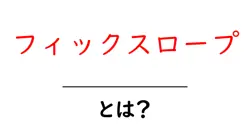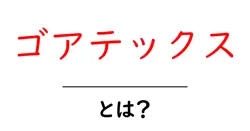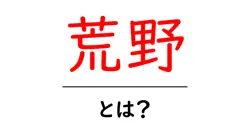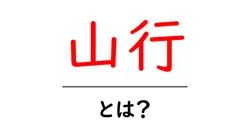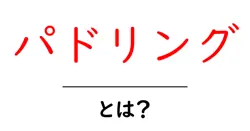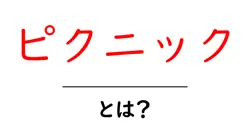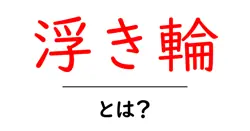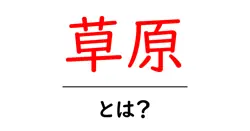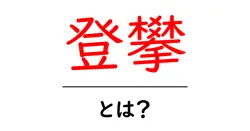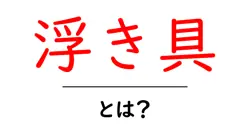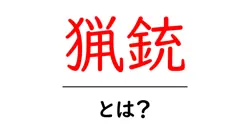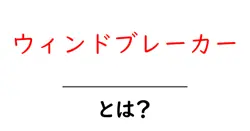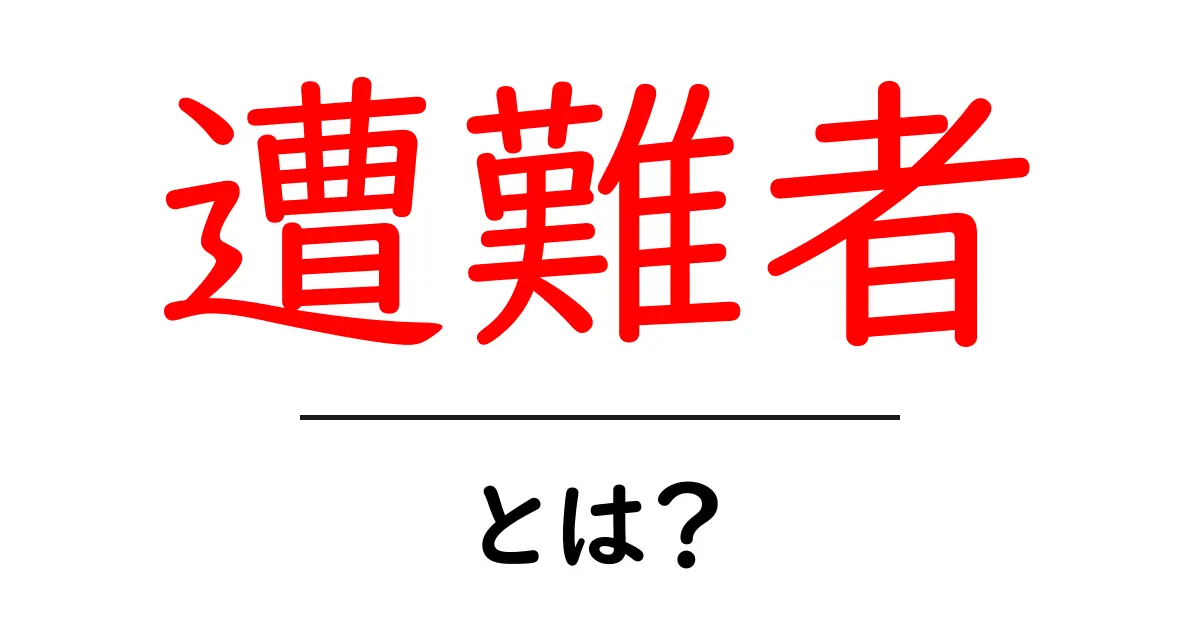
遭難者とは?
「遭難者」は、特に山や海などの自然環境で、方向を見失ったり、危険な状況に陥ってしまった人を指します。日本では、特に登山やキャンプを楽しむ人々が多く、そうした場所での遭難事故は時折報じられます。
遭難者の原因
遭難の原因はさまざまです。主なものには次のようなものがあります:
| 原因 | 説明 |
|---|---|
| 道を間違える | 地図や標識を頼りにしても、読み違えたりして道を誤ること。 |
| 天候の変化 | 急な天候の悪化により、視界が悪くなったり、凍結したりすること。 |
| 体力の限界 | 無理をして進みすぎて、体力が尽きること。 |
| 事故や怪我 | 落石や滑落などの事故によって動けなくなること。 |
遭難を防ぐためのポイント
遭難を避けるためには、以下のポイントに注意が必要です:
- 事前の計画: 行く場所の調査や必要な道具を用意すること。
- 天候確認: 出発前に天気予報をチェックし、怪しいときは中止すること。
- 仲間と行動: 一人で出かけるのではなく、友人や家族と一緒に行動すること。
- 現実的な目標: 自分の体力に合ったルートを選ぶこと。
遭難した場合の対策
万が一遭難した場合には、以下のような対策を考えるべきです:
- 冷静さ: 落ち着いて、まず自分の状況を把握する。
- 位置確認: 自分がどこにいるかを確認し、移動が必要か判断する。
- 助けを呼ぶ: 携帯電話が使える場合は、救助を呼ぶ。
- サバイバル技術: 簡易なシェルターを作る、水を確保する、などの基本技術を身につける。
このように、遭難者という言葉は単なる事故の一部ではなく、多くの人が気をつけるべき危険と、正しい知識が必要な重要な問題です。自然を楽しむ魅力は大きいですが、安全第一で行動することが何よりも重要です。
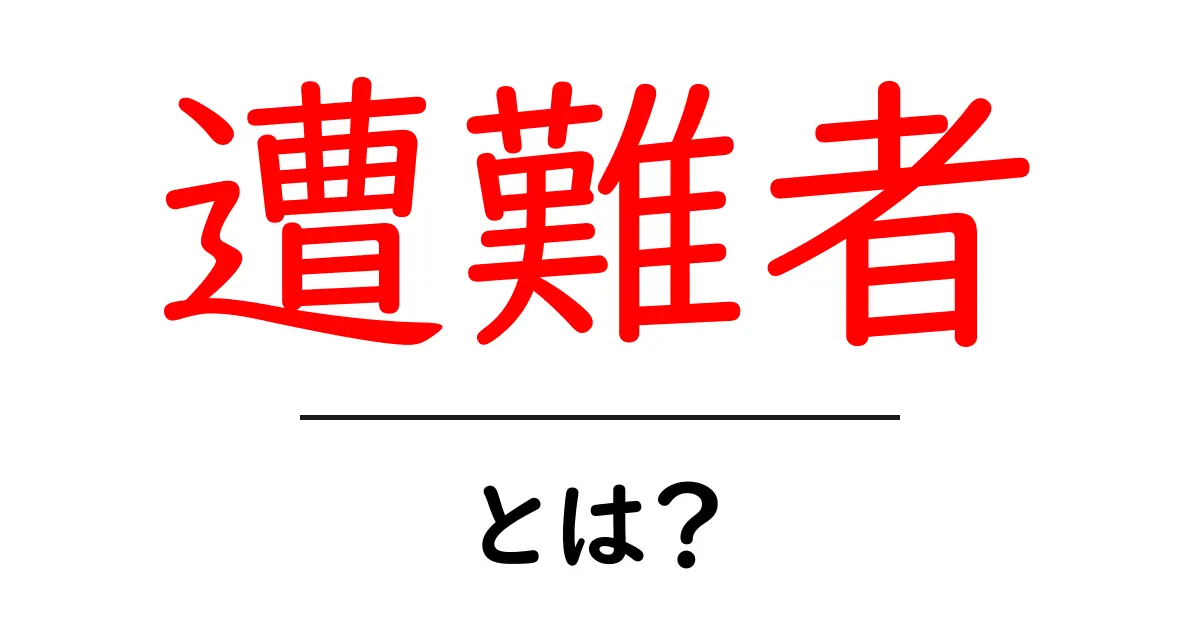
救助:遭難者を助けることや、危険な状況から安全に逃すための行動を指します。
捜索:遭難者を探し出すための活動。地元のボランティアや警察、救助隊が行います。
遭難:予期せぬ事態に遭遇し、特に山や海などで行方不明になったり身動きが取れなくなることを指します。
安全:危険がない状態を意味し、遭難者が無事に救助されることが求められます。
予防:遭難のリスクを減らすための事前の対策を指します。計画を立てることや必要な装備を整えることが含まれます。
体調:遭難者の健康状態を指し、特に寒さや疲労が深刻な場合には重要になります。
通信:遭難時に外部と連絡を取るための手段。携帯電話や無線機などが使われる。
サバイバル:遭難した際に生き延びるための技術や知識、方法を指します。
経験:遭難や救助に関する知識やスキルを持っていることが、行動を有利に進めることがあります。
ボランティア:遭難者の捜索や救助を手助けする無償の支援を行う人々。地域の人々が参加することが多い。
迷子:元々の目的地から離れてしまい、どこにいるか分からなくなった人
行方不明:何らかの理由で所在が分からなくなっている人
孤立者:周囲から隔てられ、助けを求めることができない状況にある人
遭難者:山や海などの自然環境で危険な状況に陥ったり、道に迷ったりして救助が必要な人
遭遇者:意図せずに危険な状況に遭遇した人
遭難:特定の場所や状況において、目的地に到達できずに危険な状態に陥ることを指します。主に登山や山道、海上などで起こることが多いです。
救助:遭難者を安全な場所へ救い出す行為のことです。消防士や警察、ボランティア団体が行うことが一般的です。
遭難信号:遭難した際に、自分の位置や状況を外部に知らせるための信号や合図のこと。サバイバルシートやホイッスル、フラッグを使うことがあります。
サバイバル技術:遭難時に生存するための技術や知識のこと。水の確保、食料の調達、避難所の設置などが含まれます。
緊急事態:突発的に発生した危険な状況を指し、迅速な対応が求められる状態のことを指します。遭難はこの一例です。
位置情報:GPSや地図を使って自分の現在地を特定する情報のこと。遭難時には特に重要で、自分の位置を明確にすることで救助を求めやすくなります。
予防策:遭難を未然に防ぐための対策。事前に天候情報を確認したり、装備を整えたりすることが重要です。
エマージェンシーキット:緊急時に必要な物品をまとめたキットのこと。応急処置用品や食料、水、ナイフなどが含まれることが一般的です。
登山計画書:登山を行う際に、行き先やルート、所要時間を記載した書類のこと。これを提出することで、万が一の際に救助が行いやすくなります。
遭難場所:遭難が発生した特定の地点。地形や気象条件によって遭難のリスクが高まる場所が存在します。
遭難者の対義語・反対語
該当なし