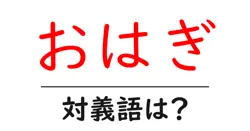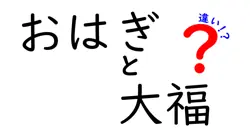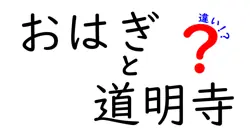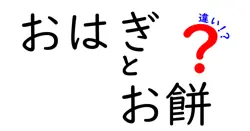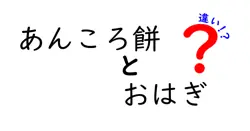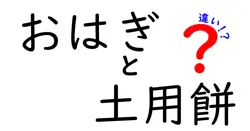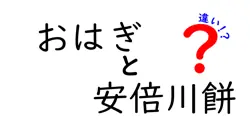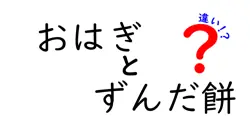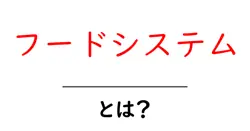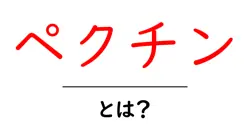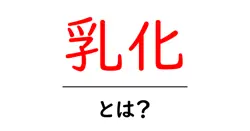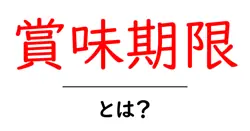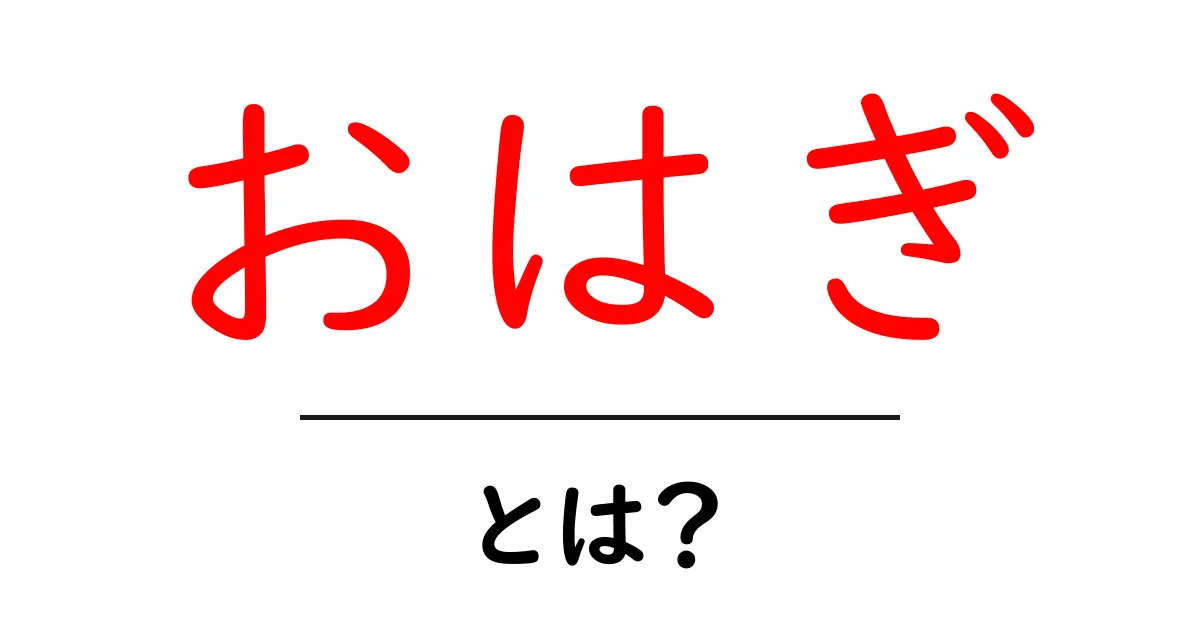
おはぎとは?
おはぎは、日本の伝統的なお菓子で、主にお米を使って作られます。和菓子の一種で、もち米やうるち米を調理し、あんこをまぶしたり包んだりします。そのため、甘い味わいともちもちとした食感が特徴です。
おはぎの歴史
おはぎは日本で古くから食べられており、特に秋の彼岸(ひがん)の時期に供えられることが多いです。その起源は、庶民の間で残った米を大切に使うために、あまりの米を加工して食べる風習から来ていると考えられています。
おはぎとぼたもちの違い
おはぎは、春のお彼岸に食べるぼたもちと似ている部分がありますが、主に作る時期や使用する材料によって名前が変わります。おはぎは秋に食べるのに対して、ぼたもちは春に食べるとされ、この時期で使う小豆の収穫時期も関係していると言われています。
おはぎの作り方
おはぎを作るのは意外と簡単です。以下に基本的な作り方を説明します。
材料
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
| もち米 | 2合 |
| うるち米 | 1合 |
| あんこ(こしあん) | 200g |
| 黒ごまやきな粉 | 適量 |
手順
- もち米とうるち米を混ぜて洗い、数時間水に浸します。
- 炊飯器でご飯を炊きます。
- 炊き上がったご飯を少し冷まし、手が触れる程度の温度にします。
- 手に水をつけて、ご飯を握り、お好みの大きさに成形します。
- 成形したご飯の中心にあんこを入れ、周りを包みます。
- 最後に、黒ごまやきな粉をまぶして完成です。
まとめ
おはぎは、日本の伝統的なお菓子で、家庭でも簡単に作ることができます。秋の彼岸には特に多く食べられるので、この時期にぜひ挑戦してみてください。甘さともちもちの食感が楽しめるおはぎを、家族や友達とシェアするのも素敵ですね。
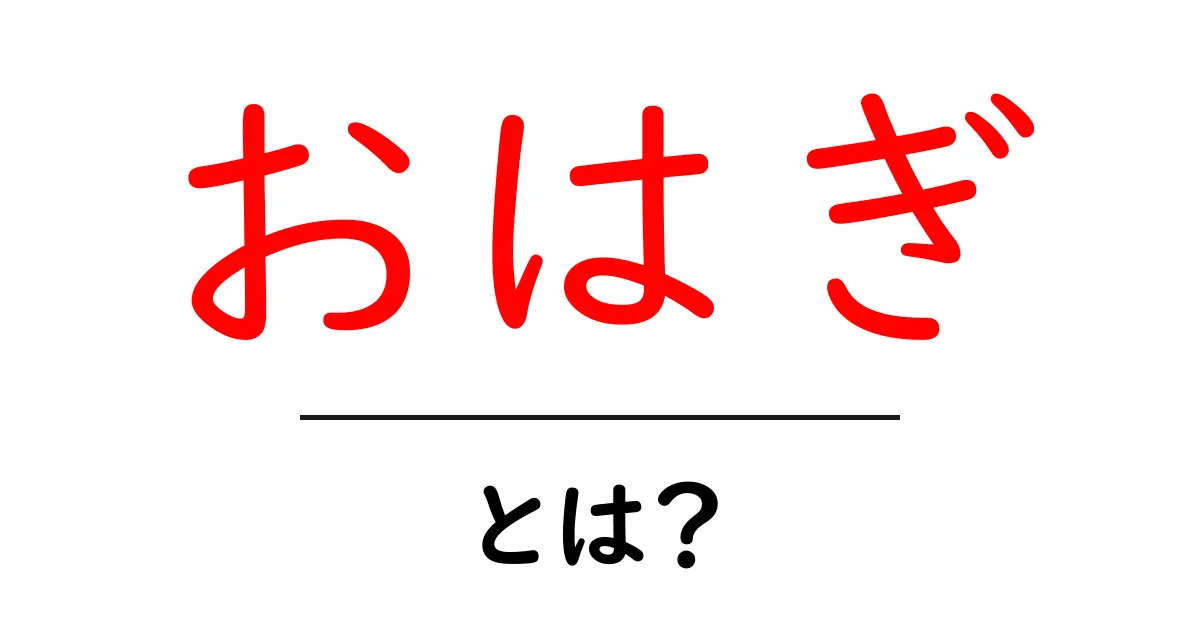 美味しさの秘密と作り方を徹底解説!共起語・同意語も併せて解説!">
美味しさの秘密と作り方を徹底解説!共起語・同意語も併せて解説!">おはぎ 半殺し とは:おはぎは、日本の伝統的な和菓子で、もち米とあんこを使って作られています。その中でも「半殺し」とは、もち米を完全に潰さずに、少し残した状態のことを指します。これによって、おはぎのもちもち感とあんこの甘さが絶妙に調和し、食感が楽しくなります。 まず、半殺しのおはぎを作るには、まずお米をしっかりと洗い、2時間ほど水に浸けておきましょう。その後、炊飯器で炊き上げます。お米が炊けたら、熱いうちにすりこぎや麺棒を使って、軽くつきましょう。全体がべちゃっとならないように、固まりを残すのがポイントです。あんこは、こしあんやつぶあん、好みで選びます。 最後に、半殺しにしたお米を手のひらに取り、あんこを包み込み、形を整えたら完成です。見た目にも美しいおはぎを作って、家族や友達と楽しんでみてください。和菓子の中でも特に簡単に作ることができるので、ぜひ挑戦してみてください。
もち米:おはぎの主な材料です。もち米は、柔らかく粘り気のあるごはんを作るための米で、おはぎには特に重要です。
あんこ:おはぎの中に包まれる甘いあんこのことです。一般的には、こしあんや粒あんが使用されます。
きな粉:おはぎにまぶすことが多い、炒った大豆を粉にしたものです。風味を加えるためによく使われます。
お彼岸:おはぎがよく作られる時期の一つです。春分の日や秋分の日がある季節を指し、先祖を供養する習慣があります。
和菓子:日本の伝統的な菓子の総称で、おはぎもその一つです。和の素材を使った甘いお菓子が含まれます。
季節:おはぎは特に春と秋に人気がありますが、季節によってその作り方や食べ方に変化があります。
供養:おはぎは、お祭りや先祖の供養に供えられることから、特別な意味を持つ食べ物です。
お祝い:おはぎは、祝い事や特別な日にも食べられることがあります。家族や友人と一緒に楽しむ意味合いがあります。
手作り:おはぎは家庭で手作りされることが多く、自分で作ることで愛情や思いを込めることができます。
甘さ:おはぎの特徴的な要素で、あんこの甘さや使用する砂糖の種類によって風味が変わります。
あんころ餅:おはぎと同様に、もち米を用いて作られ、あんこで包まれた甘いお菓子のこと。
ぼたもち:春のお彼岸に食べられるおはぎの一種。主に白ごまを用いて、もち米とあんこで作られる。
お浸し:おはぎとは異なるが、伝統的な和食に見られる調理法の一つで、主に野菜を使った和風の料理。
和菓子:おはぎを含む日本の伝統的な甘いお菓子全般を指す広い概念。
もちはん:おはぎと同じように、もち米を使用して作られる甘いお餅の一種。それぞれ地域によって呼び名が異なることがある。
和菓子:日本の伝統的なお菓子で、米や豆、砂糖を主な材料としています。おはぎも和菓子の一種です。
もち米:おはぎの主成分の一つ。通常の米よりも粘り気が強く、特におはぎや餅などの和菓子に使われます。
あんこ:甘く煮た豆(主に小豆)を潰して作るペースト。おはぎの中に入ったり、外にコーティングされたりします。
祝日:おはぎが特に食べられる日で、秋の彼岸やお盆などの時期に家庭で作られることが多いです。
もなか:薄いおせんべいの中にあんこを詰めた和菓子で、おはぎと同様に甘いものですが、食感や形が異なります。
だんご:もち米やうるち米を使った団子で、串に刺して焼いたり、煮たりします。おはぎとは異なるが、米を用いた点で関連性があります。
餅:もち米を蒸してついたもの。おはぎの土台となるもち米と似ていますが、形状や食べ方が異なります。
甘味処:和菓子や甘い飲み物を提供するお店のこと。おはぎなどの和菓子を楽しむことができます。
季節の行事:おはぎが特に作られる秋の彼岸や春のお彼岸など、特定の行事や時期に関連した文化的なイベントですが、その背景も意味を持っています。