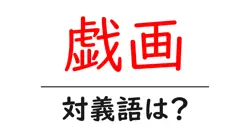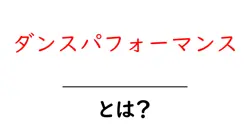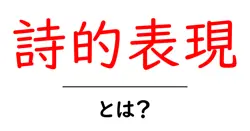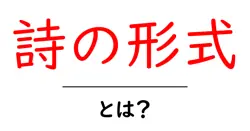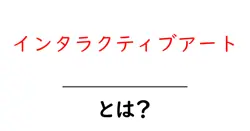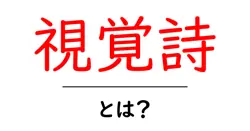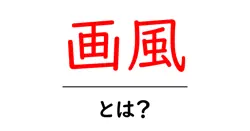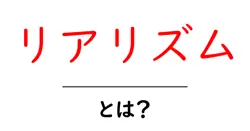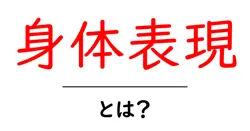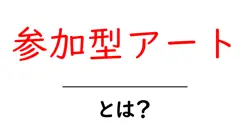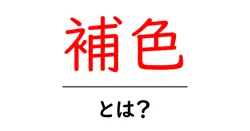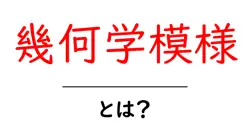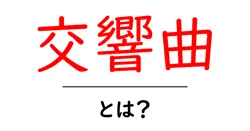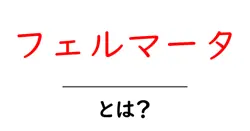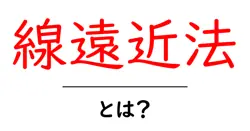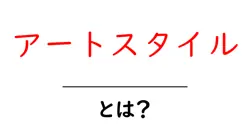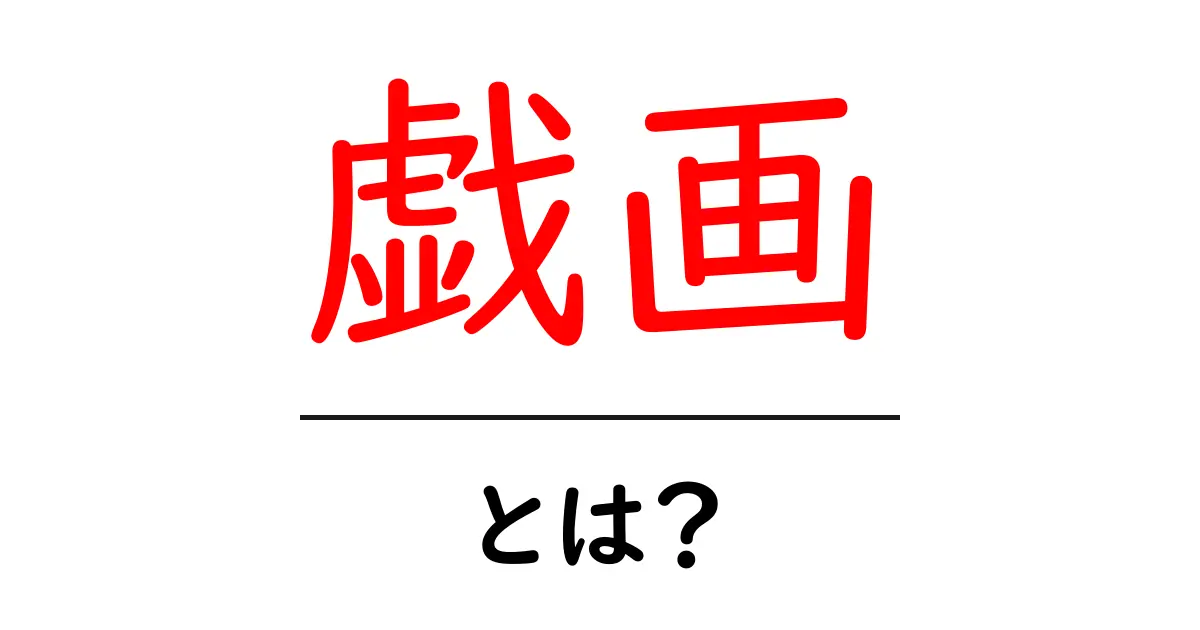
戯画とは?その歴史や特徴をわかりやすく解説!
皆さん、戯画(ぎが)という言葉を聞いたことがありますか?戯画とは、日本の伝統的な絵画の一種で、人や動物をおもしろおかしく描いた作品のことを指します。この文章では、戯画の意味や歴史、特徴について詳しく説明していきます。
戯画の基本的な意味
戯画は、一般的には人々や動物をユーモラスに描いた絵画です。絵の中には、時には風刺(ふうし)が効いているものもあります。戯画の特徴は、リアルではなく、面白さやおかしみを前面に出しているところです。こうしたスタイルの作品は、古くから日本の文化に根付いています。
戯画の歴史
戯画の起源は、鎌倉時代(1185年-1333年)にまでさかのぼります。当時は、絵巻物に描かれることが多く、物語や伝説をユーモラスに表現していました。その後、江戸時代(1603年-1868年)に入ると、より多くの人々に親しまれるようになり、さまざまな戯画が数多く作られました。
戯画の特徴
戯画には以下のような特徴があります。
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| ユーモラスな表現 | 普通の絵画と違い、面白く描くことが主な目的。 |
| 風刺的な要素 | 社会や政治を批判する意味を持った作品もある。 |
| 多様なテーマ | 動物や日常生活、人間関係など様々なテーマで描かれる。 |
戯画の代表的な作家
戯画には、多くの著名な作家がいます。たとえば、歌川国芳や北斎らは、その独自のスタイルで日本の絵画界に大きな影響を与えました。これらの作家たちの作品は、江戸時代において非常に人気があり、今でも高く評価されています。
まとめ
戯画は、日本の伝統文化の一部として、ユーモアを大切にした素晴らしい絵画です。歴史とともに変化しながらも、多くの人に愛されている戯画の世界をぜひ知っていただきたいと思います。
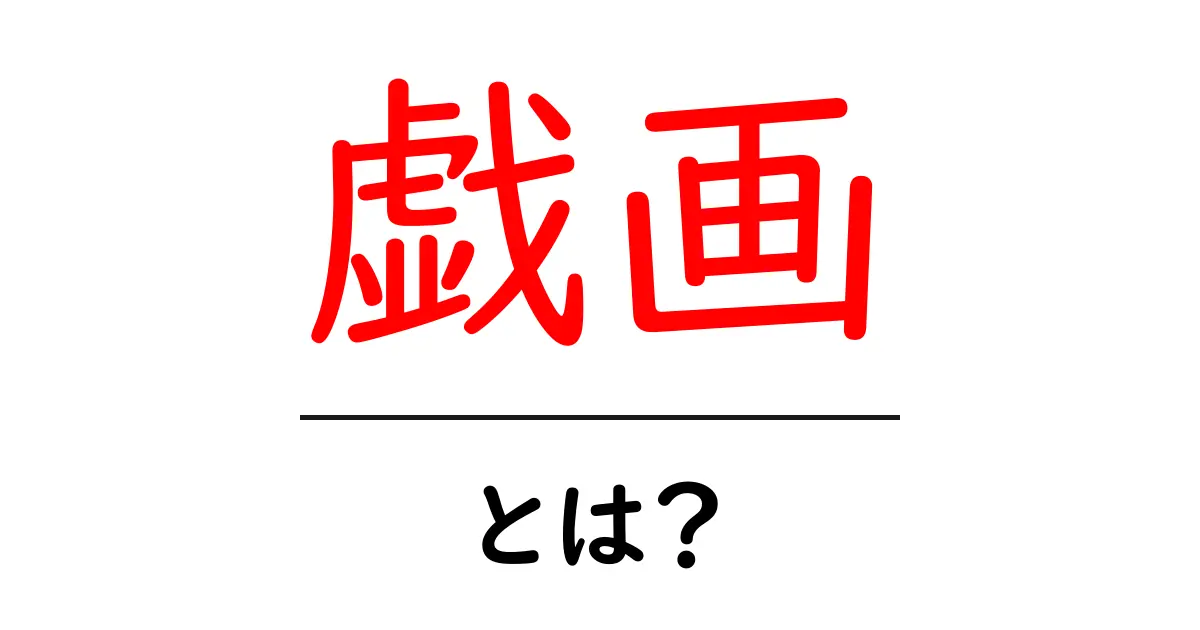
鳥獣 戯画 とは:鳥獣戯画(ちょうじゅうぎが)は、日本の平安時代の絵巻物で、かわいらしい動物たちが描かれています。この作品は、ウサギやカエル、サルなど、さまざまな動物が人間のように振る舞うシーンが特徴です。特に、動物たちがお相撲を取ったり、遊んでいる様子は、とてもユニークで楽しく感じるでしょう。 この絵巻物は、元々は聞いたこともある「鳥獣戯画」の名前通り、鳥や獣が主役になっています。また、画風はユーモアにあふれ、動物たちの表情が豊かで、生き生きとしています。それが多くの人に愛され、今も大切に保存されています。 鳥獣戯画は、ただのアート作品だけでなく、日本の古い文化や風習を感じさせる重要な資料でもあるのです。また、動物たちの行動から、人間社会のことを考えさせられるメッセージも含まれています。現在では、学校の授業でも取り上げられることが多く、幅広い世代に親しまれています。文化としての価値だけでなく、見る人を楽しませる作品としても、有名です。自分も一度、このかわいらしい動物たちの世界を楽しんでみてはいかがでしょうか?
イラスト:視覚的な表現として描かれた絵や図のこと。戯画はイラストを用いて表現されることが多い。
漫画:ストーリーやキャラクターを持った絵を使った物語形式の作品。戯画は漫画と同様にストーリー性があることがある。
ユーモア:人を笑わせる要素や、軽妙な表現を指す。戯画はしばしばユーモアを交えて人間社会や風俗を描く。
風刺:社会や政治の問題を批判的に取り扱う手法のこと。戯画は風刺的な要素を含むことがよくある。
キャラクター:物語に登場する人物や動物などの設定された性格を持つ存在。戯画では独特なキャラクターが多く描かれる。
表現:感情や考えを伝える方法。戯画は独自のスタイルや技法で様々な表現を行う。
ストリップ:一連の描写で物語を語る手法。戯画もストリップ形式で展開されることがある。
情景:特定の場面や状況を描写したもの。戯画では情景が重要な役割を果たすことがある。
歴史:過去の出来事や人物を指す。戯画はしばしば歴史的な文脈の中で描かれることがある。
文化:特定の社会や集団の持つ価値観や習慣など。戯画は文化を反映し、地域や時代によって異なることがある。
漫画:日本のコミックやグラフィックノベルの形式で、戯画と同様に表現が自由で楽しさが重視されます。
アニメ:動きのある絵として表現される芸術の形式で、戯画のスタイルやテーマが多く取り入れられています。
イラスト:視覚的な表現として描かれた絵画や画像で、戯画の特徴的なスタイルが見られることがあります。
風刺画:政治や社会の問題を笑いや皮肉を交えて表現した絵画で、戯画の中にはその要素を持つものもあります。
コミックアート:絵と物語を組み合わせてカラフルに表現する芸術形式で、戯画の持つ楽しさや遊び心が存分に発揮されます。
ジャンル:戯画は「日本の漫画」の一ジャンルとされることが多いです。特に、風刺やユーモアを用いたものを指し、社会や政治を題材にすることが多いです。
浮世絵:戯画は浮世絵の影響を受けていることがあります。浮世絵は江戸時代に流行した版画で、生活の一部を描写した作品が多いです。
風刺画:戯画は風刺画の一種とも考えられます。風刺画とは、社会問題や人物を批判的に描いた絵であり、通常はユーモアを交えています。
漫画:戯画は漫画の起源の一つとも言われています。ストーリー性が薄く、絵を楽しむことが主目的の場合が多いです。
絵巻物:戯画は絵巻物に描かれることが多かったため、絵巻物はその表現方法の一つと言えます。絵巻物は物語を絵で表現したもので、長い形式の作品です。
伝説:戯画にはしばしば古い伝説や神話が題材として使われることがあり、閲覧者にメッセージを伝える手段として用いられます。
俗信:戯画の中には当時の俗信や迷信が描かれることも多く、庶民の生活や考え方を反映しています。
風俗:また、戯画は当時の風俗を描写することが多く、江戸時代の人々の闘争や楽しみを知る手がかりとなります。
カルチャー:戯画は、当時の日本のカルチャーや価値観を反映したもので、現代においてもその影響を受けている部分が多くあります。