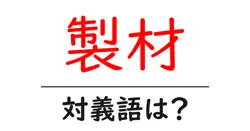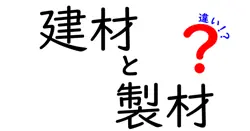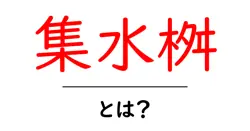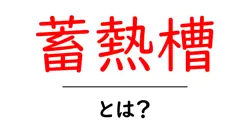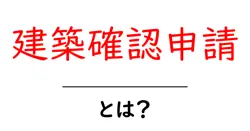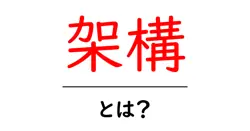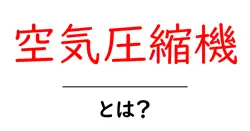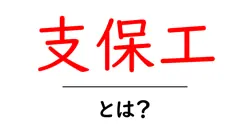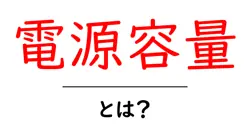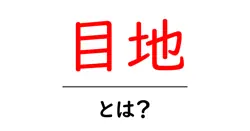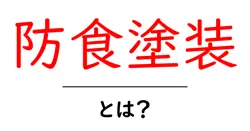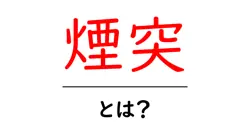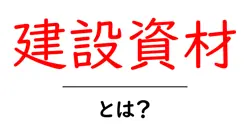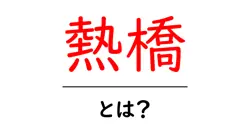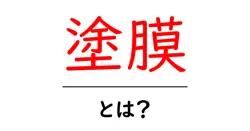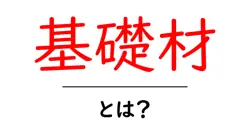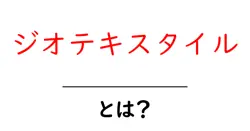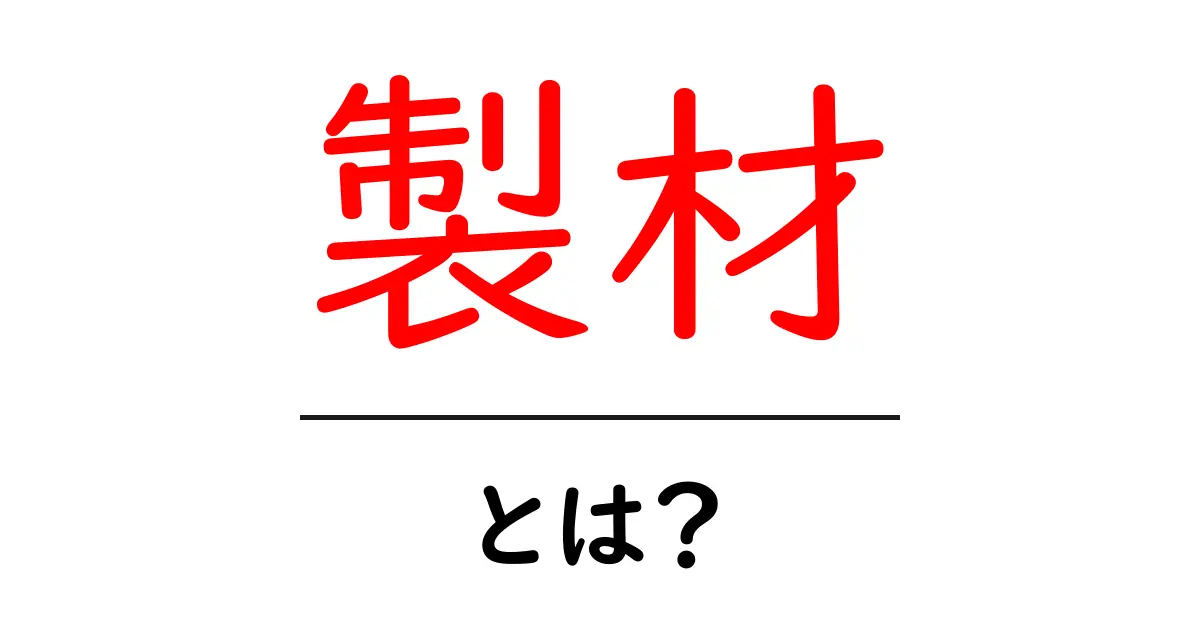
製材とは?木を使ったものづくりの基本を知ろう!
製材(せいざい)とは、木材を使って様々な製品を作るための工程のことを指します。私たちが普段目にする家具や建物は、多くの場合、製材された木材を使って作られています。製材のプロセスを理解することで、木の持つ特性や利用方法についてもっと深く学ぶことができます。
製材の主な工程
製材は、大きく分けて以下の工程に分かれます。
| 工程 | 内容 |
|---|---|
| 伐採 | 森林から木を切り出すこと。 |
| 製材 | 伐採された木を切り、形を整えること。 |
| 乾燥 | 木の水分を適切な割合に減らすこと。 |
| 加工 | 製品にするための最終的な仕上げ。 |
製材の重要性
製材は、ただ木を切り出すだけではなく、木の種類や用途に応じて適切な形に加工するための技術が求められます。そのため、製材のプロは、木材に関する知識や経験が必要です。製材された木材は、家具や建物以外にも、紙や建材、さらには燃料としても利用されています。
製材の歴史
製材の歴史は古く、古代から人類は木を使って様々な製品を作ってきました。昔は木を手作業で切っていたため、製材には時間がかかりました。しかし、技術の進化とともに、今では機械を使って効率的に製材が行えるようになりました。
未来の製材技術
近年、環境問題や資源の再利用が重要視されています。そのため、製材業界でも持続可能な森林管理や再生可能な資源の利用が求められています。未来の製材では、環境に優しい技術がますます重要になるでしょう。
製材を理解することは、木材製品の背景や、その利用がどれほど便利で重要かを知る良い手段です。日常生活や仕事で木材に関わる機会が増えている現代、製材について勉強することはとても有意義です。
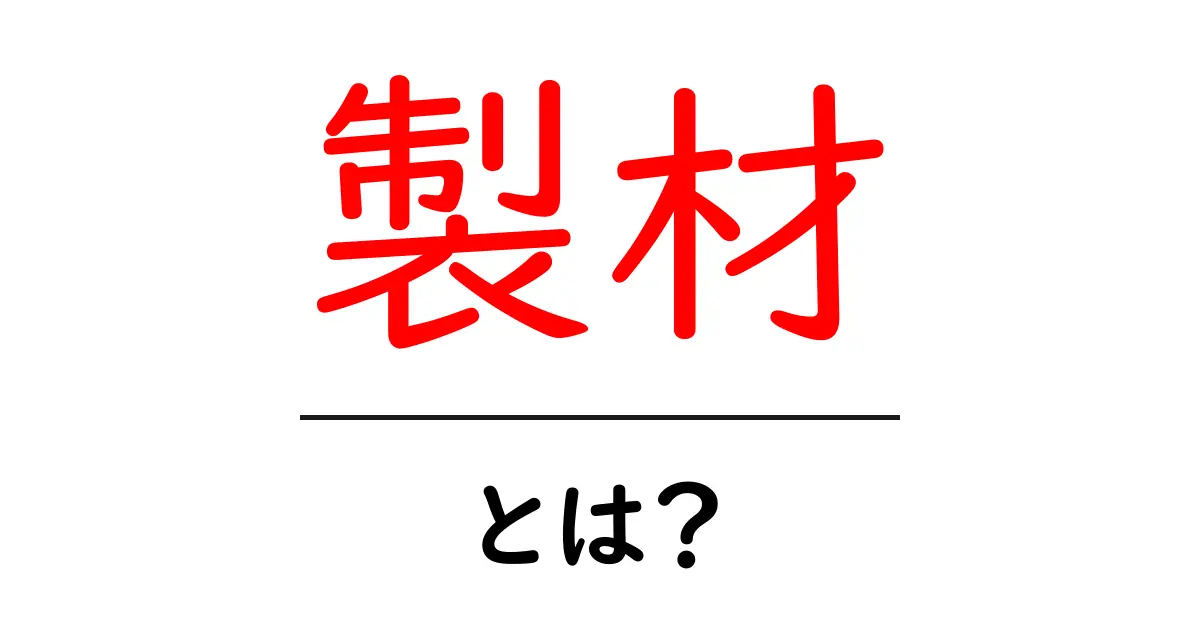
木材:製材の原材料である木のこと。これを加工して製品にすることで、家具や建材などが作られます。
加工:木材を鋸で切ったり、削ったりして形を整えるプロセス。製材では、この加工が重要な役割を果たします。
乾燥:木材から水分を取り除く工程。乾燥が不十分な木材は後に反りやひび割れが生じやすく、品質に影響します。
製品:製材を通じて作られる最終的な商品。家具や建材、パレットなど多种多様な製品があります。
丸太:製材の前の状態の木で、主に樹木を切り倒した後の幹の部分。ここから木材へと加工されます。
鋸:木材を切るための道具。製材工程では、丸太を必要な大きさに切るために用いられます。
品質:製材された木材の性質や性能を指します。適切な加工と乾燥がなければ、品質は落ちます。
市場:製材された木材や製品が流通される場所や環境。需要と供給が影響し、価格にも反映されます。
森林管理:木材の持続的な供給を確保するための、森林の育成や伐採を計画的に行うこと。製材業界にとって重要です。
設備:製材工場や作業場に必要な機械や道具のこと。効率的に製材を行うためには適切な設備が必要です。
木材加工:製材は木材を加工することを指しますが、木材加工という言葉も、木をさまざまな形に加工することを示します。
木製品製造:木を用いて製品を作ることを指します。製材の工程を経た木材は、木製品製造に使用されます。
伐採:製材の前段階として、木を切り倒すことを指します。伐採した木が最終的に製材されます。
板材:製材によって得られる平らで厚さのある木のことです。これを使って様々な製品が作られます。
木材選別:製材のプロセスにおいて、使用する木材を選ぶことを指します。質や種類によって選別が行われます。
製品化:製材された木材を使って最終的な製品を作るプロセスを示します。
木材:製材の原料となる木のこと。木材は建材や家具、工芸品などさまざまな用途に利用される。
製材所:木材を製材するための工場や施設のこと。ここで丸太を切断し、用途に応じたサイズや形状の木材に加工する。
製材業:木材を加工して製品を作る産業。主に住宅や家具の製造に携わっている。
乾燥:製材した木材の水分を取り除くプロセス。これにより、木材は強度が増し、縮みや反りを防ぐことができる。
厚板:製材された木材の一種で、比較的厚い板状のもの。建築や家具製造などで使用される。
薄葉:薄い板状の木材で、主に装飾や内装に使用される。製材の際の切り出し方によって作られる。
合板:複数の薄い木材板を接着して作った木材のこと。強度があり、様々な建築や家具に利用される。
集成材:小さな木材を接着して、大きな木材のようにしたもの。強度があり、特に建築で多く使われる。
無垢材:自然の木材をそのまま使用したもの。他の素材と接着されていないため、自然な風合いを持つ。
木目:木材の表面に現れる柄のこと。木の種類や製材の仕方によって異なる美しい模様を持つ。