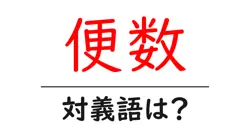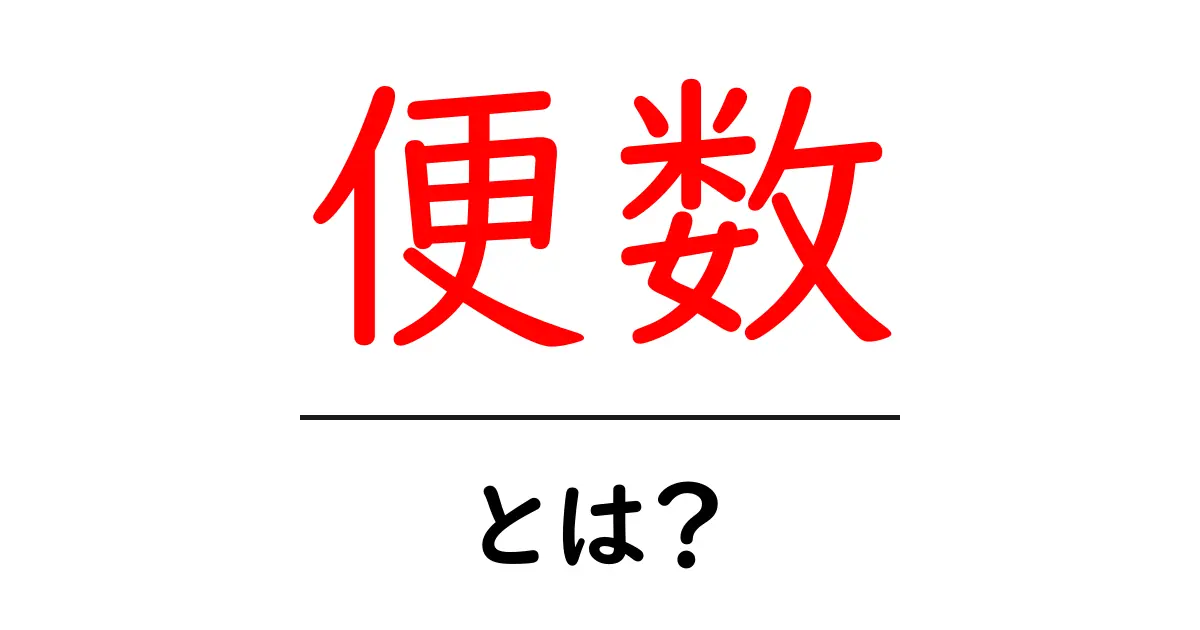
便数とは?
「便数(びんすう)」という言葉を聞いたことはありますか? この言葉は、特に交通機関においてとても重要な要素です。便数とは、特定の時間内に運行される乗り物の数を指します。つまり、例えば、ある路線バスや列車が1時間の間に何回そのルートを走るか、ということです。
なぜ便数が大切なのか?
便数が多ければ多いほど、利用者にとって便利です。例えば、通勤や通学で使うバスや電車が頻繁に運行されていると、待たずに乗れるのでとても助かります。反対に、便数が少ないと長時間待つことになり、計画が狂ってしまうこともあります。
便数の具体例
| 交通手段 | 便数(例) |
|---|---|
| 路線バス | 15分に1本(4本/時間) |
| 快速電車 | 20分に1本(3本/時間) |
| 新幹線 | 1時間に2本(2本/時間) |
上の表は、いくつかの交通手段における便数の例です。このように、便数は運行の頻度を示しており、それが利用者にどれだけ便利かを示す指標ともなります。
便数と運行ダイヤ
便数は運行ダイヤとも体型しています。ダイヤは、特定の時間に列車やバスがどのように運行されるかを示したものです。便数が多ければ、ダイヤもそれに合わせてより細かい時間設定になることが多いです。
便数の決定要因
便数は、さまざまな要因によって決まります。特に利用者の需要が大きな影響を与えます。例えば、朝の通勤時間帯には便数を増やし、昼間や夜間は少なくするという調整が行われることがよくあります。
まとめ
便数は、交通機関の利便性を示す重要な数字です。特に移動をする上で、利用者と便数との関係は切っても切れないものです。これを知っておくことで、あなたの移動計画をよりスムーズにすることができるでしょう。
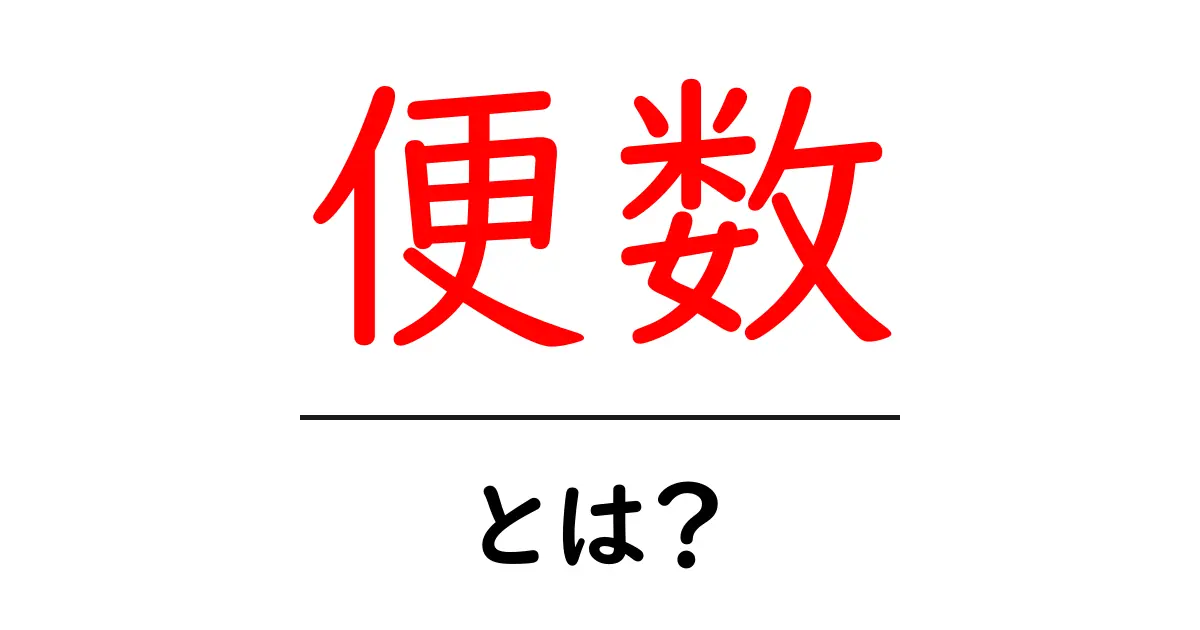
交通:移動のための手段や方法。バスや電車などの公共交通機関の利用に関連する。
ダイヤ:交通機関の運行スケジュール。便数とは、このダイヤに基づいて定められた運行の回数を指す。
本数:特定の交通機関が一定期間に運行する便の数。便数と同義で使われることが多い。
運行:交通機関が定期的に移動すること。便数はこの運行の頻度を決定づける要因である。
時刻表:交通機関の運行時刻を示した表。便数を確認するために利用されることが多い。
ピーク時間:交通機関が最も混雑する時間帯。この時間帯には便数が増えたり、特別な運行がされることがある。
需要:交通機関の利用者が必要とするサービスの量。便数はこの需要に応じて設定される。
運営:交通機関を管理・運営すること。便数は運営側の政策や方針によって決まる。
運行本数:特定の路線や時間帯における交通機関の運行回数を指します。例えば、バスや電車が1日に何回運行されるかを表します。
列車本数:鉄道において、特定の期間に運行される列車の数量を示します。例えば、朝の通勤時間帯に運行される電車の本数です。
便:特に航空機やバスなどにおいて、特定の時刻に出発する便のことを指します。便数は、出発する便の数を示します。
運行頻度:交通機関がどのくらいの間隔で運行されるかを示す用語です。便数が多いほど運行頻度は高くなります。
出発回数:特定の場所から特定の目的地に向けて出発する交通機関の回数を指します。これも便数に関連しています。
便数設定:交通機関がサービスポリシーに基づいて運行本数を決定することを指します。利用者の需要に応じて変更されることがあります。
運行本数:運行される便の本数のこと。例えば、1日に何回その路線が運行されるかを示す。
便名:特定の便を識別するための名前。通常、航空会社や鉄道会社によって与えられる。
時刻表:交通機関の運行する時間を記載した表。便数を把握するためには、この情報が重要。
ピーク時:利用者が特に多くなる時間帯。便数が増えることが一般的で、混雑することも。
定期便:特定の時間に定期的に運行される便のこと。便数が一定で、利用者にとって利用しやすい。
シャトル便:特定の区間を短時間で運行する便のこと。通常は頻繁に運行される部分が多い。
空席率:運行される便に対して、実際にどれだけの座席が埋まっているかの比率。便数の調整に影響を与える。
運航スケジュール:便がどのように運行されるかをまとめた計画。ここには便数や時間などが含まれる。
欠航:予定されていた便が運行されないこと。様々な理由で発生し、便数が実際の便数に影響を及ぼす。
増便:需要がある場合に、通常の便数よりも多くの便を運行すること。便数を増やすことでサービス向上を図る。