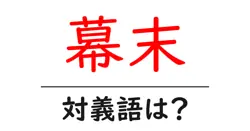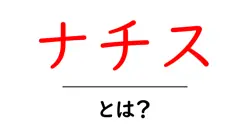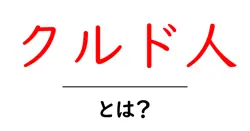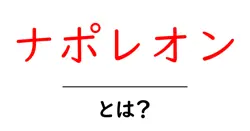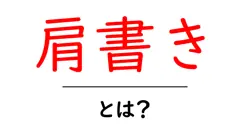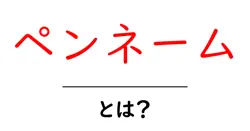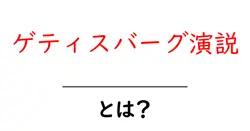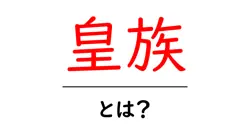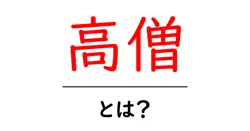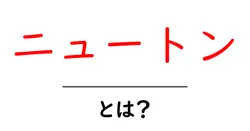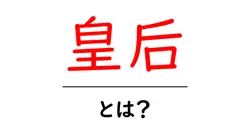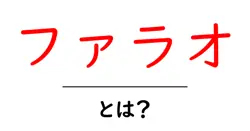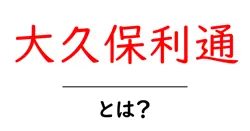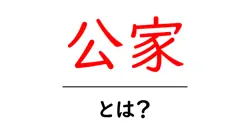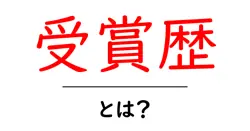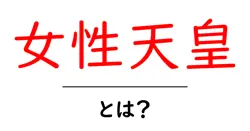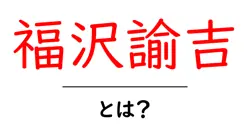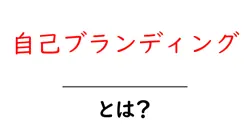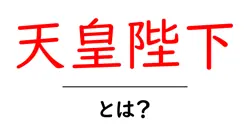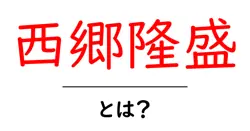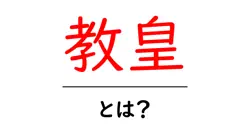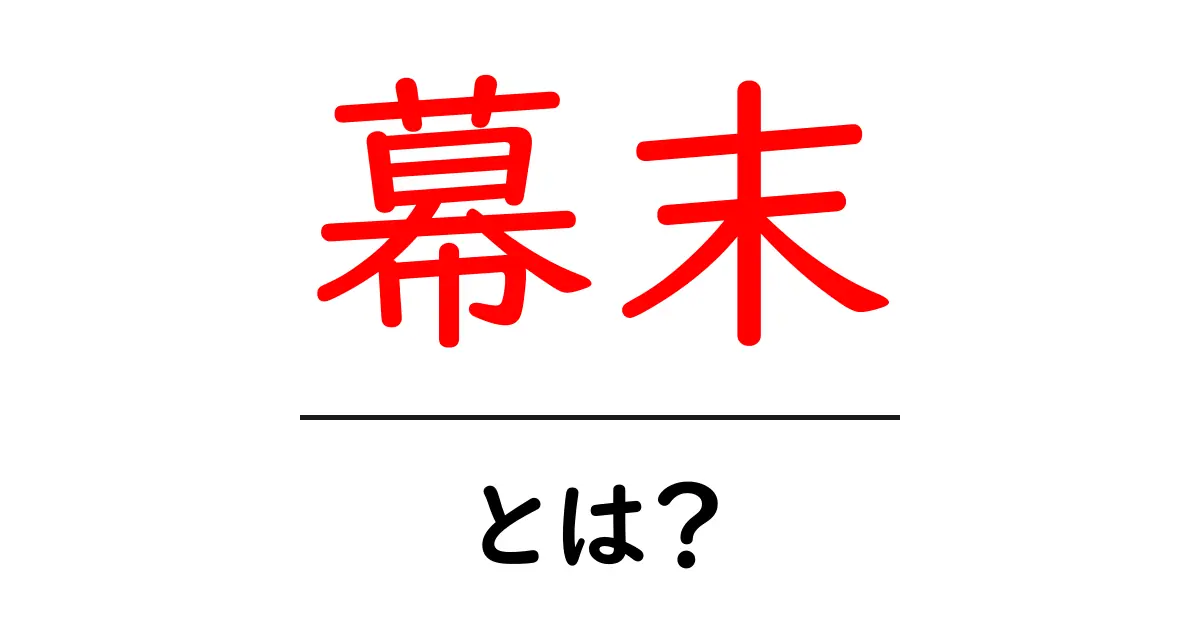
幕末とは?
「幕末(ばくまつ)」という言葉は、日本の歴史の中で非常に重要な期間を指します。幕末は一般的に、1868年に明治維新が起こるまでの約15年、つまり1853年から1868年のことを指すことが多いです。この時期は、江戸幕府が弱体化し、西洋の影響を受けながら日本が大きく変わろうとしていた時代です。
幕末の背景
幕末の背景には、江戸幕府の体制が長い間続いていたことがあります。平和な時代が続いたため、経済が発展し、商人や町人の力が強くなりました。しかし、幕府の権力は次第に弱まっていき、内部での改革が求められるようになりました。
西洋の影響
この時期の大きな出来事の一つは、1853年にアメリカのペリー提督が日本に来航したことです。ペリー艦隊は、日本に開国を求めました。これにより、閉鎖的だった日本は西洋文明と接触することになります。
幕末の重要な出来事
幕末にはさまざまな出来事がありました。代表的なものをいくつか紹介します。
| 年月 | 出来事 |
|---|---|
| 1853年 | ペリー来航 |
| 1854年 | 日米和親条約締結 |
| 1867年 | 大政奉還 |
| 1868年 | 明治維新 |
幕末の変化
幕末は、単に外国の侵略を受けるだけではなく、日本国内でも大きな変革が起きました。武士や農民、商人たちが新しい時代を切り開こうとさまざまな努力をしました。
思想の変化
また、幕末には、「尊王攘夷」と呼ばれる運動もありました。尊王攘夷運動は、天皇を尊び、外国の影響を排除しようとする動きです。この運動が幕末を通じて盛り上がり、後の明治維新につながりました。
まとめ
最後に、幕末とは日本の歴史において非常に重要な時期であることが分かります。外国との交流がもたらした影響や、それに対する日本の人々の反応は、今でも多くの学びを与えてくれます。幕末の出来事や考え方は、現在の日本にも影響を与え続けているのです。
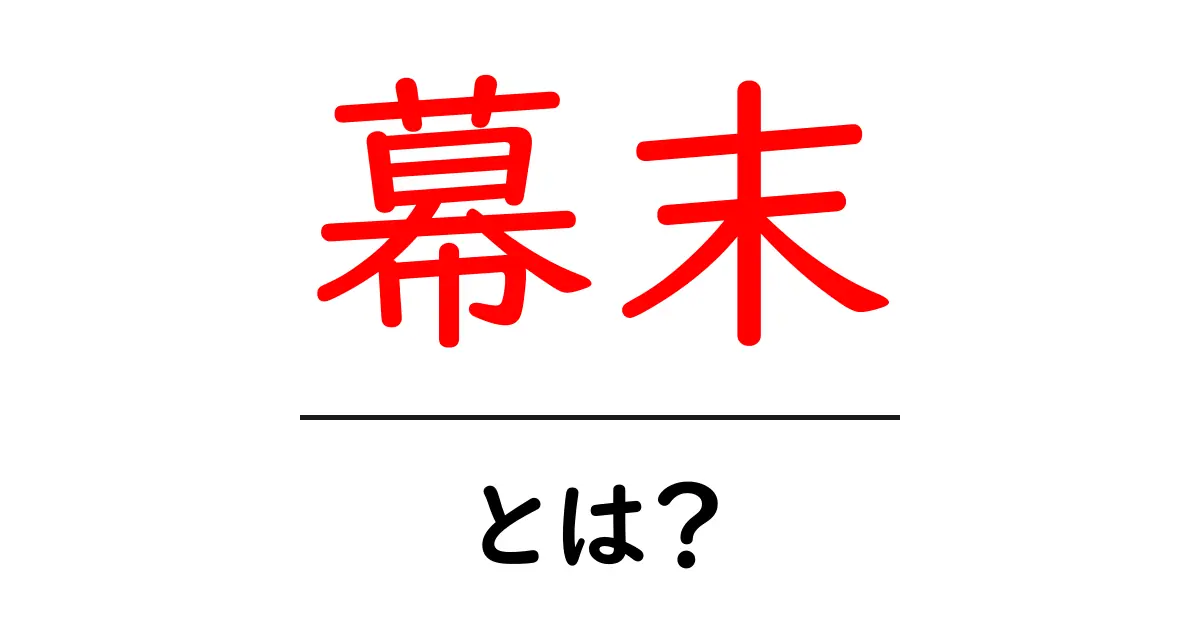
幕末 ええじゃないか とは:「ええじゃないか」は、幕末の日本で起きた大きな社会運動の一つです。この言葉は「ええじゃないか」という掛け声から来ていて、人々が集まって踊ったり叫んだりすることによって、一種の熱狂を表現していました。1867年から1868年の頃、特にこの運動が盛んになりました。人々は、社会の不満や不安を抱えていて、特に政治や経済の変化に対する恐れがありました。この運動は、そんな状況下で人々が集まって、仲間同士で励まし合うことによって、ストレスや不満を発散しようとしたのです。ええじゃないかの動きは、一種の解放感をもたらし、また、地方の村や町でも広まりました。それによって人々はお互いに連帯感を強め、日本全体での変革の動きとなりました。ええじゃないかは、単なる祭りではなく、幕末の日本が大きく変わる一つのきっかけとなったのです。
幕末 とは 意味:幕末とは、江戸時代の最後の約15年間、つまり1853年から1867年のことを指します。この時期、日本は外国との接触が増え、特にアメリカのペリー提督が来航した1868年の黒船来航が重要な出来事となりました。幕末の時代は、武士や庶民が幕府に対して反発し、新しい未来を求める動きを見せた時期でもあります。この時期、日本は大きな変革を迎えました。特に、西洋の文化や技術が流入し、国のあり方が大きく変わるきっかけとなったのです。たとえば、ペリーが来たことで、日本は鎖国政策を見直さざるを得なくなり、国際社会へと足を踏み入れることになります。また、この時期、尊王攘夷運動が盛んになり、天皇を尊重し、西洋の影響を排除しようとする動きが広がりました。最終的には、1868年に明治維新が起こり、日本は近代国家として生まれ変わりました。幕末は、日本の歴史の中で非常に重要な時代であり、未来の日本を形作る基盤となったのです。
幕末 佐幕派 とは:幕末の時代、つまり江戸時代の終わり頃に、日本は大きな変革の時期を迎えていました。その中で「佐幕派」という言葉が使われるようになりました。佐幕派は、幕府を支持し、幕府が続くことを望んでいた人たちのことを指します。つまり、江戸幕府を維持し、政治を安定させようとした勢力のことです。主要な佐幕派の人々には、幕府の大名や武士、商人などが含まれていました。彼らは、薩摩藩や長州藩のように新しい政治を求める勢力、つまり「尊王攘夷派」と呼ばれる反幕派と対立しました。尊王攘夷派は、外国の影響を排除し、天皇を中心とした新しい政治体制を作りたいと考えていました。このように、幕末の佐幕派は、日本が西洋の影響を受けて大きく変わろうとしている時期に、幕府を守ろうと奮闘した人々だったのです。彼らの活動や考え方は、後の明治維新に大きな影響を与えました。佐幕派と反幕派の戦いは、日本の歴史を語る上で非常に重要です。これを知っておくことで、幕末の時代がいかに複雑だったか、そしてどのようにして現在の日本に繋がっているのかを理解する手助けとなるでしょう。
明治維新:幕末の時代に起こった、日本の政治的な大変革を指し、江戸時代から明治時代にかけての移行を意味します。
薩摩藩:九州地方にあった藩で、幕末における重要な政治勢力の一つです。西郷隆盛や大久保利通などの指導者が活躍しました。
長州藩:山口県を中心とした藩で、幕末の志士たちが多く輩出し、明治維新に大きな影響を与えた地域です。
坂本龍馬:幕末の志士で、日本の近代化に貢献した人物として知られています。彼は薩摩藩と長州藩の連携を目指して活動しました。
新選組:幕末の京都で活躍した武士の集団で、幕府側の治安維持を目的として活動し、名を馳せました。
大政奉還:1867年に行われた、徳川慶喜が政権を天皇に返還することを決めた重要な出来事で、幕末から明治時代への転換点となりました。
池田屋事件:1864年に起こった新選組と長州藩の間の戦闘事件で、幕末の激動の一端を示す出来事として知られています。
倒幕運動:幕末の時代に、幕府を倒して新しい政治体制を作ろうとする運動を指します。主に薩長などの志士たちが中心となりました。
外国の干渉:幕末の日本において、西洋列強が日本に対して影響を及ぼそうとした事態を指し、開国に伴うさまざまな問題を引き起こしました。
横浜開港:1859年に行われた日本の主要な港の開放で、外国との貿易が始まり、幕末の日本に多大な影響を与えました。
明治維新:幕末の時代を経て、日本が近代国家へと移行する重要な出来事を指します。幕末の改革や変動が直接的なきっかけとなり、日本の政治や社会が大きく変わりました。
幕藩体制:江戸時代の日本の政治体制を指し、幕府と諸藩がそれぞれの権力を持ちながら共存していました。この体制が崩れることが幕末の背景となります。
戊辰戦争:1868年から1869年にかけて行われた内戦で、幕末の動乱の象徴的な事件です。新政府軍と旧幕府軍が対立し、新しい日本の基礎が築かれました。
開国:幕末において、日本が外国と通商を始めることを指します。特に1854年のペリー来航によって外交が始まり、西洋の影響を受けるようになりました。
倒幕:幕末の時代において、江戸幕府を倒すことを目指す運動や運命を指します。多くの志士たちがこの目標に向かって活動しました。
尊王攘夷:幕末の政治運動の一つで、天皇を尊重し、西洋勢力を排除しようとする考え方です。この思想は多くの志士に影響を与えました。
明治維新:幕末から明治の初めにかけて、日本の政治体制が大きく変わった出来事で、天皇を中心とした新政府が誕生しました。
攘夷:外国勢力を排除し、日本の主権を守ることを目指す運動で、幕末の動乱の中で重要な思想の一つとなりました。
尊王:天皇を崇め、天皇制の強化を目指す思想で、幕末の尊王攘夷運動に影響を与えました。
薩摩藩:幕末の動乱期において、明治維新を主導した藩の一つで、現代の鹿児島県にあたります。
長州藩:薩摩藩と並んで明治維新を推進した藩で、現在の山口県を中心にありました。
坂本龍馬:幕末の志士で、薩摩藩と長州藩の連携を図るなど、明治維新の立役者の一人です。
西郷隆盛:薩摩藩の武士で、明治維新の指導者として活躍し、後に西南戦争の指導者となります。
大政奉還:1867年に徳川慶喜が政権を天皇に返上した事件で、幕末の政治的転換点となりました。
戊辰戦争:1868年から1869年にかけて、明治新政府と旧幕府勢力との間で戦われた内戦です。
開国:幕末に外国との交易を再開することを指し、特に1854年のペリー来航が転機となりました。
倒幕:江戸幕府を倒そうとする運動を指し、幕末の志士たちが推進しました。
新選組:幕末期に活動した武士集団で、幕府の側で反乱者を取り締まる役割を果たしました。