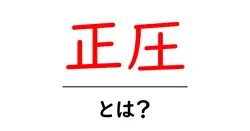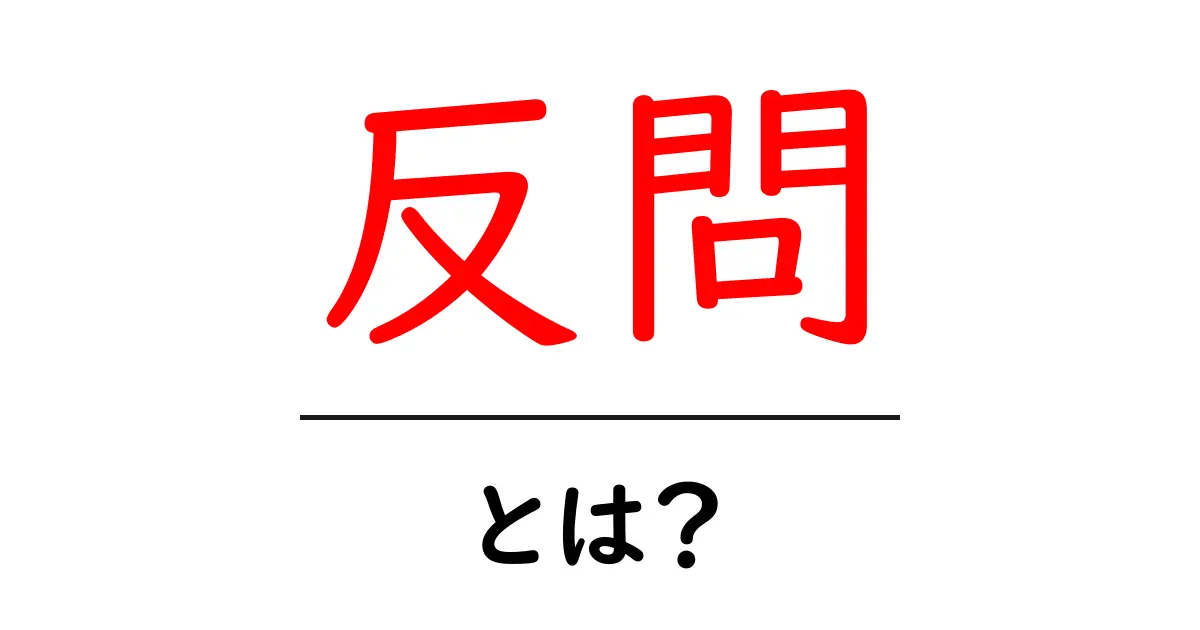
反問とは何か?
「反問」という言葉を聞いたことがありますか?これは、ある問いに対して逆に質問を返すことを指します。例えば、友達が「お菓子食べる?」と聞いたときに、「お菓子食べないの?」と返す場合が反問です。このように、相手の発言に対して疑問を持って反応することが「反問」と言えます。
反問の特徴
反問にはいくつかの特徴があります。
- 相手の発言に興味を持たせる
- 会話を活発にする
- 自分の意見を示すことができる
たとえば、学校の授業で先生が「こんな問題、みんな解ける?」と聞いた時に、学生が「解けなくていいの?」と返すことは反問になります。これによって、会話が弾みやすくなるのです。
反問の使い方
反問は様々な場面で使われます。ここではいくつかの例を見てみましょう。次の表は、archives/17003">一般的な会話の中での反問の例とその意図を示しています。
| シチュエーション | 元の質問 | 反問の例 | 意図 |
|---|---|---|---|
| 友達との会話 | 今日遊びに行く? | 行かないの? | 友達が遊びたくないのか確認 |
| 学校の授業 | 宿題できた? | 宿題しなくても大丈夫? | 宿題の重要性を再確認 |
反問の注意点
反問を使うときには、相手の気持ちや状況を考えることが大切です。たとえば、誰かが悩んでいる時に反問をすることで、逆に相手を傷つけてしまうこともあるかもしれません。ですので、相手の感情に配慮した使い方を心掛けましょう。
要するに、反問はコミュニケーションを豊かにするための道具の一つです。ぜひ覚えて、使ってみてください!
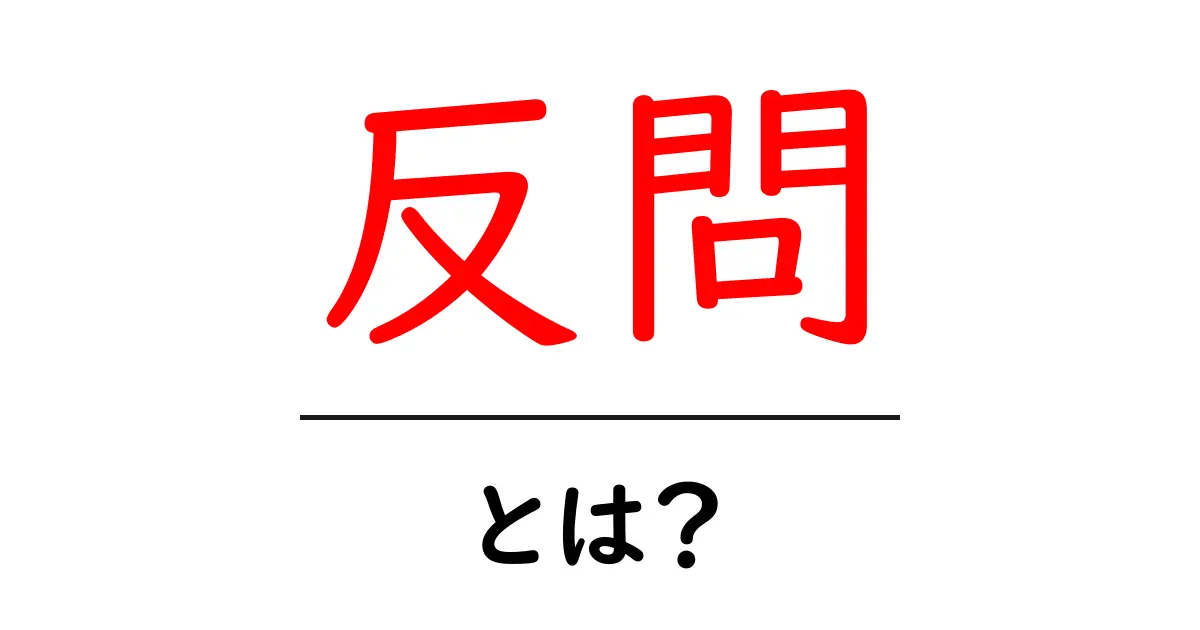 archives/9451">併せて解説!">
archives/9451">併せて解説!">疑問:何かに対して確信が持てなかったり、理解できなかったりする様子。反問の際には相手の意見や主張に対する疑問を提示することが多い。
逆質問:質問に対して、さらにそれに関連する質問を返すこと。反問はこの逆質問の一種で、相手の見解をさらに掘り下げる目的で行われる。
否定:何かを認めないこと。反問は時に、相手の意見や主張を否定する形で行われることがある。
省察:自分の考えや行動を振り返ること。反問は、自らの立場や思考を深く見つめなおすきっかけになることがある。
対話:二人以上の人間が意見や考えを交わすこと。反問は対話の重要な要素であり、互いに理解を深める手段となる。
論点:議論や討論の中心となるテーマや問題。反問を通じて、新たな論点が浮かび上がることが多い。
説得:相手に自分の意見を納得させること。反問は相手を説得するための手段として用いられる場合がある。
反体制:既存の考え方や支配的な意見に対抗する姿勢。反問は、こうした反体制的なスタンスを取る一環として行われることもある。
信念:強く信じている考えや価値観。反問は、自分の信念に基づいて他者の意見を問い直す場合が多い。
意見交換:archives/2481">異なる意見を持つ者同士で意見を交わすこと。反問は意見交換の中で生じやすい。
逆説:ある事柄が他の事柄と矛盾するように見えるが、実際にはそれが真実であることを示す表現。
疑問:何かを問いかける時に使われる表現。相手の意見や行動に対して疑いを持っていることを示す言葉。
反論:ある主張に対して逆の立場から意見を述べること。反問を行うことが、反論に該当する場合がある。
問い返し:相手の発言や意見を受けて、再び問いかける行為。または、その時に使用される表現。
自問自答:自分自身に問いかけ、それに対する答えを自分で考えること。反問的な問いを含むことが多い。
逆説:archives/17003">一般的に考えられることとは逆の事柄を述べることで、反対のことを示す表現方法。反問の一部として使われることが多い。
質問:情報を得るために何かを尋ねる行為。反問はその質問の形式の一種であり、相手に考えを促すための手法でもある。
意義:ある事柄が持つ意味や重要性。反問を用いることで、意義を再確認したり、それに対する考えを促すことができる。
同意:何かに賛成すること。反問は相手の意見を確認したり、同意を求めるための有効な手段となる。
挑発:ある人の反応を引き出すために促すこと。反問は相手を挑発することで、深い議論を生むことがある。
論理:物事を考えたり、説明したりする際の筋道や基準。反問は論理的に考えさせる手法であり、理路整然とした議論を促進する。
答弁:質問に対して答えること。反問を通じて、相手に自分の意見を見直させたり、より深い答弁を引き出すことができる。
証明:ある事柄が真実であることを示す証拠や理由。反問はしばしば、意見や主張を証明するための道筋を提供する。