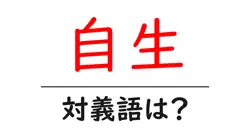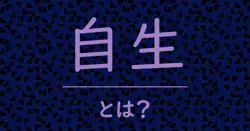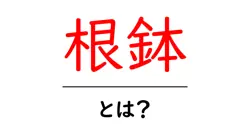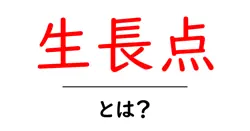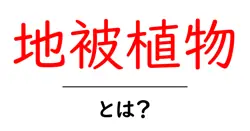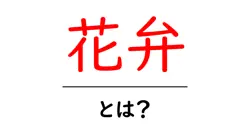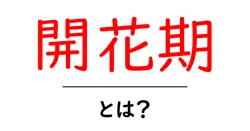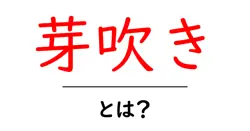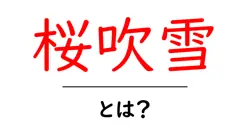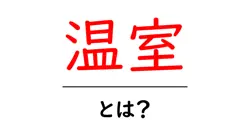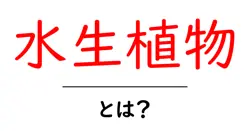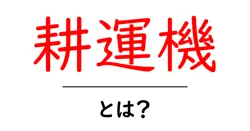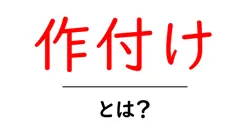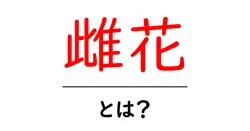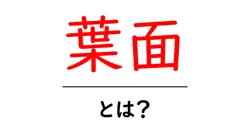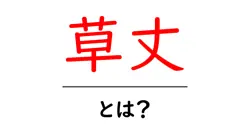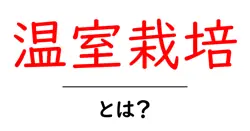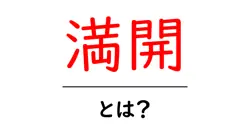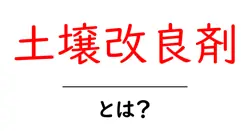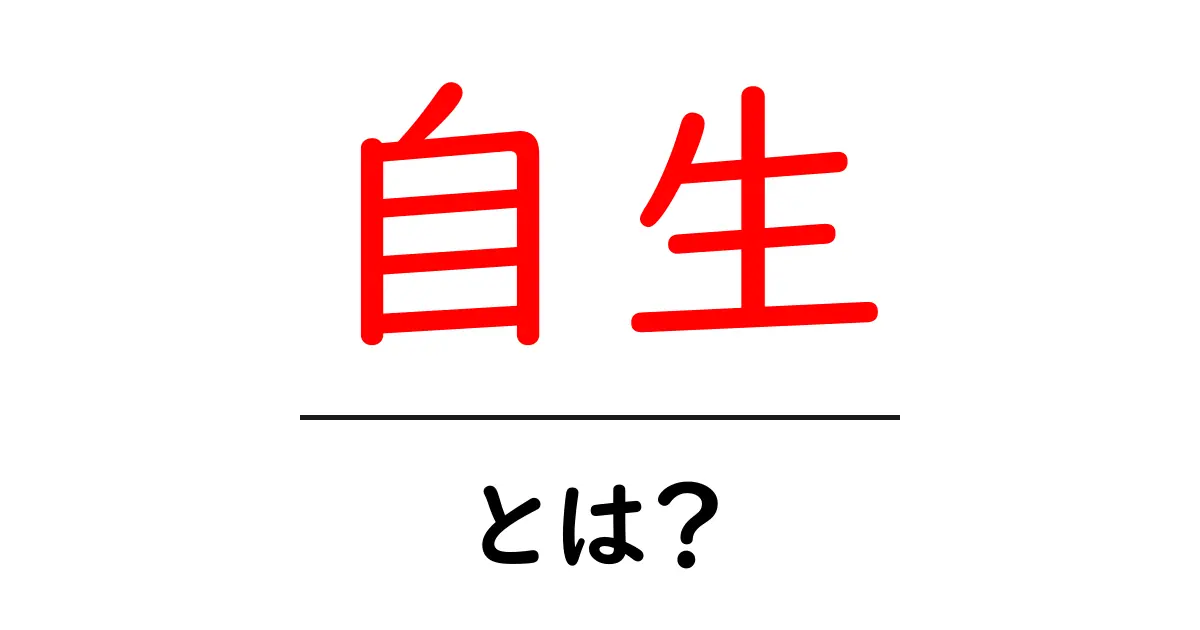
自生とは?
自生という言葉は、自然の中で育つことを意味します。特に植物に関して使われることが多いですが、動物や他の生物にも当てはまります。自生する植物は、人間が手を加えずに自然の環境で成長します。このような植物はその土地に適した条件で育っているため、強い生命力を持っています。
自生する植物の特徴
自生する植物は、その地域の気候や土壌の条件に適応しながら生息しています。以下は、一般的な特徴です。
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 適応力 | それぞれの環境に合わせた生育ができる。 |
| 競争力 | 他の植物と生息空間を争うことができる。 |
| 再生力 | 環境が厳しくても生き延びる力が強い。 |
| 繁殖力 | 自然に種を散布して増える。 |
自生植物の例
日本の自生植物には、ススキやシダ、ツツジなどがあります。これらの植物は日本の気候や地形にぴったりと合っています。自生植物はその地域の生態系を支える重要な役割を果たしています。
自生と人間の関わり
人間は森林や草原を開発することで、自生植物の生息地を減らしてしまうことがあります。しかし、最近では自生植物を保護する動きが広がっています。
例えば、国立公園や保護地域が設けられ、自生植物の保護や再生が行われています。このように、人間は自生植物との共生を考える必要があります。
まとめ
自生は自然に育つ植物や生物を指し、その生物たちは環境に適応して強い生命力を持っています。自生植物を理解し、保護することで、より良い未来を築くことができるのです。
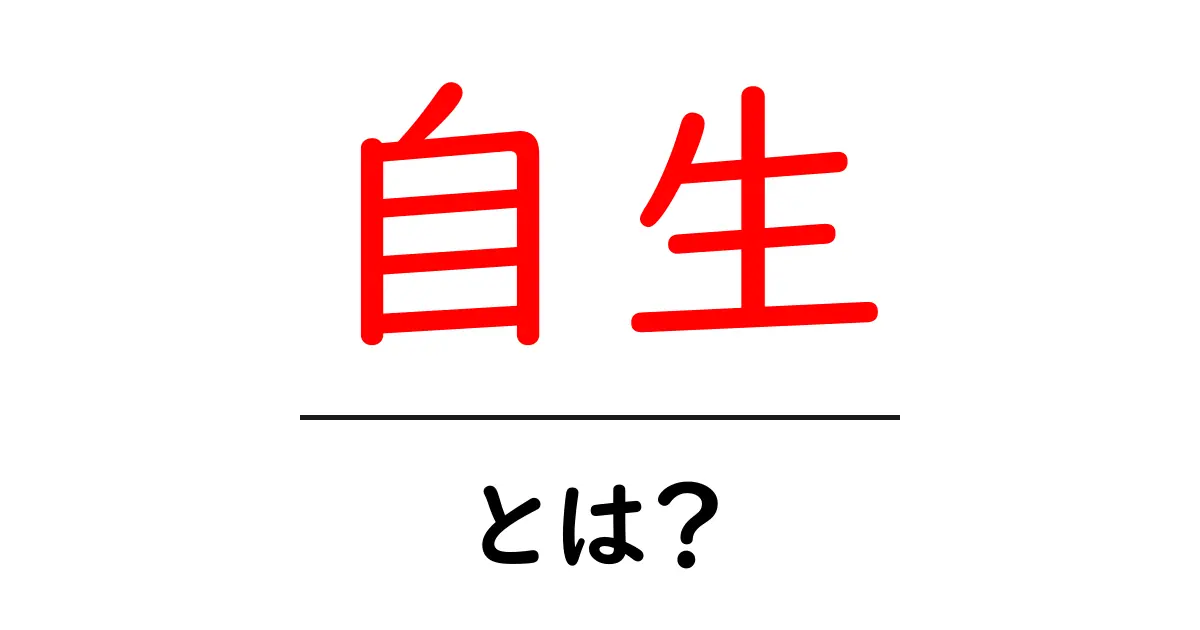
植物:自生は主に植物が自然環境に適応して生育することを指します。特定の地域に自然に存在する植物を指すことが多いです。
動物:自生は植物だけでなく動物にも関連します。特定の生息環境で自然に繁殖・生活する動物を指します。
生態系:自生は生態系の一部であり、さまざまな生物が相互作用し、環境に適応しながら共存する状態を示します。
固有種:自生する植物や動物の中には、その特定の地域にしか存在しない固有種があり、それらは地域の生態系の重要な構成要素です。
環境保護:自生する生物を守るためには、その生息環境を保護することが重要です。環境保護活動は自生種の保存に寄与します。
外来種:自生種とは対照的に、外来種は他の地域から持ち込まれた生物で、自生する生態系に影響を与えることがあります。
自然:自生は自然環境の一部として考えられ、人工的な介入なしで発展する生物の成長過程を指します。
生息地:自生する生物は特定の生息地に依存します。生息地はそれぞれの種が生きるために必要な条件を提供します。
自発:自ら進んで行動すること。環境により自然に生じることを指します。
自然発生:外部からの影響を受けずに、自然に生じること。特に生物や物質が自らの力で生まれる様子を表します。
天然:人為的な手を加えず、自然の状態にあること。自然界でそのまま存在するものを指します。
原生:元々の姿や状態に近いこと。人間の手が加わることなく存在する物を指すこともあります。
非人工的:人間の介入がない状態や、自然に形成されたものを指します。
植物:自生は特に植物が自らの力で自然の中で育つことを指します。人間の手を借りずに、固有の環境で生きている植物のことです。
環境:自生する生物は、その地域の気候や土壌、他の生物といった環境条件に適応して生きています。この環境の影響が自生の成功に重要な要素となります。
生態系:自生する植物は生態系の一部を形成しており、動物や微生物との関係によって栄養の循環やエネルギーの流れが保たれています。
固有種:特定の地域にのみ自生する植物を指します。これらの固有種は、その地域の生態系に特有の役割を果たしており、保護が必要です。
外来種:自生とは対照的に、外来の環境から持ち込まれた植物種のことです。外来種は自生の環境に影響を与えることがあり、生態系のバランスに問題を引き起こすこともあります。
適応:自生植物は環境に適応して進化します。これにより、劣悪な条件でも生き延びることができるようになります。
生存競争:自生する植物がお互いに生存するために、資源(光、栄養、水など)を巡って競い合うことを指します。これが種の多様性を生む要因となります。
保護:自生する植物やその生息地を保護することは、生物多様性の維持や生態系の安定に不可欠です。持続可能な方法で自然環境を守ることが求められています。