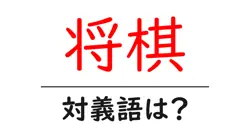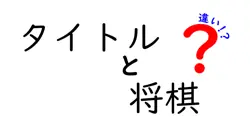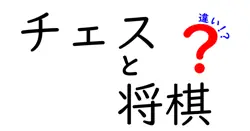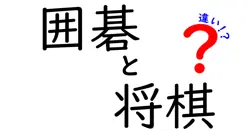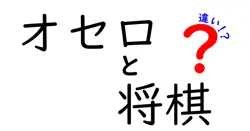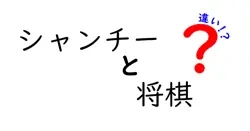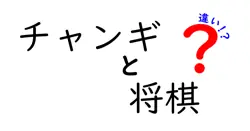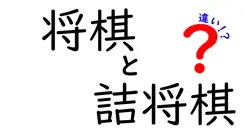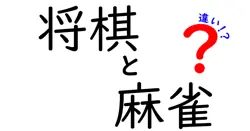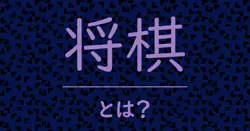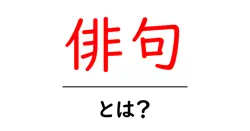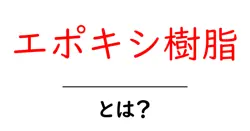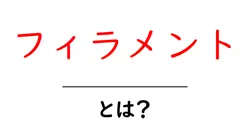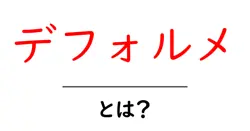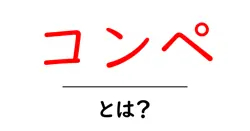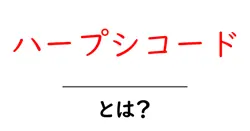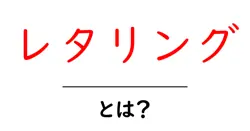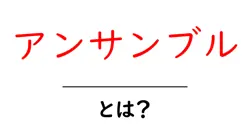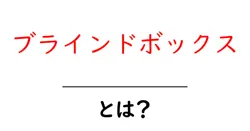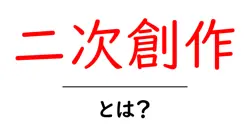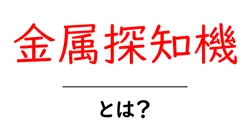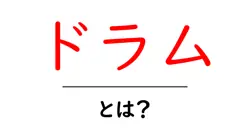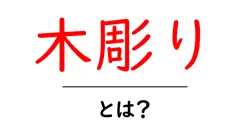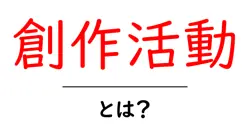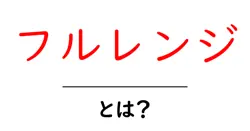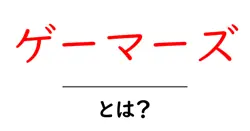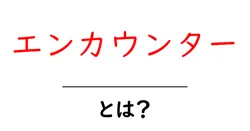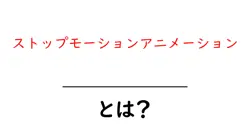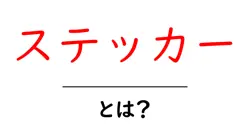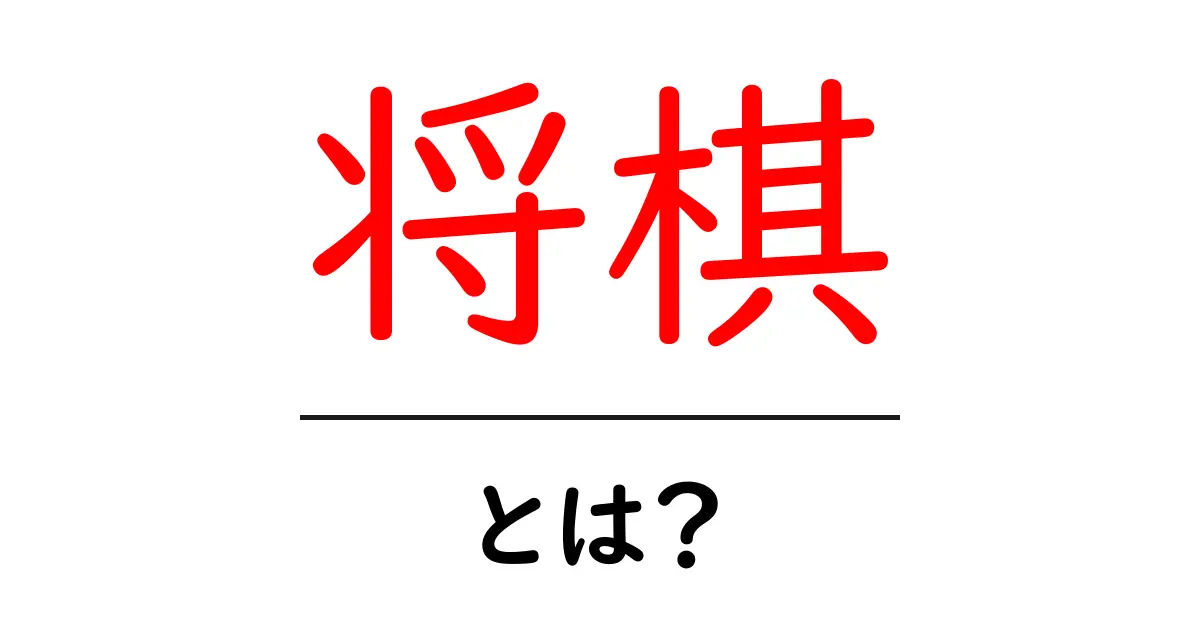
将棋とは?基本的なルールと魅力
将棋(しょうぎ)は、日本の伝統的なボードゲームで、2人が対戦しながら戦略を駆使して勝利を目指します。将棋は、非常に奥深いゲームであり、考える力や判断力を養うのにピッタリな遊びです。
将棋の基本ルール
将棋は、81マスの盤面と32個の駒を用いて行われます。各プレイヤーは、持ち駒を用いて相手の王将を取ることを目的としています。以下は、将棋の基本的なルールについての表です。
| 駒の名前 | 動き方 | 特別なルール |
|---|---|---|
| 王将(おうしょう) | 1マスどちらの方向にも動ける | 取られると負け |
| 飛車(ひしゃ) | 縦・横に何マスでも動ける | 成ることができる(竜に変身) |
| 角行(かくぎょう) | 斜めに何マスでも動ける | 成ることができる(龍に変身) |
| 金将(きんしょう) | 1マスの前・横・後ろに動ける | 成ることはできない |
| 銀将(ぎんしょう) | 1マスの前・斜めに動ける | 成ることができる(成銀に変身) |
| 桂馬(けいま) | 前方の2マス先の斜めに飛び越える | 成ることができる(成桂に変身) |
| 香車(きょうしゃ) | 前方に何マスでも動ける | 成ることができる(成香に変身) |
| 歩兵(ふひょう) | 前方に1マス動ける | 成ることができる(と金に変身) |
将棋の魅力
将棋の魅力は、その戦略性にあります。一手一手が勝敗に大きく影響するため、考える力が試されます。また、将棋は一局ごとに異なる展開があり、同じ対局は二度とありません。これがプレイヤーを飽きさせず、何度でも挑戦したくなる理由です。
将棋の楽しみ方
将棋を楽しむためには、実際に対局してみることが一番です。初心者向けのオンライン対局サイトやアプリも多くありますので、気軽に始めてみましょう。また、棋士たちの対局を観戦することも、将棋の力を伸ばす良い方法です。
まとめ
将棋は単なるゲームではなく、深い戦略や判断力を養うことができる素晴らしい遊びです。是非、一度挑戦してみてください!
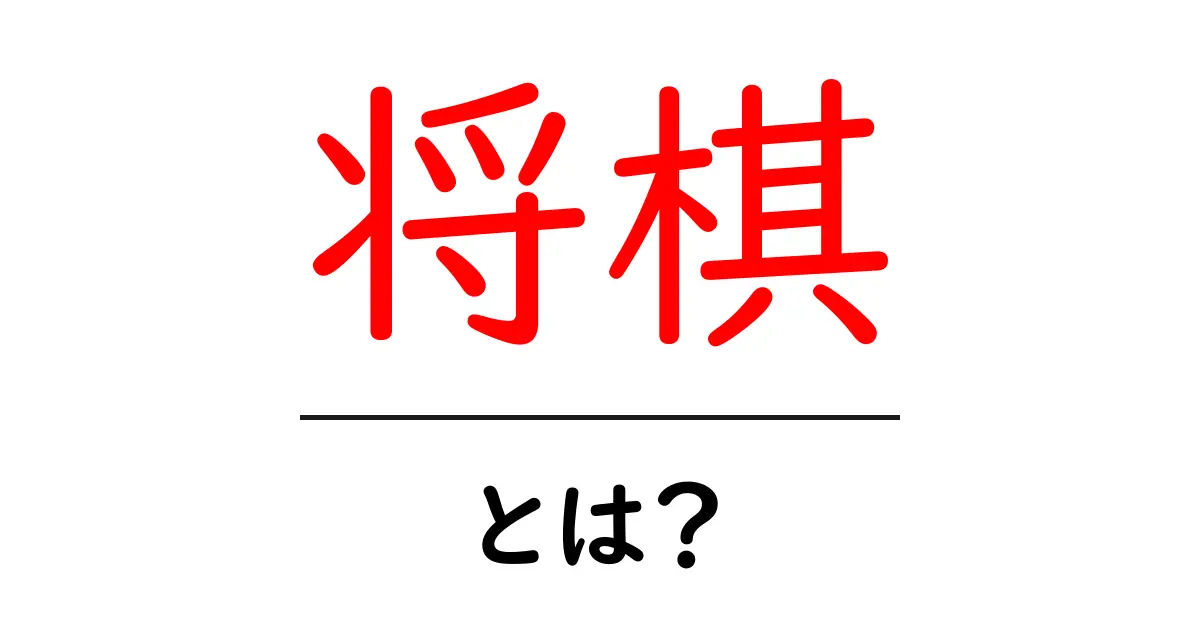
力戦 将棋 とは:力戦将棋とは、将棋の戦い方の一つで、主に攻撃的な形を重視したスタイルのことを指します。通常の将棋では、守りを重視したり、相手の動きを慎重に観察しながら進めたりすることが多いですが、力戦将棋では自ら積極的に攻めることが求められます。このスタイルは、特に初心者や中級者にとって分かりやすく、楽しく将棋を学ぶきっかけになります。力戦将棋を好む棋士たちは、力強い駒の動かし方や、攻めのタイミングを重視しており、観客を引きつける熱い戦いを展開します。例えば、桂馬や銀などを使って、相手の陣地に素早く侵入し、攻撃を仕掛けることが代表的です。このように、力戦将棋は、勇ましい攻め合いが繰り広げられるため、多くのファンに愛されています。将棋を始めたばかりの人は、まずこの動きや流れを体験してみるといいでしょう。理解しやすい戦略を学ぶことができ、将棋の楽しさを感じられるはずです。力戦将棋を通して、友達と対戦しながら楽しく上達していきましょう。
封じ手 将棋 とは:将棋の封じ手という言葉を聞いたことがありますか?封じ手は、対局中に一時停止することを指します。特に、長時間対局が続く場合に、選手が次の手を考えるための時間を設けるために行われます。将棋の対局は非常に集中力を必要とするため、休憩を入れることで選手の疲労を軽減し、より良い思考を促す狙いがあります。封じ手を行うタイミングは、一般的には持ち時間が残り少なくなったときです。これにより、選手は自分の次の手を考え直し、戦略を見直すことができます。また、封じ手を行うことで、観客もその瞬間を楽しむことができ、後日再開される際の緊張感を高めることができます。将棋の魅力は、ただの勝ち負けだけではなく、こうした駆け引きや思考の過程にもあるのです。
将棋 とは どんなゲーム:将棋(しょうぎ)は、日本の伝統的なボードゲームで、二人のプレイヤーが対戦します。将棋盤と呼ばれる9×9のマスがあるボードを使い、お互いに持ち駒と呼ばれる将棋の駒を使って戦います。各駒には異なる動き方があり、たとえば、「歩兵」は前に1マス進むことができ、また「角行」は斜めに移動できます。プレイヤーは相手の「王将」を取ることを目指します。王将が取られると、試合は終了です。このゲームの魅力は、戦略を練ることや相手の動きを読むことにあります。初心者でも、ルールを覚えていくうちに自分なりの戦法を考えて楽しめるようになります。また、将棋は歴史的にも深い背景があり、日本文化の一部としても親しまれています。最近では、AIを使った将棋ソフトも登場し、さらに多くの人が興味を持つようになっています。友達や家族と一緒に楽しめるので、ぜひ挑戦してみてください!
将棋 とは何か:将棋(しょうぎ)とは、日本の伝統的なボードゲームの一つで、二人のプレイヤーが対戦します。将棋は将軍の戦いを模したもので、縦9マス、横9マスのボード上で行われます。各プレイヤーは20枚の駒を持ち、駒の動きにはそれぞれルールがあります。例えば、王様は1マスだけ動けますが、飛車は縦横に何マスでも動けるなど、駒によって違いがあります。将棋の目的は、相手の「王」を捕まえることです。将棋の魅力は、戦略を考える楽しさや、駒の動きによって状況が変わるダイナミックさにあります。初心者でも、基本的なルールを理解すればすぐに楽しむことができます。近年、将棋は奨励会やプロリーグが盛り上がり、多くの人々に親しまれています。また、将棋ソフトの進化により、対戦相手としても楽しめるようになっています。将棋を通じて、頭を使う楽しさや、友達とのコミュニケーションも楽しむことができます。これから将棋を始めてみると、新しい世界が広がるかもしれません!
将棋 八冠 とは:将棋は日本の伝統的なボードゲームで、多くの人々に親しまれています。その中でも「八冠」とは、将棋界の最高のタイトルを意味します。将棋にはいくつかの主要なタイトルがあり、これらのタイトルをすべて獲得することを「八冠制覇」と呼びます。具体的には、名人、竜王、棋聖、王将、王座、棋王、女流名人、女流棋士など、合計8つのタイトルがあります。 一般的に、将棋界のトップに君臨する棋士が八冠を達成することは非常に難しく、多くの対局者が挑戦する中で、実績を積み重ねた者だけがこの偉業を成し遂げることができます。八冠に到達する棋士は、実力もさることながら、安定した精神力や戦略眼が求められます。そのため、将棋界の八冠という言葉は、棋士たちの努力と才能の象徴とされています。将棋を学んでいる方や興味を持った方は、八冠の棋士たちから多くのことを学ぶことができるでしょう。
将棋 成る とは:将棋をプレイする上で、重要なルールの一つに「成る」があります。この言葉は、特定の駒が相手陣の格子(升目)に入ったときに、その駒の能力が変わることを指します。例えば、歩兵(ふひょう)が敵陣に入ると「と金(ときん)」という特別な駒に成ります。これにより、歩兵は前進だけでなく後ろや横にも動けるようになります。成ることによって駒の役割が変わるため、戦略的に非常に重要な要素となります。成り方には、駒が動ける場所に到達することが条件で、成った時点で駒の能力が向上します。初心者の方も、成ることでゲームの展開が大きく変わることを理解すると、将棋の魅力がさらに増します。ぜひ、実際の対局でも積極的に駒を成らせて、自分の戦略に活かしてみてください。成ることで対局がよりスリリングで面白くなることでしょう。
永世 将棋 とは:永世将棋(えいせいしょうぎ)とは、将棋界で非常に名誉のある称号の一つです。将棋は日本の伝統的なボードゲームで、多くの人々に愛されています。将棋には、プロ棋士と呼ばれるトッププレイヤーがいて、その中でも特に優れた成績を収めた棋士に与えられる称号が「永世」と呼ばれるものです。たとえば、「永世名人」や「永世王将」といった称号があります。これらは、特定のタイトル戦での勝利を重ねることで得られるもので、棋士にとって栄光の象徴です。この称号は、一度取得すると一生涯有効であり、その棋士の名をずっと残すことになります。将棋ファンや棋士からの敬意を集めるこの称号を持つ棋士は、将棋界のトップに君臨し、一般のファンからも特別な存在として認識されます。将棋に興味がある方は、ぜひ永世将棋について知識を深めて、この美しいゲームの魅力をさらに楽しんでください。
疑問手 将棋 とは:将棋の世界には「疑問手」という考え方があります。疑問手とは、特定の局面において、なぜその手を指したのか不思議に思えるような手のことを指します。例えば、相手の王を攻めるチャンスがあるのに、あえて守りに入るような手を指すとき、周囲の人々は「それはなぜ?」と疑問を持つわけです。疑問手が生まれる理由はいくつかあります。一つは、初心者が戦略をまだ十分に理解していないためです。将棋では、相手の動きや盤面の状況を考慮しながら最善の手を考えなくてはなりません。それが難しいために、一見奇妙に見える手が指されてしまうのです。また、疑問手は熟練者でも目にすることがあります。その場合、実は局面を打開するための隠れた意図があったり、相手に誤解を与えるための策略だったりします。このように、疑問手は単に「悪い手」というわけではなく、戦略の一部になることもあるのです。だからこそ、将棋をより深く理解するためには、疑問手をどう考えるかも重要なポイントとなります。初心者は、この疑問手を通して将棋の面白さや奥深さを感じることができるでしょう。
雁木 将棋 とは:雁木将棋とは、将棋の一つの指し方で、特に対局の際に防御を重視する戦略です。この手法は、相手の攻撃をしっかりと防ぎながら、自分の持ち駒を効果的に使っていくことが特徴です。雁木とは、元々は「雁」のように一列に整然と並ぶことを指します。この指し方では、自分の駒を縦に並べて相手の攻撃を抑え、強固な壁を作ります。雁木は特にミスが少なく、安定した局面を作りやすいので、初心者にとっても利用しやすいです。また、雁木を使う際には、駒の配置やその後の攻撃方法をしっかりと考える必要があります。特に相手からの反撃に備えて、柔軟に戦略を変えることも求められます。将棋はじっくり考えるゲームですから、まずは雁木将棋から入門してみると良いでしょう。基本をしっかりと学んで、少しずつ自分のスタイルを見つけていくことが大切です。
対局:将棋をすること。二人が将棋の駒を使って勝敗を競う行為を指します。
駒:将棋の盤上で動かす pieces、具体的には王、玉、飛車、角行、金、銀、桂馬、香車、歩などの構成要素です。
棋士:将棋をプロフェッショナルとして行う人。日本将棋連盟に所属する者が多く、公式の試合で競います。
戦法:特定の戦い方や駒の動かし方を意味します。たとえば、居飛車や振り飛車といった戦略のことです。
詰将棋:特定の局面で、相手の王様を詰ませるための問題を解くパズルのこと。将棋の実力を向上させるために役立ちます。
オープニング:対局の開始時における最初の数手。オープニングをマスターすることで、対局の流れを有利に進めることが可能です。
終盤:将棋の局面の中で、局面が大詰めとなる終わりの段階。ここでの判断力や計算力が勝敗を左右します。
棋譜:対局の進行を記録したもの。駒の動きや対局の流れを後で見返すために重要で、学習にも役立ちます。
チェス:将棋と同様に、戦略を駆使して相手の王を取るボードゲーム。一般的に西洋で広く遊ばれている。
囲碁:将棋とは異なり、碁石を使って陣地を囲むゲーム。戦略を考えながら相手を圧倒する点で似た要素がある。
ボードゲーム:将棋はボードゲームの一種であり、一般的には盤上で行われるルールに基づくゲーム全般を指す。
オセロ:盤上で黒と白の石を使って相手の石を挟み込むことで自分の色に変えて陣地を拡大するゲーム。戦略性が求められる点が将棋と共通している。
将棋盤:将棋をプレイするための専用のボード。将棋に対する具体的な用語だが、将棋自体を指す場合もあり、重要な関連性を持つ。
駒:将棋で使用される駒のことを指します。各駒には異なる動きがあり、指し手によって勝敗が決まります。
王将:将棋の最も重要な駒で、相手の王将を詰ますことがゲームの目的です。王将が取られると負けとなります。
詰将棋:特定の条件下で王を詰ます手筋を解くための問題のことです。将棋の腕を磨くために有効です。
定跡:将棋における過去の棋譜(対局の記録)から得られた、効果的な戦術や手筋のことを指します。定跡を学ぶことで、序盤の戦略が立てやすくなります。
持ち時間:対局中にプレイヤーが思考に使える時間のことです。持ち時間が尽きると、そのプレイヤーは敗北します。
棋譜:対局のすべての手順を記録したものです。棋譜を見返すことで、自分の対局を振り返ったり、他のプレイヤーの戦術を学んだりすることができます。
叩く:相手の駒を取ることを意味する用語です。将棋では、駒を取ることが戦略上非常に重要です。
成り:特定の条件を満たすことで駒が強化されることを指します。例えば、相手の陣地に入ると特定の駒は「成る」ことができ、強力な駒として扱われます。
持ち駒:相手から取った駒を、自分の手駒として使用できる状態のことです。持ち駒を使うことで、戦略の幅が広がります。
横歩取り:将棋の定跡の一つで、相手の横にある歩を取る戦法です。序盤の戦い方として多く使われます。