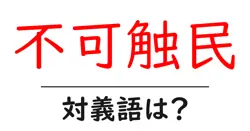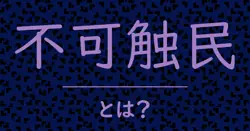不可触民とは?
不可触民(ふかしょくみん)とは、インドにおけるカースト制度の中で、最も低い位置に置かれた人々を指します。これは、彼らが社会から差別を受け、伝統的に貧困や苦労を強いられてきたことを示しています。不可触民という言葉は、他の人には触れてはいけない、という意味合いを持つところから来ており、長い間、社会的に孤立させられてきました。
不可触民の歴史
不可触民は、インドのカースト制度の下で、主に「アチュート」と呼ばれる存在に分類されます。カースト制度は、インドのヒンズー教の社会構造で、非常に古い歴史を持っています。この制度の中で、人々は生まれながらにして異なる階級に生まれ、不可触民はその中でも特に厳しい差別を受けていました。近代に入り、彼らの権利を守るための運動が盛んになり、国連が人権を重視するようになったことで、少しずつ状況は改善されてきました。
現在の不可触民の状況
現在、インドでは不可触民に対する法律が整備され、差別を禁じる政策が取られています。しかし、実際には社会的な偏見は根強く残っており、不可触民は依然として貧困や教育の機会が十分ではないという問題を抱えています。たとえば、以下の表は、不可触民の現状についてのデータを示しています。
| 問題 | 発生率 |
|---|---|
| 識字率 | 約50% |
| 教育機会の不平等 | 約70% |
| 貧困層に属する割合 | 約45% |
不可触民の支援活動
多くのNGO(非政府組織)や政府の取り組みが、不可触民の改善のために行われています。支援活動には教育プログラムや職業訓練が含まれており、彼らが社会に参加し、生活を向上させるための努力が続けられています。
まとめ
不可触民という存在は、インドの歴史の中で非常に重要です。彼らが直面している課題は簡単には解決できませんが、理解と支援が必要です。
カースト制度:インドの伝統的な社会階層制度で、土着の身分や職業に基づいて人々が分類される仕組み。不可触民はこの制度内で最も低い位置に属し、主に汚れた仕事や職業を担っています。
社会的排除:特定のグループが社会の一部から隔離され、経済的、政治的、文化的な活動に参加できない状態。不可触民はこの現象の被害者となりがちです。
ダリット:インドの不可触民を指す言葉で、「壊されるもの」という意味。また、苦しんでいる人々を指す概念でもあり、社会的な地位向上を目指す運動もあります。
差別:人々がその出自や地位に基づいて不平等に扱われること。不可触民はカースト制度において差別の対象となることが多いです。
人権:すべての人間が享有すべき基本的な権利。不可触民の扱いに関しては人権問題が大きく取り上げられています。
平等:すべての人間が同じ権利を持ち、差別されない状態。不可触民の権利向上のためには、社会全体での平等の理解と推進が重要です。
教育の機会:個人が教育を受ける機会。不可触民は教育制度からの排除が多いため、教育の機会を得ることが彼らの社会的地位向上に繋がります。
被差別部落民:日本における不可触民の一種で、歴史的に差別を受けてきた人々を指します。
アウトカースト:インドのカースト制度において、社会の最下層に位置し、一般的に差別される人々を指します。
ダリット:インドの社会における不可触民を意味し、伝統的に社会的、経済的に疎外されてきた人々を指します。
カースト:社会階層の一種で、インドなどの伝統的な社会で見られる厳格な身分制度。不可触民はこのカースト制度において最も底辺に属する人々を指します。
ダリット:インドのカースト制度において、不可触民を指す言葉で、彼らを取り巻く社会的不平等や差別に対抗する運動も存在します。
差別:社会の中で特定の集団や個人が不利益を被る行為や状態。不可触民は特に差別されやすい立場にあります。
社会的排除:特定の集団が社会から干渉や参加を拒否されること。不可触民はその代表的な例とされ、その権利や機会が制限されることが多いです。
人権:すべての人が持つ基本的な権利。不可触民は特にその人権を侵害されることが多いため、様々な活動が彼らの権利を守るために行われています。
社会運動:社会的不公正や差別に対抗するための集団的な活動。不可触民の権利を主張する運動も広がりを見せています。
変革:社会的な構造や制度を改善しようとする取り組みのこと。不可触民の状況を改善するための変革が求められています。
教育:不可触民がより良い生活を送るための重要な要素とされ、彼らへの教育の機会を提供する運動が必要とされています。
不可触民の対義語・反対語
不可触民(フカショクミン)とは? 意味や使い方 - コトバンク
不可触民(フカショクミン)とは? 意味や使い方 - コトバンク
不可触民の関連記事
社会・経済の人気記事
次の記事: 両替手数料とは?知って得するお金の話共起語・同意語も併せて解説! »