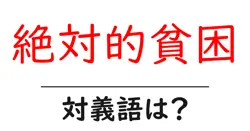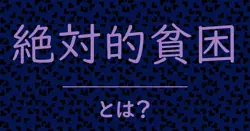絶対的貧困とは何か
私たちの生活は、さまざまなものに恵まれていることが多いですが、世界にはそうでない人たちもいます。絶対的貧困とは、そのような人たちが直面する問題の一つです。具体的には、基本的な生活を営むために必要な資源が不足している状況を指します。例えば、食べ物や清潔な水、衣服、住居、医療など、最低限の生活に必要なものが手に入らないことを意味します。
絶対的貧困の基準
国際的には、絶対的貧困の基準が定められています。例えば、2021年現在の基準では、一日に使えるお金が1.90米ドル(約200円)以下の生活をしている人を絶対的貧困と定義しています。この基準は、低所得国の生活費をもとに設定されています。
絶対的貧困の現状
世界遺産や美しい自然で有名な国々でも、実際には多くの人が絶対的貧困に苦しんでいます。国連によると、2021年には約6億人が絶対的貧困に分類されるとされています。これは、世界全体の人口の約9%にあたります。
絶対的貧困に関する統計
| 年 | 絶対的貧困者数(億人) | 全人口に対する割合(%) |
|---|---|---|
| 2015年 | 7.3 | 10% |
| 2021年 | 6.0 | 9% |
絶対的貧困の影響
絶対的貧困は、ただ食料や住居が不足しているだけでなく、教育や医療の機会も奪います。教育を受けることができないと、将来的によりよい職業に就くことが難しくなり、貧困の連鎖が続いてしまいます。また、医療が不足しているために健康を維持できず、さらに貧困が深刻化する危険もあります。
どのように貧困を解決するのか
絶対的貧困を解決するためには、国際的な支援や地域の取り組みが重要です。教育プログラムや職業訓練、生活費の支援など、さまざまな方法が検討されています。私たちができることは、貧困問題を知り、関心を持つことです。それにより、より多くの人が支援の必要性を理解し、行動を起こすことが可能になります。
絶対的貧困 相対的貧困 とは:私たちの社会には、貧困という言葉があります。しかし、貧困には2つの種類があるんです。それが「絶対的貧困」と「相対的貧困」です。まず、絶対的貧困とは、最低限の生活を維持できない状態を指します。例えば、食べるものがない、住む場所がないといった状況です。国連によると、1日あたりの所得が1.9ドル(約200円)以下の人が絶対的貧困に該当します。これに対して相対的貧困は、社会全体の中での貧困を表しています。たとえば、周りの人たちと比べて、収入が著しく少ない状態を指します。日本では、家庭の収入が全国平均の半分以下の人が相対的貧困に該当します。つまり、相対的貧困は他の人と比べての立場を考えるので、自分がどれだけ困っているかが分かりやすくなります。絶対的貧困と相対的貧困、この2つを理解することで、私たちが本当に大切にすべきことが見えてくるのです。
相対的貧困:特定の社会の中で、他者に比べて経済的に恵まれていない状態を指します。この場合、生存に必要な最低限の収入が不足しているわけではなく、生活水準が周囲より明らかに低いとされることが特徴です。
貧困線:絶対的貧困を測るために定められた収入基準のことです。通常、1日あたりの最低限必要な食料費や生活費を元に算出され、これを下回ると貧困と見なされます。
生活保護:経済的に困窮している人々を支援するための公的制度です。絶対的貧困状態にある人が最低限の生活を営むために必要なIncome(source:収入)を提供します。
社会的排除:貧困層が社会の中で十分な支援や機会を得られない状態を指します。この状況では、教育や雇用、医療といった重要なサービスへのアクセスが制限されます。
発展途上国:経済的発展がまだ不十分で、絶対的貧困の問題が深刻な国を指します。これらの国では、貧困の解消や生活水準の向上が重要な課題となっています。
経済格差:富裕層と貧困層との間にある資産や収入の差を指します。この格差が広がることで、貧困問題がさらに深刻化することがあります。
教育:貧困から脱却するために重要な要素です。教育を受けることで、より良い仕事に就く機会が増え、経済的に自立できる可能性が高まります。
健康:絶対的貧困の影響を受ける要因の一つです。貧困状態にあることで、十分な医療を受けられず、健康を損ねるリスクが高まります。
持続可能な開発:貧困問題を解決するための視点の一つで、経済成長と環境保護、社会的包摂を両立させることを目指します。
相対的貧困:経済的な状況が他の人々と比較して劣っている状態を指します。絶対的貧困とは異なり、基準となる生活水準以上の人々がいる集団の中での位置を重視します。
貧困:一般的に必要最低限の生活に必要な資源(食料、住居、医療など)が欠乏している状態を指します。
経済的困窮:資金や資源が不足しているため、基本的な生活ニーズを満たすことが難しい状況を示します。
生活困難:日常生活を営む上で、経済的な理由により困難を感じる状態を表します。
絶対的困窮:必要不可欠な物資が全く手に入らない状況で、基本的な生存が脅かされる状態を指します。
貧乏:十分な経済的資源がないため、生活が不自由である状態を指します。
低所得層:収入が一般的な水準に比べて非常に低い人々を指し、生活の質が影響を受けることが多いです。
飢餓:十分な食料が入手できず、栄養不足や空腹状態にある状況を指します。
社会的孤立:貧困により、社会的なつながりやサポートが不足している状態を意味します。
資源不足:生命維持に必要な物資やサービスが少なく、生活に困難さをもたらしている状況を示します.
相対的貧困:相対的貧困とは、一定の地域や社会の基準に照らし合わせて、他の人々に比べて経済的に恵まれていない状態を指します。具体的には、平均的な収入の50%未満で生活している人々が相対的貧困者とされることが多いです。
絶対的貧困ライン:絶対的貧困ラインとは、食料や生活必需品を満たすために最低限必要な収入の基準です。国際的には1日1.90ドル未満の生活をしている人が絶対的貧困にあたります。
経済的な格差:経済的な格差とは、収入や資産、機会などでの不平等な分配を指します。絶対的貧困はこの格差のひとつの側面として現れることがあります。
貧困の悪循環:貧困の悪循環とは、貧困状態にある人々が教育や健康、職業の機会に恵まれず、その結果、貧困から抜け出せない状況を指します。貧困が次の世代にも引き継がれることが多いです。
社会的排除:社会的排除とは、経済的な理由や特性により社会の活動に参加できない状態を指します。絶対的貧困にある人々は、教育や医療、雇用などにアクセスしにくくなることがあります。
開発援助:開発援助とは、発展途上国や貧困地域の経済発展を支援するために、他国や国際機関が行う資金や技術の提供を指します。絶対的貧困の解消を目的としています。
食料安全保障:食料安全保障とは、適切な栄養を得るために必要な食料が十分に供給され、アクセス可能である状態を指します。絶対的貧困が広がると、これが脅かされることがよくあります。
教育の普及:教育の普及とは、多くの人々が教育を受けられるようにすることを指します。教育が普及することで、絶対的貧困の克服に繋がる可能性が高まります。
福祉政策:福祉政策とは、貧困層や弱者を助けるための政府の施策を指します。絶対的貧困の解消を目指した支援が行われることが重要です。
非政府組織 (NGO):非政府組織(NGO)とは、政府に依存せず、社会の問題解決のために活動する非営利団体を指します。貧困の解消に向けたプロジェクトが多く展開されています。
絶対的貧困の対義語・反対語
絶対的貧困とは?相対的貧困との違い、世界の現状、原因、解決策も
相対的貧困とは?絶対的貧困との違いや相対的貧困率についても学ぼう