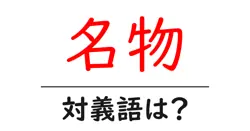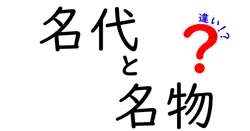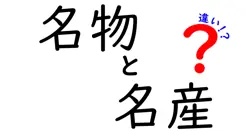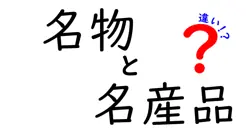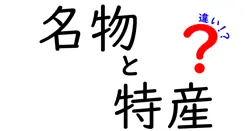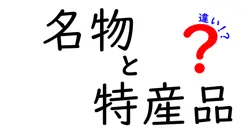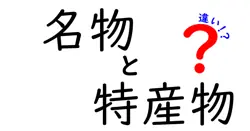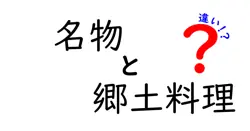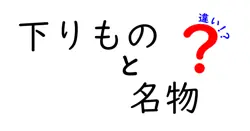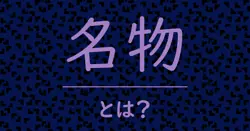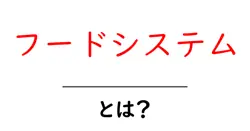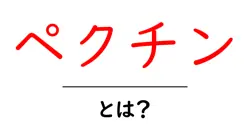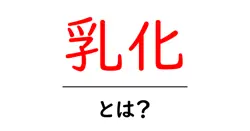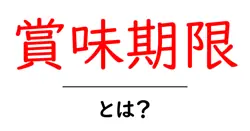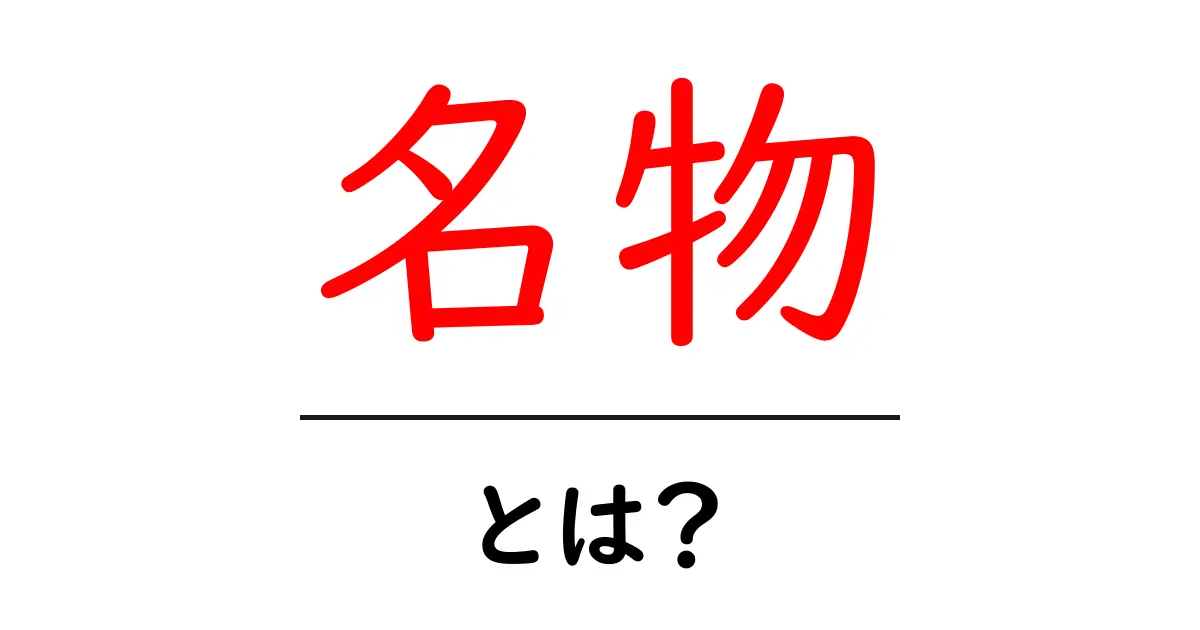
名物とは?
「名物」という言葉は、特定の地域や場所で有名な食べ物や商品、観光名所などを指します。ここでは、日本の名物について詳しく説明していきます。
名物の種類
名物には、主に以下の2種類があります。
1. 食べ物の名物
日本各地には、その地域特有の食べ物が多くあります。例えば、以下のようなものがあります。
| 地域 | 名物 |
|---|---|
| 北海道 | ジンギスカン |
| 大阪 | たこ焼き |
| 福岡 | 博多ラーメン |
2. 観光名所の名物
名物は食べ物だけではなく、観光名所や地域の特産品にも関連しています。例えば、京都の金閣寺や奈良の大仏などが挙げられます。これらは多くの観光客を惹きつける名物です。
なぜ名物が大切なのか?
名物はその地域の文化や歴史を反映しています。地元の食文化を知ることは、その地域を理解する手助けになります。また、名物を通じて地域経済を支えることにも繋がります。
名物を楽しむ方法
名物は実際に訪れて食べたり、見たりすることが一番の楽しみ方ですが、最近ではネットでも購入できる名物も増えてきました。旅に行けない場合でも、通販で気軽に楽しむことができます。
まとめ
名物はその地域の特徴や魅力を伝える大切な存在です。旅行の際には是非、名物を食べたり、観光地を訪れたりして、その地域の文化を体験してみましょう。
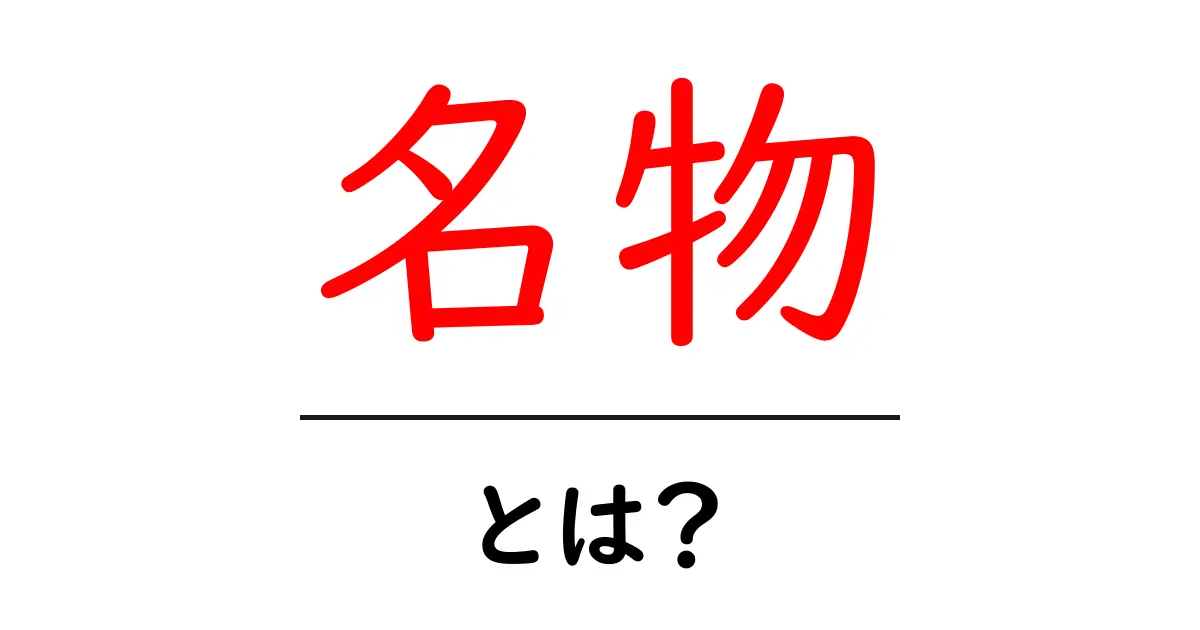
仙台 名物 とは:仙台にはたくさんの名物がありますが、その中でも特に人気のある料理や特産品をいくつか紹介します。まず、仙台の名物と言えば「牛タン」です。牛タンは、厚切りにして焼いたもので、外は香ばしく、中は柔らかい食感が特徴です。また、仙台は「ずんだ餅」でも有名です。ずんだ餅は、枝豆をすりつぶしたものをお餅にのせたお菓子で、甘さと香ばしさが絶妙にマッチしています。さらに、仙台の「笹かまぼこ」も人気です。これは、魚のすり身を使って作るおつまみで、ふわふわとした食感が特徴です。これらの料理は、特に観光で訪れる人たちにも大変好評です。仙台の食文化は、豊かな自然に育まれたおいしい食材を使い、地域の伝統を大切にしています。だからこそ、訪れた際にはぜひ地元の名物を楽しんでほしいと思います。仙台の名物は、食べるだけでなく、地域の文化や人々の思いも感じられる素敵なものばかりです。
神社から広まった 江戸 名物 とは:江戸時代には、多くの神社が存在し、さまざまな文化が栄えました。そして、その神社を訪れる人々が楽しんだ名物料理も多くありました。まず一つ目は、神社のお祭りで食べられる「団子」です。団子は、もち米を使った甘くて柔らかいお菓子で、特に春には桜の花がついた団子が人気です。次に、「おでん」があります。これは、具材をだしで煮込んだ料理で、寒い冬には特に好まれます。神社の境内で、温かいおでんを楽しむ人たちの姿がよく見られました。また、神社の近くで振る舞われる地元の鮮魚を使った「刺身」も、江戸名物の一つです。このように、神社を通じて広まった料理は、江戸の町の人々の生活に欠かせない存在でした。神社の儀式や祭りは、人々が集まる重要なイベントであり、その際に楽しむ料理も、地域のアイデンティティを形成していました。江戸名物は単なる食べ物ではなく、地域の文化や人々の絆とも深く結びついているのです。これらの江戸名物を食べることで、当時の人々の生活を感じることができます。今でも神社で行われる祭りには、多くの人々が集まり、美味しい料理を楽しむ光景が見られます。
福岡 名物 とは:福岡名物は、福岡県で特に人気がある食べ物や飲み物のことを指します。代表的な名物として有名なのは、博多ラーメンや明太子、もつ鍋などです。博多ラーメンは、濃厚な豚骨スープにストレートの細麺が特徴で、トッピングにはチャーシューやネギがよく合います。また、明太子は辛い味付けがされていて、ご飯のお供やおにぎりの具として大人気です。さらに、もつ鍋は、牛や豚の内臓を使った鍋料理で、特に寒い季節に食べられています。福岡では、これらの名物を楽しむための専門店もたくさんあります。観光で訪れた際には、ぜひこれらのグルメを味わってみてください。福岡の名物は、地域の歴史や文化を反映しており、食べることでその土地のことを深く知ることができます。名物料理を通して、福岡の魅力を存分に感じてみましょう。
特産品:特定の地域で生産され、その地域を代表する商品や食品のこと。名物と同じように、地域の名を馳せるものです。
名所:観光地や有名な場所を指します。名物と共に訪れることで、その地域をより深く体験できます。
郷土料理:その土地ならではの食文化を反映した料理のこと。名物がその中に含まれることが多いです。
お土産:旅行の際に買って帰る品物のこと。名物をお土産として持ち帰ることで、旅行の思い出を楽しむことができます。
地元:特定の地域やその地域に住む人々を指します。名物は地元の人々によって大切にされています。
伝統:長い歴史を経て受け継がれてきた文化や習慣のこと。名物の多くは、地域の伝統に基づいています。
観光:旅行や見物を目的とした行動やその活動のこと。名物は観光の重要な要素となることが多いです。
食文化:特定の地域や国の食事に関する独自の慣習や知識のこと。名物は食文化の一部をなしています。
魅力:何かが持つ引き寄せる力や素晴らしさのこと。名物は地域の魅力を引き立てる重要な要素です。
イベント:特定の日に行われる行事のこと。名物に関連したイベントが開催されることも多く、地域を活性化させます。
名産品:特定の地域で特に有名な商品のこと。地域の特産物として知られ、人々に愛されている。
特産物:ある地域特有の自然環境や文化から生まれる製品のこと。その場所でしか手に入らないことが多い。
名物料理:特定の場所で特に有名な料理のこと。その土地の伝統や食材を活かした料理。
地元名物:その地域に住む人々が誇りに思う特有の品や文化のこと。観光客にも人気がある。
特長:ある物や事柄の他と異なる特徴や魅力のこと。特に際立つポイントがある場合に使われる。
シンボル:ある地域や文化を象徴するもの。名物はその場所のシンボルとなることが多い。
定番:定期的に人気があるもの、または選ばれやすいもののこと。名物は地域の定番アイテムの一つです。
特産品:特定の地域で生産され、その地域を代表する商品や食べ物のことを指します。名物は特産品として有名なものが多いです。
伝統:長い歴史を持ち、代々受け継がれてきた文化や習慣のことです。名物は、その地域の伝統や習慣に根ざしていることが多く、地元の人々に愛されています。
観光:旅行や観光を通じて、特定の場所を訪れることです。名物は観光地の大きな魅力の一つで、多くの観光客が名物を目当てに訪れます。
地域振興:地域の産業や文化を発展させるための取り組みや活動のことを指します。名物は地域振興の一環として地元の魅力をアピールする手段となります。
グルメ:美味しい食べ物や飲み物を楽しむことを指します。名物料理はグルメとして多くの人に親しまれ、特に食に関心が高い人々にとって大きな魅力となっています。
イベント:特定の目的のために開催される行事や催し物のことです。名物は地域のイベントで取り上げられることが多く、地元の食や文化を広める役割を果たします。
市場:商品の売買が行われる場所やシステムのことです。名物が売られている市場は、地元の人々や観光客にとって人気のスポットとなります。
食文化:特定の地域や国における食に関連する習慣や伝統のことです。名物はその地域の食文化を代表する存在として位置づけられています。