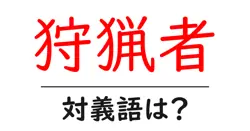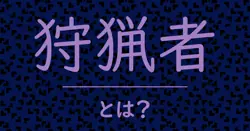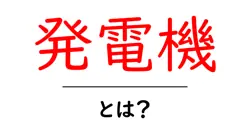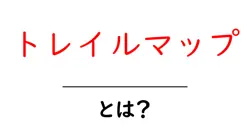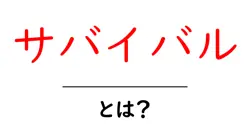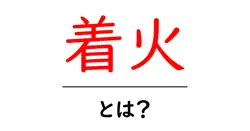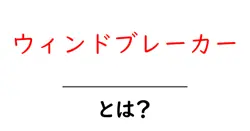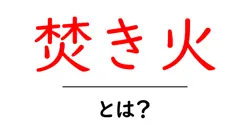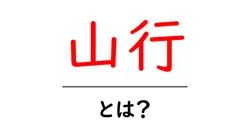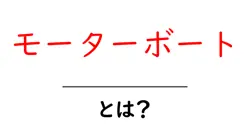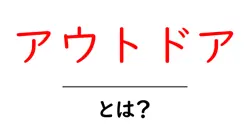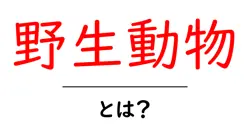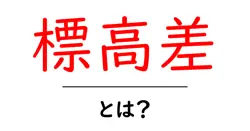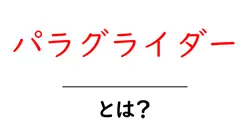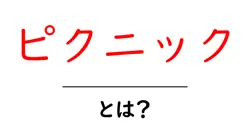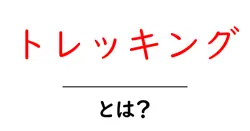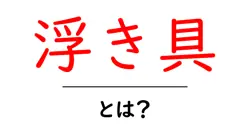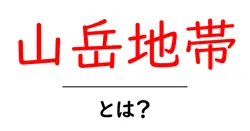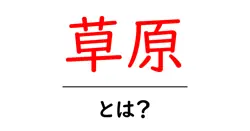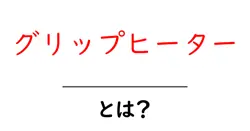狩猟者という言葉を耳にしたことがある人も多いでしょう。狩猟者とは、野生動物を捕らえることを目的とした人のことを指します。狩猟は、古代から行われてきた活動で、今でも多くの国や地域で行われていますが、その内容やルールは時代や場所によってさまざまです。
狩猟の歴史
狩猟の歴史は非常に古く、初期の人類が食料を得るための主要な手段でした。狩猟によって獲得した肉や皮は、生活の糧として欠かせないものでした。その後、農業が発展するにつれて、狩猟の役割は少しずつ変わっていきました。
現代の狩猟
現代においては、狩猟は食料の確保だけでなく、自然環境の保護や管理にも関わっています。特に、野生動物の個体数が増えすぎて生態系に影響を及ぼす場合、狩猟が必要とされることがあります。しかし、狩猟を行うには様々な法律や規制があり、それを守ることが求められます。
狩猟の魅力
狩猟者の活動にはいくつかの魅力があります。たとえば、自然の中での体験や、動物との駆け引き、仲間との絆を深めることなどです。また、狩猟を通じて自分の食料を確保するという経験は、自己満足感をもたらします。
注意点
しかし、狩猟には注意が必要です。法律を守ることや、安全対策を講じることが大切です。また、獲物を無駄にしない心構えも不可欠です。狩猟の際は、必要な許可を取得し、倫理的に行動することが求められます。
| 魅力 | 注意点 |
|---|---|
| 自然とのふれあい | 法律や規制を守ること |
| 仲間との絆を深める | 安全対策の徹底 |
| 自己満足感 | 獲物を無駄にしない |
狩猟者という活動は、魅力と責任が伴う重要な活動です。興味がある人は、まずは狩猟についてしっかり学ぶことから始めてみてはいかがでしょうか。
狩猟:動物を捕まえること。狩猟者はこの活動を行う人を指します。
ハンター:狩猟を行う人の英語表現。特に野生動物の捕獲に従事する人を指します。
狩猟法:狩猟に関する法律や規則で、狩猟者が守らなければならないルールを定めています。
獲物:狩猟で捕まえる対象となる動物を指します。狩猟者にとっての目的でもあります。
猟犬:狩猟を助けるために訓練された犬のこと。獲物を追い詰めたり、探し出したりする役割を果たします。
エコロジー:生態学のこと。狩猟者は生態系への影響を考慮する必要があり、持続可能な狩猟が求められます。
TKYの会:狩猟者や関連する専門家たちの団体で、狩猟に関する知識の普及や技術向上を目指しています。
射撃:狩猟で使用するための火器を扱う技術を指します。狩猟者は狙いを定めて獲物を捕らえます。
ハンター:動物を捕まえるために狩りをする人。特に狩猟を生業とする人を指すことが多い。
狩人:狩猟を行う人を指し、特にその地域での伝統や技術を持った人を意味する場合もある。
狩猟者:狩りを通じて生計を立てる人を指し、狩りの技術や知識を持つことが求められる。
採集者:通常は植物や果物を収穫する人を指すが、時には狩猟も行うことから関連性がある。
フィッシャー:釣りを専門とする人。狩猟者とは異なるが、自然から食料を得るという点で共通する。
猟師:特に森林や野原での狩猟を行う職業の人。動物の生態や環境に精通していることが多い。
狩猟:食料や皮などを得るために、野生動物を捕獲する行為。狩猟は古くから行われており、現代でもスポーツや伝統的な文化の一部として行われることがある。
罠:狩猟において動物を捕まえるために使用される装置。さまざまな種類があり、動物が近づくと自動的に反応して捕まえる仕組みがある。
獲物:狩猟や捕食の対象となる動物のこと。狩猟者は特定の獲物を狙って狩りを行い、肉や皮、骨を利用する。
狩猟免許:狩猟を行うために必要な資格。国や地域によって異なる規定があり、一定の講習を受けたり試験に合格したりする必要がある。
バイオトピカル:狩猟に関する生態系や生物多様性を考慮した狩猟法。動物の個体数や環境への影響を評価し、 Sustainable での狩猟を促進する。
狩猟シーズン:特定の期間に狩猟が許可される仕組み。多くの地域では、繁殖期や生息数などに配慮して、狩猟可能な動物とその数量が規定されている。
狩猟文化:狩猟が社会・コミュニティにおいて果たす役割や価値観のこと。多くの地域で伝統的な手法が継承され、食文化や祭りと関連していることがある。
生態保護:狩猟者が獲物やその生息環境を保護するための取り組み。持続可能な狩猟を実施するため、獲物の個体数管理や環境保全が求められる。
自然観察:狩猟と関連していても、動物を捕まえるのではなく、周囲の自然や生き物を観察する活動。狩猟者でも興味を持つ人が多く、自然と共存する視点をもつ。