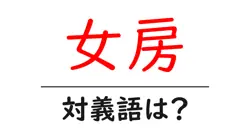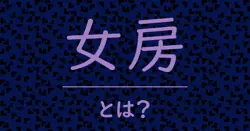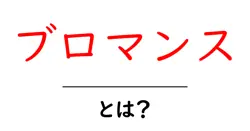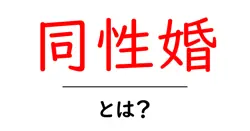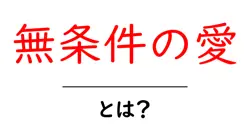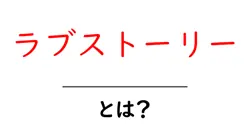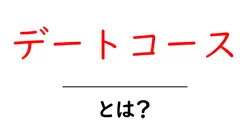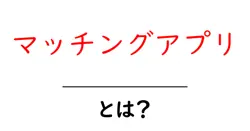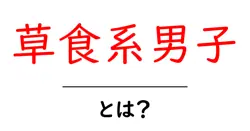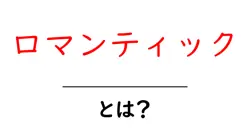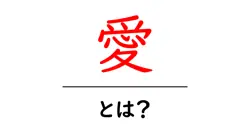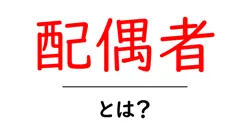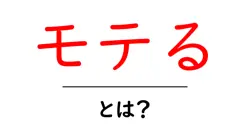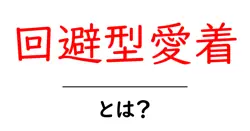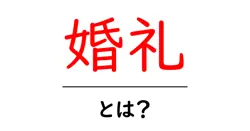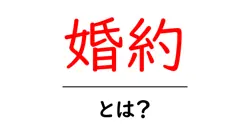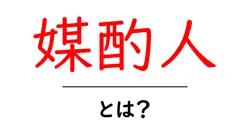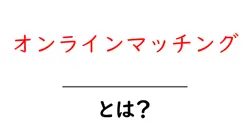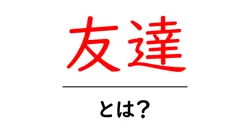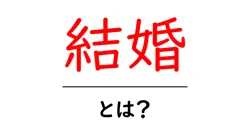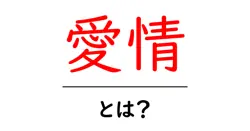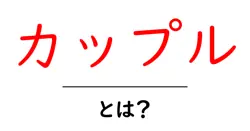女房とは?
「女房」という言葉は、主に夫が自分の妻を指して使う表現です。妻という言葉よりも、より親しみを込めた呼称として使われることが多いです。日本の文化では、家族や夫婦の絆が深く結びついているため、こうした言葉が生まれました。
女房の語源
「女房」という言葉の語源にはいくつかの説があります。一つの説では、「女」と「房」が結びついてできた言葉だと言われています。「女」は女性を意味し、「房」は部屋を意味するため、一緒に住む女性としての意味合いが感じられます。このように、女房はただの配偶者ではなく、生活を共にする大切な存在としての役割を表しています。
女房の役割
女房は、家庭を支える大きな存在であり、夫のサポートをするだけではなく、子どもたちの育成や家庭の管理など、多くの役割を果たしています。以下に女房の代表的な役割をまとめてみました。
| 役割 | 説明 |
|---|---|
| 家庭管理 | 日々の食事や掃除、洗濯などを行い、家庭を整える。 |
| 子育て | 子どもを育て、教育を考える役割を担う。 |
| 精神的な支え | 夫や家族の心の支えとなる存在。 |
女房とパートナーシップ
現代においては、女房とは単に結婚関係にある女性というだけでなく、良きパートナーとしての関係も求められます。夫婦はお互いを尊重し合い、意見を共有することが大切です。女房が夫にとっての強いサポーターであると同時に、夫も女房の意見や気持ちを尊重することが理想的です。
まとめ
女房は、ただの妻ではなく、家庭全体を支える重要な存在です。互いに支え合い、成長していくことが、より良い夫婦関係を築くための鍵となります。
光る君へ 女房 とは:「光る君へ 女房」という言葉は、特別な意味を持つ表現です。きっと、あなたはこのフレーズを聞いたことがあるかもしれません。これは、愛しい人への深い思いを表すもので、特に奥さんやパートナーに対して使うことが多いです。日本語の言葉の中には、そうした特別な表現がたくさんあります。「女房」という言葉は、もともと妻を指す言葉ですが、単なる呼び名だけではなく、愛情や絆を感じさせるものです。この表現がどのように使われているかを知ることで、もっと深く愛について考えることができます。また、このフレーズは歌や詩の中でも使われることが多く、感情豊かな言葉でもあります。歌の中では、相手に伝えたい特別なメッセージが込められていて、聴いた人が心に響くことが多いです。さらに、「光る君へ」という言葉には、未来への期待や希望が込められていることもあります。つまり、愛する人と一緒に過ごすことの大切さを感じさせてくれます。ですから、この言葉はただの表現ではなく、心の奥深くに響くものなのです。これから、ぜひこの言葉を使って、大切な人への気持ちを伝えてみてください。
女房 とは 平安时代:平安時代は、日本の歴史の中でも特に文化が花開いた時代です。この時代において、「女房」とは、平安貴族の女性たちを指します。女房たちは、華やかな衣装をまとい、優雅に振る舞うことが求められました。彼女たちの生活は、貴族の家の中で重要な役割を果たしていました。 女房は、家事や子育てを行う一方で、詩や歌を書いたり、絵を描いたりして文化を支える役割も持っていました。例えば、紫式部や清少納言といった著名な女房たちは、自らの才能を発揮し、多くの文学作品を残しています。これらの作品は、今でも日本文学として愛されています。 また、女房たちは、家族の名誉を守るために、政治的な役割も担うことがありました。後宮での生活を通じて、彼女たちは時には政略結婚を通じて、家族の地位を高める役割を果たしていました。 このように、平安時代の女房は、ただの妻や母親だけではなく、文化や政治にも関与する重要な存在だったのです。彼女たちの生き方は、今の私たちにとっても非常に興味深いものです。女房たちの魅力を知ることで、平安時代の文化をより深く理解できるでしょう。
女房 とは 平安時代:平安時代(794年~1185年)は、日本の歴史の中で特に文化が栄えた時代です。この時期において「女房」とは、宮廷に仕える女性たちのことを指しました。女房たちは、貴族や皇族に仕え、さまざまな役割を担っていました。彼女たちは、主に内廷での生活を支えるために働き、食事の準備や衣服の手入れ、さらには教育や家庭の運営などを担当していました。また、女房たちは、文才に秀でた人も多く、和歌や物語を詠むことが評価されていました。特に、平安時代の文学作品である「源氏物語」や「枕草子」には、女房たちの生活や感情が描かれています。女房の存在は、当時の文化や社会に深く根付いており、彼女たちの生活スタイルや役割を知ることは、平安時代を理解する上で非常に重要です。女房たちは、ただの家事をこなすだけでなく、文化を支えていた重要な存在だったのです。今でも、彼女たちの影響は日本の歴史や文化に名残を残しています。
源氏物語 女房 とは:「源氏物語」は平安時代に書かれた日本の古典文学で、主人公の光源氏の恋愛や人生が描かれています。そして、その物語の中にはたくさんの女性たちが出てきます。その中で特に「女房」と呼ばれる役割の女性たちがいます。女房とは、貴族の家に仕える女性たちで、主にお手伝いや家事を行う仕事を持っていました。女房は、自分の主人やその家族のために尽力し、時には一緒に遊んだり、相談を受けたりする存在でもありました。彼女たちは単なる召使いではなく、知識や教養が求められ、文才を持つこともありました。このため、女房は家の中で重要な役割を果たし、時には家庭の代弁者とも言える存在でした。「源氏物語」には印象深い女房たちの描写がありますが、彼女たちの生き方を知ることで、当時の平安貴族の生活や価値観をより深く理解できるでしょう。他にも、女房の文化やその後の女性の地位に与えた影響について考えることも面白いです。
野球 女房 とは:野球において「女房」という言葉は、主に捕手のことを指します。なぜ「女房」と呼ばれるのかというと、昔の言い回しに由来しています。捕手は投手と密に連携を取り、試合をリードする大事なポジションです。その役割は、ストライクやボールの判定の他、投手に対してサインを出したり、守備の指示をしたりすることです。また、捕手は対戦相手のバッターの動きをよく観察し、戦略を立てるために重要なポイントとなります。日本のプロ野球では、素晴らしい捕手たちが多く存在し、彼らの活躍が試合の鍵を握ることもしばしばです。このように、「女房」は単なる呼び名のことではなく、野球チームにとって欠かせない役割を果たしています。捕手がしっかりと仕事をすることで、チーム全体のパフォーマンスが向上すること間違いなしです。
コミュニケーション:女房と夫が良好な関係を築くために必要な情報や意見の交換を指す。
妻:法律的に結婚した相手を指し、一般的に「妻」と呼ばれることが多いです。
奥さん:親しみを込めて女性の配偶者を指す呼び方で、友人や知り合いに対して使われることがあります。
嫁:主に結婚した女性に対して使われる言葉で、特に家庭や親の視点から見た時に多く使われます。
配偶者:結婚した相手を指す正式な表現で、性別に関係なく用いることができます。
連れ合い:夫婦であることを強調する言葉で、特にお互いに支え合う関係を表現しています。
家内:伝統的な言い回しで家庭の中での妻を指す際に使われることが多いです。
妻:結婚した女性のこと。一般的には「妻」という言葉が使われますが、地域や文化によって呼び方が異なることもあります。
配偶者:結婚している相手のことを指す言葉で、夫または妻のことを包括的に表現します。カジュアルな言い回しではなく、法律や公式な文書でよく使われます。
家族:親子や親戚など、血縁関係や婚姻関係にある人々の集まりを指します。女房(妻)も家族の一員になります。
夫婦:結婚した男女のこと。夫婦はお互いに対する愛情や責任を持ち、共同生活を営むことが一般的です。
結婚:法律や宗教的な手続きを通じて、男女が正式に伴侶としての関係を持つことを指します。結婚は愛情の表現としても、社会的な役割を果たす重要な行為です。
嫁:一般的には他の家庭の女性を指す言葉で、自分の家庭に入った妻を指すこともあります。特に地域によって使い方が異なることがあり、相關する文化背景が影響します。
愛情:他者に対して持つ温かい感情や思いやりのこと。女房との関係を深めるためには、お互いの愛情が重要です。
家庭:家族が生活する空間や生活を共にする様子を指します。女房(妻)と共に営む家庭の形は、各家庭で異なります。
サポート:生活や仕事において、お互いに手助けや支援を行うこと。女房(妻)と良好な関係を築くためには、サポートし合うことが重要です。
パートナーシップ:夫婦や恋人間の協力関係を表し、お互いの役割や権利、責任を尊重し合うことを重視します。
女房の対義語・反対語
女房(にょうぼう) とは? 意味・読み方・使い方 - 国語辞書
女房衆(にょうぼうしゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク
女房の関連記事
恋愛・結婚の人気記事
前の記事: « 毎日できる!呼吸訓練の効果と方法共起語・同意語も併せて解説!
次の記事: 減算とは?基本からわかる計算の世界共起語・同意語も併せて解説! »