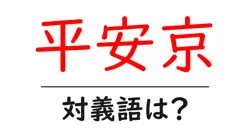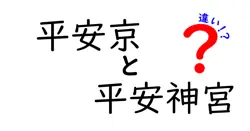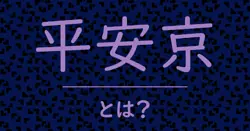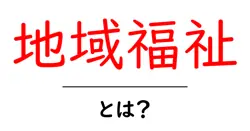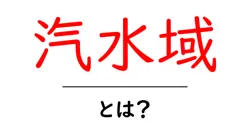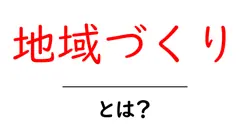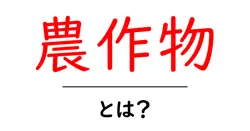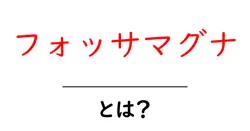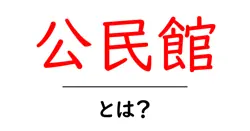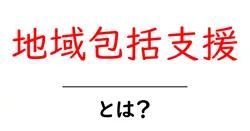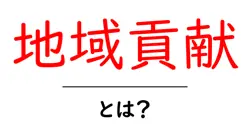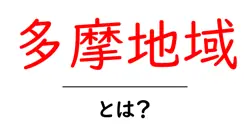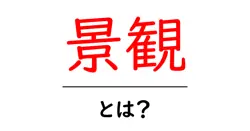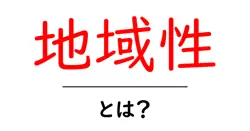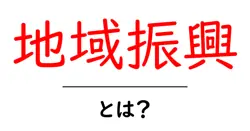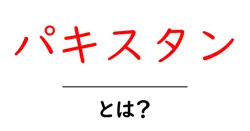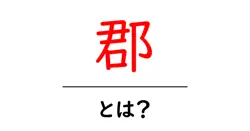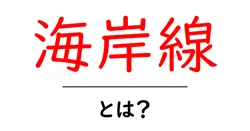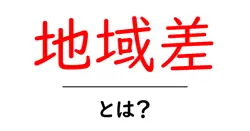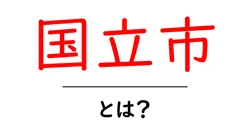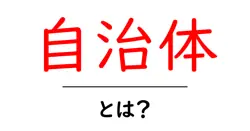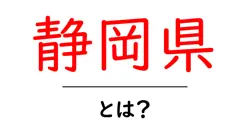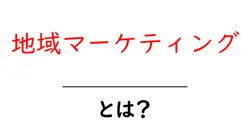平安京とは?
平安京は、日本の歴史において非常に重要な意味を持つ都市です。794年に桓武天皇によって建立され、約400年にわたって日本の都として機能しました。この都市は、今の京都市にあたりますが、当時は日本の文化、政治、そして経済の中心地でした。
平安京の歴史的背景
平安京は、当時の人々にとって理想的な場所と考えられ、東山と西山に囲まれた平地に作られました。この地形は自然災害を避けるため、また、周囲の田畑からの水の供給が容易だったからです。他の都市と同様に、平安京も鬼や悪霊から守るために、特定の位置に神社が建てられました。
政治と文化の中心地
平安京は、平安時代の貴族文化が栄えた場所でもありました。多くの文人や詩人がここで活動し、『源氏物語』のような文学作品が生まれました。また、平安時代には独特の和服や美術、音楽が発展し、今でも多くの人に愛されています。
平安京の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設立年 | 794年 |
| 面積 | 約15km² |
| 人口 | 推定10万人以上 |
| 公家文化 | 栄えた |
平安京の衰退とその後
しかし、平安京は平安時代末期に、外部からの侵略や内部の権力闘争によって次第に衰退していきました。その結果、1185年に鎌倉幕府が成立し、政治の中心が鎌倉に移りました。平安京はその後も存続しましたが、次第にその役割は薄れていきました。
今も残る平安京の影響
現在、京都市には平安京時代の名残が多く残っています。例えば、平安神宮や二条城などの歴史的建造物があります。また、平安時代の伝統的な行事や祭りも残っており、多くの観光客が訪れています。
まとめ
平安京は、日本の歴史において重要な都であり、その文化や政治の中心地として多くの影響を与えました。現在もその名残を感じることができ、訪れることで当時の文化を知ることができます。
平安京 とは 簡単に:平安京(へいあんきょう)は、日本の京都にあった古代の都で、794年から1868年までの長い間、日本の首都であり続けました。この都は、当時の天皇や貴族たちが住む場所として栄え、文化や政治の中心地でもありました。平安京は中国の都城を手本にして作られ、長方形の形をしているのが特徴です。また、周囲には山や川があり、自然に囲まれた美しい環境でした。平安京では、文学や芸術が盛んに発展し、『源氏物語』や『枕草子』などの名作が生まれました。また、官庁や神社仏閣も多く建てられ、歴史的な遺産がたくさんあります。平安時代は、平和な時代であり、貴族たちの優雅な生活が描かれています。その後、平安京は鎌倉時代に入ると、次第にその役割を失っていきますが、今でも多くの人々に親しまれています。観光地としても有名で、歴史を感じることができる場所です。平安京は日本の文化の根が育った場所とも言え、今もなおその影響を受け続けています。
羅生門 とは 平安京:「羅生門」は平安京に存在した門で、平安時代における京都の重要なランドマークの一つです。この門は、都の南西に位置しており、当時、多くの人々が行き交う重要な道路の入り口でした。そのため、商人や旅行者、貴族たちが行き来する場所でもあり、多くの人が出会う場所でもありました。 「羅生門」という名前は、もともと「羅生」という言葉から来ており、意味は「生まれる」ということです。この門は、平安京の中心地へとつながる道の入り口であったため、生活や文化が「生まれる」場所としても象徴的な存在でした。 歴史的には、羅生門は物語や伝説にも登場しています。特に、芥川龍之介の小説「羅生門」では、この門が舞台になり、様々な人の運命が描かれています。このように、「羅生門」はただの門ではなく、平安京の歴史や文化を感じることができる大切な場所なのです。 今では、実際の羅生門は残っていませんが、その名残や関連する文化財は多く存在しています。訪れることで、平安時代の雰囲気を感じることができるかもしれません。歴史や物語に思いを馳せると、さらなる楽しみが広がります。
京都:平安京が位置する場所で、日本の古都として有名。
天皇:平安京は平安時代の天皇の居住地であり、政治の中心地でもあった。
平安時代:平安京が建立された時期で、日本の歴史の中で文学や芸術が盛んになった時代。
寺院:平安京には多くの寺院が存在し、仏教が広まりました。代表的な寺院には清水寺や東寺がある。
文化:平安京は古典文学や美術が栄えた場所で、『源氏物語』などが生まれた。
摂政:平安時代には藤原氏が政治の実権を握り、摂政として権力を持った。
貴族:平安京は貴族社会であり、平安時代の貴族たちの生活や文化が形成された。
大内裏:平安京の中心に位置する皇居で、天皇が住んでいた場所。
平安京遷都:794年にそれまでの奈良から平安京へと都が移された歴史的な出来事。
風俗:平安期の風俗や生活様式が記録され、多くの文献に描写されている。
京都:平安京が設置された現在の京都市のこと。
平安時代の首都:平安京が8世紀から12世紀にかけて、日本の政治・文化の中心であったことから。
都:特に歴史的な文脈において、首都や中心地を指す言葉。
古都:歴史的な背景を持つ町や都市を指す言葉で、平安京もその一例。
日本の古都:日本における歴史的、文化的に重要な都市を指し、平安京がその一つである。
皇都:天皇が居住していた都市を意味し、平安時代の首都である平安京を指すことが多い。
平安合戦:平安京における戦いや出来事を指し、平安時代の文化的背景を理解する手助けとなる言葉。
平安時代:平安京が築かれた時代で、794年から1185年までの約400年間を指します。この時代には文化や文学が栄え、特に「源氏物語」などの作品が生まれました。
貴族:平安京では貴族が政治や文化の中心となっており、彼らの生活や価値観が平安時代の文化を形成しました。貴族たちは官職に就き、優雅な生活を送っていました。
平安京遷都:平安京は、桓武天皇により794年に奈良から移され、以後日本の首都として機能しました。この遷都によって、政権の中心が新たに平安京に移されました。
和歌:平安時代に盛んに詠まれた詩の形式の一つで、短歌や長歌などがあります。特に貴族たちの社交や文化活動の一環として重要な役割を果たしていました。
源氏物語:平安時代の紫式部によって書かれた、日本最古の長編小説です。平安京の貴族社会を背景に、主人公の恋愛や人生を描いています。
公家:平安時代の貴族の呼称で、皇族や高級官僚を指します。公家は主に貴族社会の上層部を形成し、政治や文化に深く関与していました。
平安京の地図:平安京を描いた古い地図のことです。平安京は碁盤目状に設計され、多くの寺院や宮殿が配置されています。この地図を見ることで、当時の都市構造が理解できます。
都街道:平安京から各地方へと伸びる主要な交通路を指します。これらの街道は、物資の運搬や人々の移動に重要な役割を果たしていました。
仏教:平安京で栄えた宗教の一つで、多くの寺院が建てられ、仏教文化が発展しました。特に浄土信仰や密教が広まりました。
歌道:和歌や詩を詠む技術を学ぶ道のこと。平安時代の貴族たちにとって、歌道は教養を高める重要な文化的活動でした。